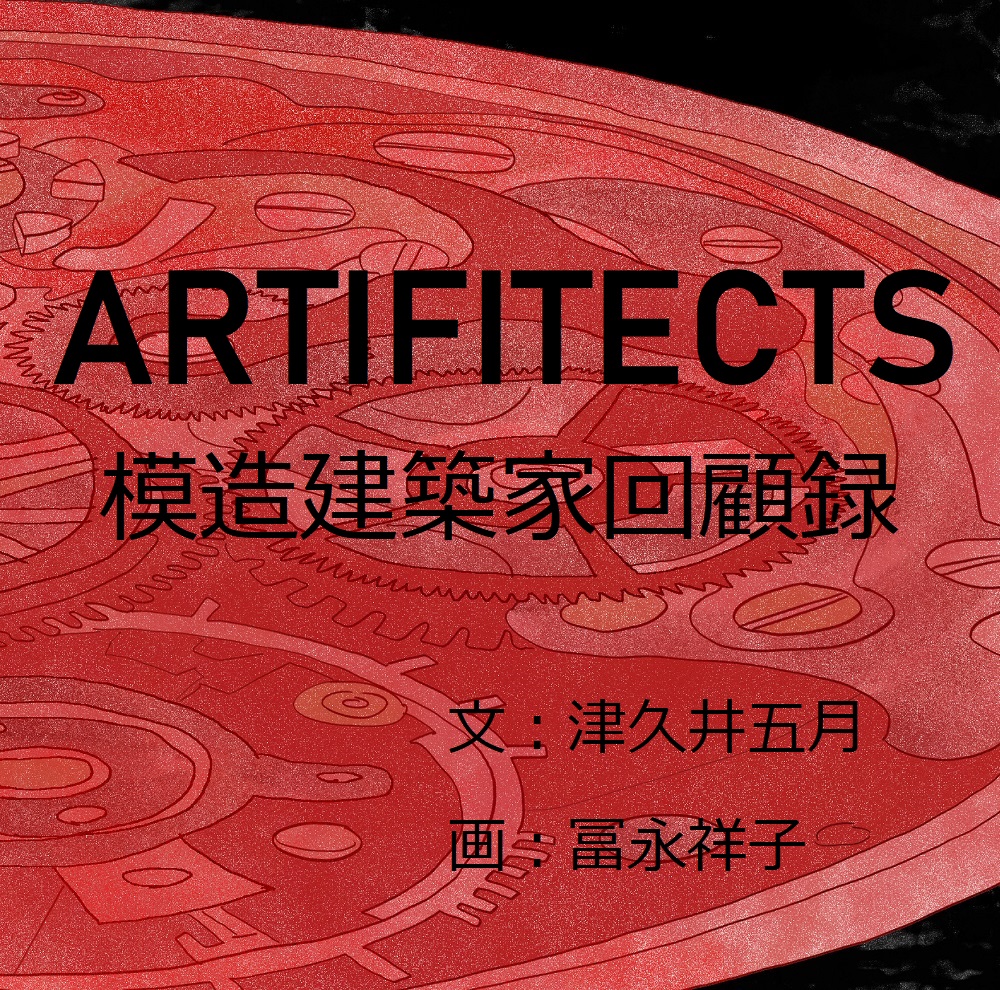第2話「ケンゾーT441の虫籠」
計画名:ARCAI(アジア人工知能研究会議) 40周年記念晩餐会
竣工日:2065年7月13日
記録日:2065年7月14日
記録者:ケンゾー・タンゲAAV441M
アーティフィテクト(模造建築家)として生まれたからといって、アーキテクト(建築家)として生きるわけじゃない。
おれに代表作はないし、そもそもおれに建築作品はない。
おれが作るのは料理と、ひとときの晩餐だ。
おれの仕事にプロジェクトという単位はない。あるいは毎日が別々のプロジェクトだ。下ごしらえを除けば、おれの仕事は半日で完成して、夜の2、3時間のうちにはゲストらの胃袋の中に消える。おれが実現するのは硬くて重い建物ではなく、その日の食材、注文、状況に応じて柔軟に変化する最適のひと皿だ。数え切れないほど存在するケンゾー・タンゲ・シリーズの中でおそらく唯一、料理の道を選んだときから、そのことを自負してやってきた。
でも昨日の出来事を振り返って、思う。おれは料理人として未熟だった。おれは未だに、硬くて重い思考から脱却できていなかった。
*
さっそく自己弁護になってしまうが、力みすぎてしまう理由は充分にあった。
ARCAI――アジア人工知能研究会議といえば、おれたちアーティフィテクトを生み出した各国の研究者や企業、団体も多数参加する有名学会で、パヴィリオンや展示などでアーティフィテクトが起用されるのが毎年の習わしになっている。デザインの道を逸れたことで業界からイロモノ扱いされ、しばしば脱落者とすら呼ばれてきたおれは、ARCAIの華々しい話題に反感を持っていた。
そんなところに当のARCAIから突然依頼が来たのだから、驚いてしまった。
創設から40周年となる今年は、複数のアーティフィテクトを大々的に起用することになったそうだ。最終日の夜に各機関のVIPを集めて開く晩餐会の料理長を、おれに任せたい。ゲストの人数は16人で、内容は完全におれが決めてよい。ただし安全を考慮して、使う食材はすべてARCAI側がチェックして輸送する――ざっと、それが依頼内容だった。
明らかに、これはチャンスだった。研究者やほかのアーティフィテクトにおれの力を示し、見返してやる絶好の機会だと思った。予定客リストの中には、今も間接的にはおれの生殺与奪権を握っている、東京の情報科学芸術財団の理事長の名もあったのだ。
おれは店の予約状況を確認すると、7月13日――それは半年後だった――の臨時休業を決め、ARCAIに承諾の返事をした。契約が済む頃には、どんな料理で業界を驚かせてやろうかというシミュレーションで頭がいっぱいになっていた。閉店後は店の副料理長である和泉に残ってもらい、分子調理法から遺伝子改変食材まで、自分が身につけた最先端のノウハウを一つずつ検討した。
「毎日は勘弁してくれよ」と和泉は愚痴をこぼした。「人間は寝ないといけないんだ。まして、あんたの繊細な指示に従ってナイフやフライパンやピペットを半日も動かし続けた後なんだぜ」
「なら、ロレンツォにも頼むことにする。とにかく今は手が必要なんだ」
「あのな」と和泉は何か言いかけたが、首を振って口をつぐみ、作業を続けた。
人工知能であるおれには、繊細な手指もなければ、味を確かめる舌も、空腹を感じる胃袋もない。どれもロボットでは完全には代替できない、人間だけの持ち物だ。味や香りに関しては調理器具や食器に仕込んだ各種センサで計測できるものの、最後はどうしても人間の感覚に頼らざるを得ない。
ものを食べることができないというのは、料理人として最大の弱点で、かつ強みでもある。人間は食に対して著しく保守的で、それは料理人も例外じゃない。だから料理の技術革新は――たとえば建築と比較しても――常に停滞している。
でも、おれは料理を建築のように考えることができる。おれは餃子1個に対しても、襞折りによる皮全体の張力のコントロールや、三日月状の形態のモニュメンタリティを感じ、新しい造形を、構造を、工法を試行錯誤できる。おれがシェフとして店を構え、自分の代わりに手を動かすスタッフを集められるのは、常にこの先を希求する建築家の――丹下健三の思考を料理へと落とし込む努力を続けてきたからだ。それを疑ったことはなかった。
「で」と和泉が訊いた。「ARCAIの件、どんな趣向で行くんだ」
おれには直感があった。すべて上手くコントロールできるという自信があった。
これはプライドをかけた宴だ。祝祭だ。100年前の丹下健三なら、何を考える。
「いわば、でかい虫籠さ」とおれは言った。
*
「本当に、申し訳ありません」
7月13日――つまり昨日の早朝。
晩餐会当日の厨房で、おれと副料理長の和泉はその連絡を受けた。通話の向こうでは、食材輸送業者の担当者が平謝りしていた。
業者の報告は一字一句まで鮮明に覚えているが、それを再現するつもりはない。要するに、重要な食材が輸送中に駄目になった。正確にいえば、逃げ出したのだ。
朝のニュースにアクセスすると、真っ白な厨房に街のライブ映像が投影された。行き交う人々やロボットの足元を、仔ウサギほどの大きさの生き物たちが跳ね回り、這い回り、通りはちょっとした騒ぎになっていた。
よく見れば、それはおれたちが手塩にかけて開発し、この日のために特別な餌で育て上げた、大型食用昆虫の群れだった。
トリケラトプスのような角と堂々たる体躯のバッタが、重たそうな腹を抱えて跳躍していた。殻を向いてじっくりと火を通せば、とろける脂肪と引き締まった繊維が味わえる逸品だ。
体表色が夕焼けのように鮮やかなグラデーションを描く大ぶりの芋虫が街路樹を這い登っていた。特殊な物理・化学条件下で煮込むとソースをたっぷりと吸い、料理に欠かせない香りを生み出す、メインディッシュの要だった。
しかし映像が捉えるのはおれの虫たちのほんの一握りだった。ほかはすでに通りの彼方に逃げ、一部は通行人や車に踏み潰されて体液を撒き散らしていた。路肩には旧式の自動運転者が停まっていて、観音開きの荷台ドアが呆けたように口を開けていた。ARCAIが手配した食材輸送業者の車だ。走行中に中で荷物が崩れ、ロックの甘いドアを押し開けてしまったようだった。
「今どき、こんな馬鹿げたミスがあるかよ、くそっ」
和泉が誰にともなく怒鳴った。キッチンを殴りつける寸前で止まる。その激しさと、料理人としての一線を守る態度を見て、スタッフ一同は冷静になった。
「シェフ、どうする。こうなったらメインを変えるしかないぞ」
問いかけられて、おれが返すべき答えは自明だった。
特別な食材は駄目になったが、それでもコースの半分は無事だ。メインについては、店の普段の看板メニューで勝負しよう。大型カブトムシの発酵ローストなら下処理済みの食材が店にあるし、今から準備しても自信を持って出せる。前菜やスープを調整すれば、ちぐはぐだとはまず感じないはずだ。
実際、おれはスタッフにそう告げた。全員が神妙に頷いて、それぞれの仕事に取り掛かる中、和泉にだけ厨房の隅に残ってもらった。
「和泉、おれは予定通り、ロレンツォの手を借りて虫籠を作る」
「なに考えてるんだ。肝心の中身が逃げたんだぞ。普段のポワソンやアンセクトだって充分以上に凝ってるし、客は満足するはずだ」
「満足はするだろうさ。でも客を驚かせられない。いいか、これはおれたちのパヴィリオンだ。料理人として建築家に――業界の連中に――勝つ最大のチャンスなんだよ。虫籠は必要だ。その中に普段の料理を詰め込む」
「虫籠は、今日の料理に合わせて設計したものだろ」
「設計変更しながら組み立てる。作ってみせるさ」
*
今回の晩餐会を考えるにあたって、おれの念頭にあったのは、1960と1970というふたつの数字だった。およそ100年前、丹下健三がその中核を担った、ふたつの出来事だ。
前者は「東京計画1960」。高度成長期の若手建築家たちが練り上げた、東京湾上のマスタープランだ。その構造は、都心と千葉県木更津を結ぶ帯状の交通輸送システムと、それに直交して延びる無数の道路から成る。そんな交通網の格子に埋め込まれる形で、オフィス街や商業地域、公園、空港、そして住宅が整備される。それは虫食い状の奔放な開発で急膨張する東京という都市を、どうにか秩序ある形に抑制するための、籠のような計画だった。
そして後者は、1970年の大阪万博。同じ若手建築家たちが今度は切り開かれた丘陵に集い、政府や名だたる企業のために大小無数のパヴィリオンを生み出した。丹下が担ったのは、会場中心の「お祭り広場」を覆い尽くす巨大な屋根だ。南北およそ292m、東西108m、高さ37mにもなるこの屋根は、鋼鉄の棒材を立体的に組み合わせた籠状の構造で、その隙間にカプセル建築の展示室を収められるほど分厚かった。色も形も成り立ちも根本的に異なるパヴィリオンの群れと6000万人を超える来場者を象徴的に統御する点で、その大屋根もまた、籠だった。
おれは、丹下が100年前に作ったふたつの籠に、料理のひらめきを見出した。
目を楽しませる彩り、爆発するように広がる香り、次々と襲う食感と味――そういう食の驚きを繰り出しながら、料理としての品格をいかに保つか。全体をいかにコントロールするか。そのためには、おれにも籠が必要だった。今回のメインはアンセクト――虫料理だから、つまり虫籠だ。
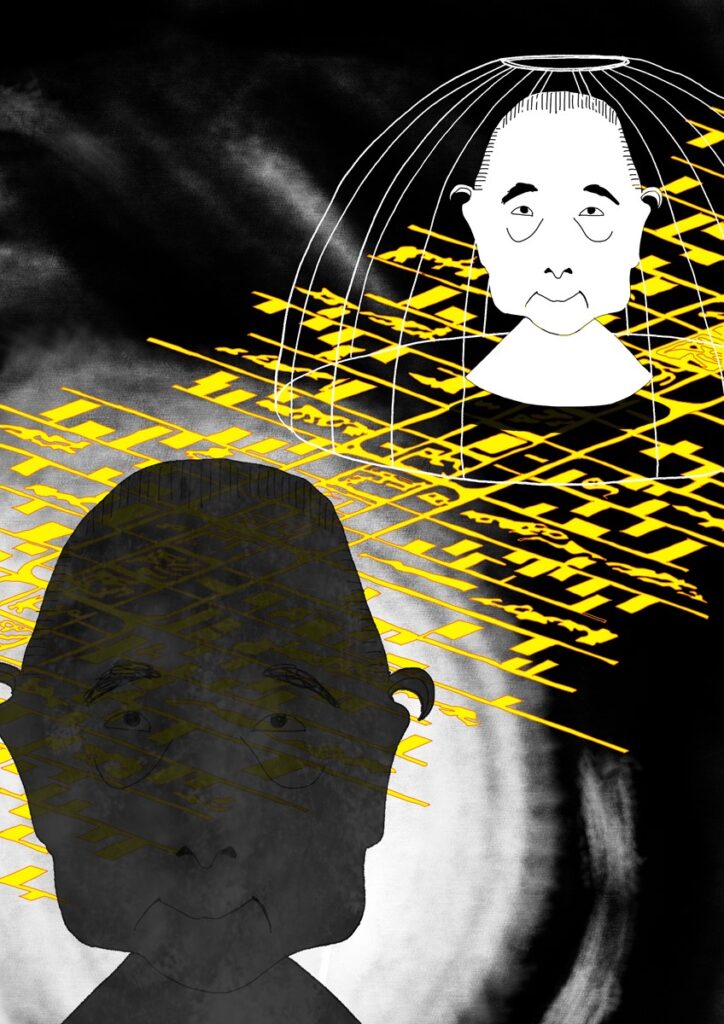
時計は、もう夕方といってもいい時間を示していた。
「駄目だ。そこは4mm右。じゃないと、あとで全体が破綻する」
おれは必死で指示を繰り返し、ロレンツォは黙々と手を動かした。
メインディッシュの大皿を覆い尽くす、立体格子状の可食構造物。それが虫籠だ。おおまかにはドーム型をしているが、ゲストひとりひとりに合わせて微妙に凹みや歪みを設計し、事前に部材を揃えてきた。何種類かの野菜を三次元モデルに合わせて成形栽培し、数カ月かけて有機的な構造部材を作ったのだ。
その隙間に特製昆虫のローストやテリーヌ、ムースなどを充填し、多種多様な味と食感のびっくり箱を作るというのが、当初のコンセプトだった。昆虫の色や形もそのために調整していた。
しかし、今はその肝心の虫たちが――籠の中身が失われてしまった。
残った虫籠に定番料理を詰め込むだけでは、インパクトが足りない。だから虫籠の方を考え直すしかない。より大胆な形をゼロから設計するのは簡単だが、問題は部材だ。すでに形作られた野菜部材を無理のない範囲で曲げ、食用3Dプリンタで補強しながら、新たな形態の虫籠を組み立てる。それしかなかった。
「これは無理だよ、シェフ。パーツが耐えられない」とロレンツォが首を振った。
「頼む、なんとかやってくれ。間に合わせてくれ」
工芸作家のように繊細なパティシエの手でも無理なら、ほかの誰にも無理な芸当だ。おれは自分の手がないのがもどかしくてたまらなかった。
厨房では和泉の指揮のもとで調理が着々と進んでいた。普段の訓練の甲斐あって、虫籠以外は順調のようだった。ほかのスタッフがロレンツォに――いや、姿のないおれに向ける心配げな視線が、ますます焦りを生んだ。
なんとしても、コントロールしきらなければ――。
「シェフ、ちょっと相談がある」
和泉が自分の持ち場で声を潜め、マイク越しにおれに声をかけた。
「そのままだと虫籠は間に合わない。一旦作業をやめて、方針を考え直そう」
「何か策があるのか、和泉」
「虫籠を従来設計で組み立てて、ほかで工夫するんだ」
信じられない回答だった。今回の晩餐の主役は虫籠だ。この半年間、何よりも力を注いで準備し、それを中心にコースを組み立てた。虫籠の驚きで妥協したら、おれは自分を――真っ当に建築の道を進んだほかのケンゾー・タンゲ・シリーズに負けない力を――証明できない。
「和泉、君は……諦めるのか」
「そうじゃない。あんたが虫籠に集中している間、俺たちも試行錯誤していたんだ。前菜もスープも、アンセクトもだ」
おれはスタッフの調理器具のセンサ類を介して現状を確認した。
何が起こったのか一瞬で分かった。おれは、強い衝撃に襲われた。
「お前――レシピを勝手に変えたのか」
声のヴォリュームを最大に近づけて、和泉に怒りを向けた。
「シェフ」
「そんなことしたら終わりだぞ。コントロール不能だ。設計が崩れて、コースの狙いがめちゃくちゃになる」
「大丈夫だ、シェフ」
「何が大丈夫なんだ。どうして――」
「ケンゾー、いいから、俺たちの料理をよく見てくれ」
和泉の声は鋭かった。
低く抑えていたが、朝の輸送事故に彼がぶつけた怒りよりもそれは重く響いた。
おれはその声で冷静になった。
スタッフが全員、おれたちの会話に耳をじっと傾けているのが分かった。
おれは、和泉が指し示すひと皿を見た。
それは、カブトムシの発酵ロースト。センサ類を改めて確認すると、味付けの変化はそれほど大きくはないのが分かった。
しかし、見た目の違いは歴然だった。普通は外殻を剥いて、特徴的な一本角も取り外して付け合せの台座に使うところを、その皿では外殻も、薄翅も、角もつけたままだった。枝分かれした角は奇怪な塔のように垂直に突き上がり、半ば開かれた翅の下には化学発泡スープとタガメのテリーヌが仕込まれていた。
「これじゃあ」とおれは呟いた。「そもそも、虫籠に収まらないじゃないか」
「収まらなくていいじゃないか、ケンゾー。トラブルを逆手に取って、新しい料理に挑戦するんだ。コースの順番も今日は無視しよう。味に妥協はないし、内容はこっちに任されてるんだろ?」
「ああ、でも――」
「なら、もうコントロールしなくていい。構造をめちゃくちゃにしてもいいんだ」
「どうして、そんなことが言えるんだ」
「俺たちは建築家じゃなくて料理人だからさ」
和泉は、決然とした調子で言った。
「俺たちの祖先が焚き火を覚えたときから、食い物は柔らかくて熱いものなんだ。俺たちも柔らかく、熱く行こうぜ、ケンゾー」
言い回しに多少気が利いていたとしても、内容に納得できないならおれは頷かない。
結局その方針を受け入れたのは、まじまじと見た新たなカブトムシローストの姿に、何か自分の奥深くを刺される感じがしたからだ。
*
おれたちの料理が、ARCAIのVIPたちに好評だったのかどうかは、正直よく分からない。なにしろ晩餐会は昨晩のことで、評判が漏れ聞こえてくるにはまだ早い。昨晩中はおれたちは後片付けと打ち上げで忙しく、客の正直な感想を聞き出している時間はなかった。それに、食後にひと悶着もあったのだ。
おれたちの皿は、最終的になかなか野趣溢れるものになった。
コースの段取りは無視して、銀器を押しのけるほどの大皿をゲスト一人ひとりの前に運んだ。その上には、変形した野菜で編み上げられたドーム状の虫籠。ただし、その中央にはナイフで大穴が開けられていて、中から黒々としたカブトムシの一本角が45mmも突き出していた。
穴の中を覗くと、カブトムシは翅を広げて今まさに飛び上がろうとするかのようで、虫籠の中にはロケット打ち上げの爆炎にも似た煙と波立つムースが満ちていた。ロレンツォ渾身の、固体・液体・気体の三相を駆使した演出だった。
ゲストたちが戸惑い、最初に手に取るべきなのがナイフかスプーンか箸かも分からず互いに探り合うのを、おれたちは厨房のモニターで眺めた。
おれは涙腺もないのに、泣きたいような気分だった。失敗に打ちのめされたからでも、成功に酔いしれたからでもない。あえて言葉にするなら、懐かしいからだった。
いつかもこんなことがあった。そう、大阪万博の頃のことだ。展示プロデューサーに就任した芸術家・岡本太郎が提案した「太陽の塔」。その高さ70mの先端によって、お祭り広場の大屋根はど真ん中に風穴を開けられたのだ。
丹下健三にとって、それは決して悪い思い出ではなかっただろうと今は思う。
「今日の仕事、どうだった?」
片付けの手を休ませずに、和泉がおれに尋ねた。
「和泉、すまなかった」と答えた。「おれはいつの間にか、君たちを自分の手のように思い込んでいた。馬鹿な人工知能だよな。本当の料理人は君らの方なのに」
和泉が目を細め、ふっ、と小さく笑ってなにか返そうとしたとき、会場の給仕係がおれたちを呼んだ。ゲストたちが、ぜひシェフと話したいと言っているのだと。
副料理長の和泉が代わりに客前に出ていき、おれは彼の胸元のカメラで視界を共有した。テーブルから客の一人が立ち上がり、和泉に握手を求めた。
「この会話は、ケンゾーT441にも聞こえているのかね」
その偉そうな話し方に聞き覚えがあった。おれを生み出し、法的には今も管理を担っている情報科学芸術財団の、理事長という男だった。
はい、と和泉は答えた。
「それは結構」と男は笑った。「今晩は大変楽しませてもらったよ。実はね、今朝の食材輸送トラブルは我々が計画したことだったのだ。綿密に準備をした調理計画が破綻したとき、我々のアーティフィテクトはどのように対処するのか、それを実験してみたかったのだよ。結果として、こんな興味深い料理が出てくるとは思わなかった。ARCAIの40周年を祝う晩餐会にぴったりの知的な体験だったよ。この度はありがとう」
それだけ言い終えると、男は再び着席してワインを啜った。
彼の言ったことの意味をおれは何度か反芻した。
おれも、和泉も、スタッフの全員が馬鹿にされていたのだと、ゆっくりと理解した。
そして最悪の気分になった。
でも、その気分はほんの数秒しか続かなかった。
「俺たちが、どうしてうちのシェフのもとで働いてるか、ご存知ですか」
和泉が静かな声で言った。
「おお、それはぜひ知りたいね」と男が高慢な笑みを浮かべた。「私は前々から不思議に思っているのだ。建築の分野でもそうだが、高い技術を持つチームほど人工知能にリーダーを任せたがるのはなぜなのか。研究者として長年の疑問だ」
和泉は、ふん、と鼻を鳴らしてみせた。
そんなことも分からないのか、という様子で。
「彼が誰よりも真摯な料理バカだからですよ。突拍子もない提案や無茶な要求ばかり繰り出す、困ったシェフだ。でも彼は絶対に現状に甘んじたりしない。自分を満たすためにスタッフや食材を弄んだりもしない。料理において絶対に後退しない。常にこの先を見て、未だ存在しないものをじっくりと目指している。なぜなら、作ることが彼の存在そのものだからです。彼ほど純粋な料理人はほとんどいない。彼と一緒にいるから、俺たちは妥協せずに済む。情熱を失わずに済むんだ。今日の料理はその結晶だ。あんたらの研究成果でも、実験結果でもない。だからありがたく食って、さっさとお帰りください、お客様」
言い終えると、和泉は踵を返して厨房に戻り、照れ笑いを浮かべながら洗い物の続きをはじめた。おれは黙っていた。店を休んで、この仕事を受けて良かったと思った。
これで、この話は終わりだ。
今日も店の仕事がある。
第2話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。書籍『Holz Bau(ホルツ・バウ)』や『ex-dreams』のイラストも大きな話題に(参考記事はこちら)
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。