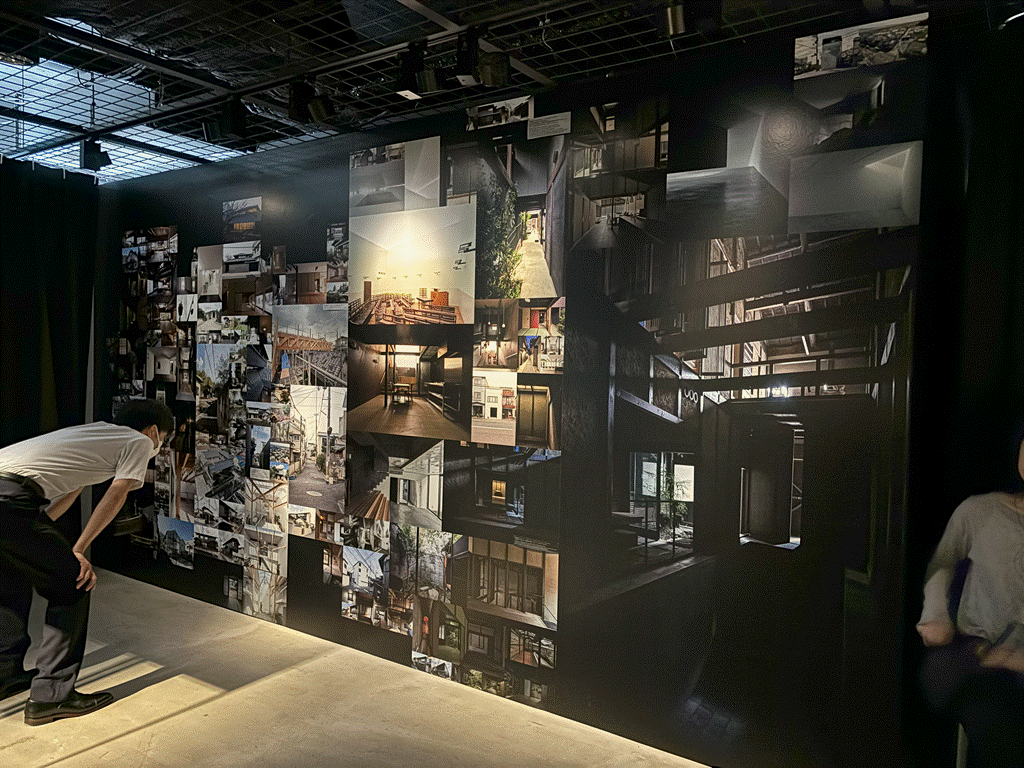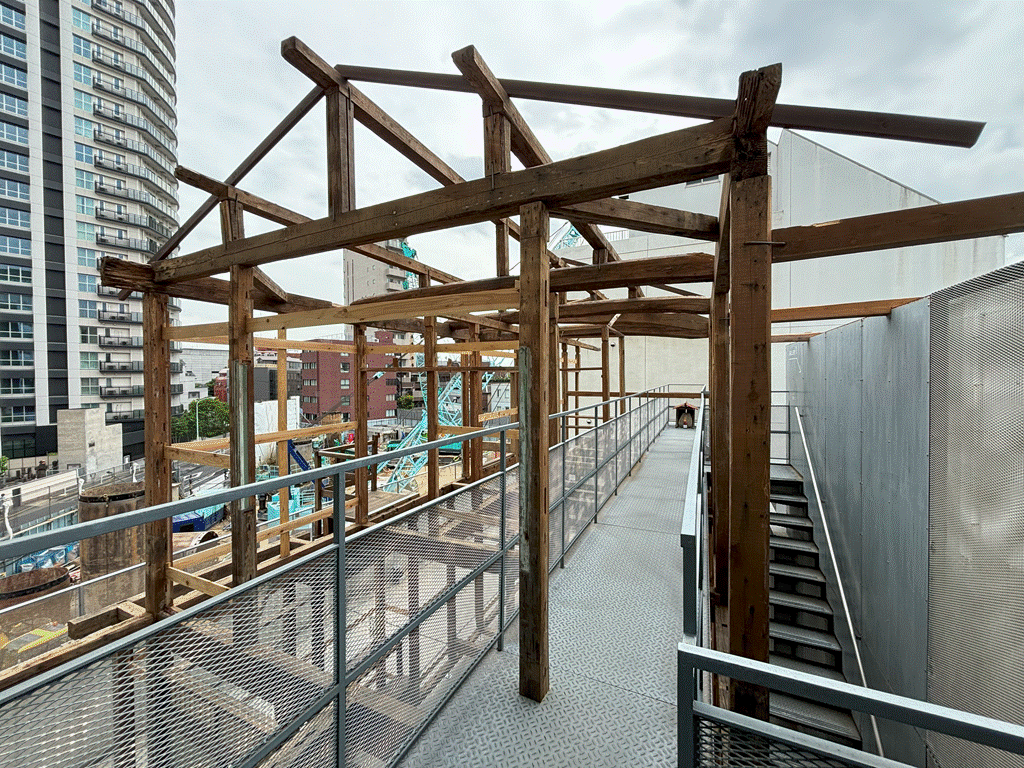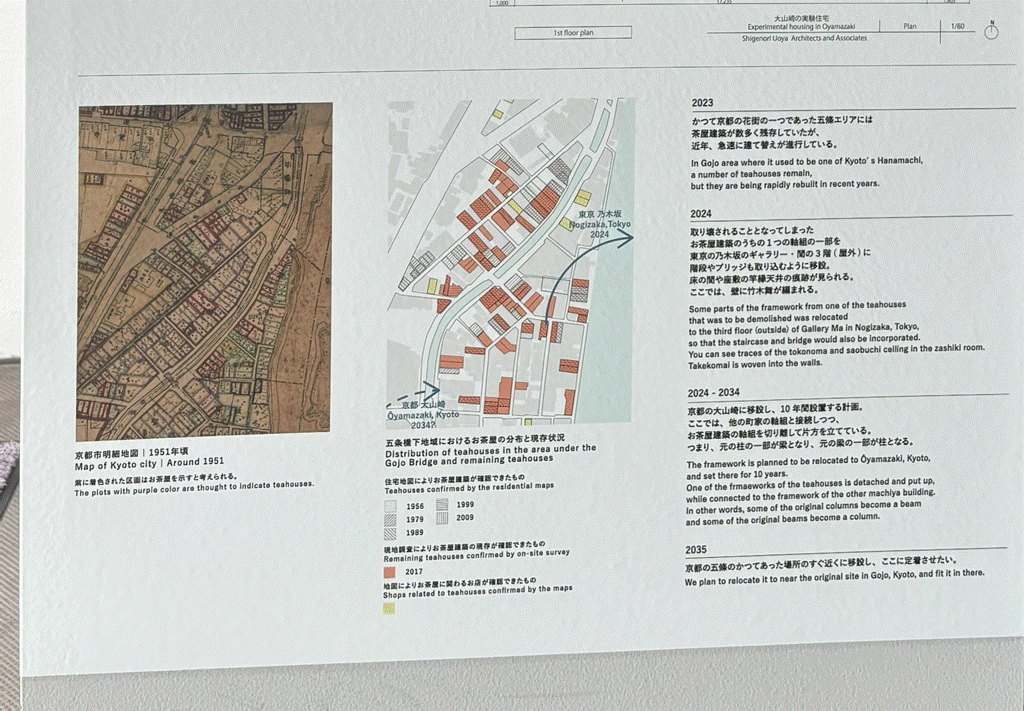東京・乃木坂のTOTOギャラリー・間で「魚谷繁礼(うおや・しげのり)展 都市を編む」が5月23日に始まった。会期は8月4日まで。同ギャラリー3階の中庭には、京都市内のお茶屋建築に使われていた木造軸組みの一部も展示している。魚谷氏は1977年生まれ。京都市内に魚谷繁礼建築研究所を構え、京町家の改修にとどまらず、国内各地や海外でも設計を手掛けている。2020年から京都工芸繊維大学の特任教授も務める。

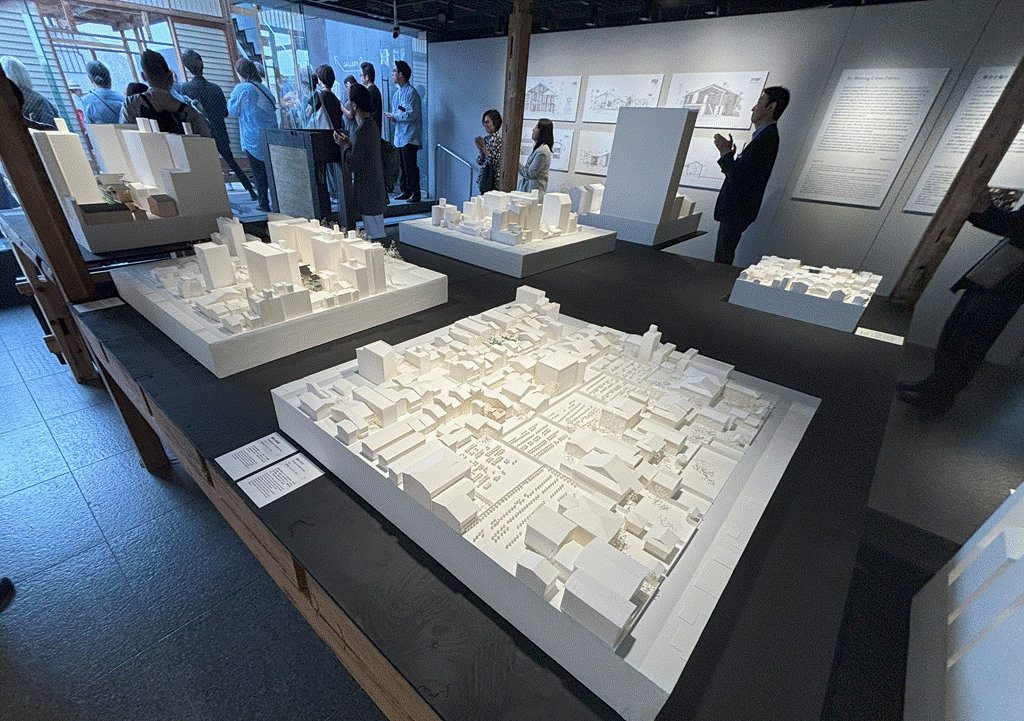
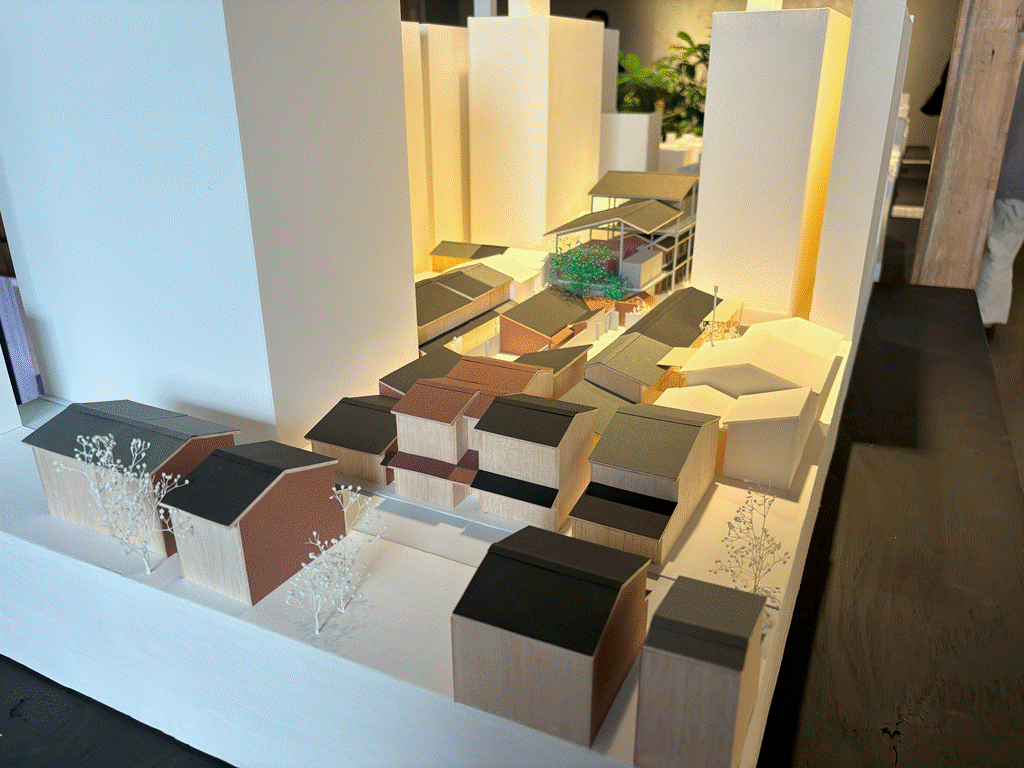
個人的には、建築雑誌の編集者だった7年ほど前から、魚谷氏の京都を中心とした町家改修の取り組みに注目している。しかし、直接、取材する機会には恵まれなかった。なかでも2019年完成の「コンテナ町家」はインパクトが大きかった。3軒長屋を覆うように鉄骨フレームを架けわたして床や屋根を設け、床の上にコンテナを設置したものだ。長屋と路地を生きた都市遺構として後世に継承することを目指した。
22年完成の「郭巨山会所(かっきょやまかいしょ)」は、コンテナ町家と比べてぱっと見穏やかな設計だが一味違う。この建物は京都祇園祭で巡行する山鉾の拠点となる会所の1つ。築100年超の手狭となった既存の会所を保存しながら増築したものだ。鉄骨の架構で補強するとともに母屋と土蔵の間に新たな架構を挿入。屋根で覆ってその下の2階には相の間などをつくり、3階を設けて板間を配置した。鉄骨と木造軸組みのスケールがうまくマッチしている。23年日本建築学会賞(作品)を受賞した。
京町家の改修実績が豊富な魚谷氏の手法はこれらにとどまらない。町家を保存しながら、短期間の“消費”に終わらず未来につなげる設計が持ち味だ。


京都大学の大学院時代に始め、20年以上続く京都のリサーチがよりどころとなっている。しかし、現況のリサーチをそのまま設計に反映させるわけではない。京都は、794年に平安京として都市が建造されて以来、グリッドパターンが都市の骨格になっている。それぞれの街区では、これまで約1200年の間に様々な改編が行われ、変化してきている。こうした流れの中で都市のコンテクスト(文脈)と現況を把握。過去から未来に続く時間軸の中において、どんな建築がいいかを見極めて提案する。
「設計者が京都の歴史をコンセプトとして利用する、あるいは設計の根拠に利用するのでは、何も言っていないと同じ。いろいろな歴史を重ねながら京都の街区がいまこういう状況なんだと立体的に体験できる都市の空間が重要だと最近は考えている。コンテナ町家のプロジェクトは、それを気づかせてくれた」。5月22日のプレスカンファレンスで、魚谷氏はそう説明した。コンテナ町家は、都市のコンテクストを楽しむという発想によって、町家の保存と建築の空間性を両立した事例だ。
3階には京都の旧市街に完成したプロジェクトを展示
魚谷氏の設計思想の一端を把握した上で、今回の展示を見てもらえば、その意図も理解しやすいだろう。順番に展示のポイントをお伝えする。
3階レセプションわきの大きな地図が、展示全体のインデックスだ。794年に建都された平安京、応仁の乱前後の市域、豊臣秀吉による御土居を重ねた上で、魚谷氏の事務所が担当したプロジェクトをプロットしている。京町家の改修は120件を超える。「都市の時間を重ねる」「都市構造を読み解き再編集する」という魚谷氏の視座から「都市を編む」という展示タイトルが付けられた。
その隣の壁面には、2000年ごろから今も続く京都のリサーチから一部を抜粋して展示した。リサーチの中心は旧市街(下京)の都市構造の現況を調べることだ。今回は旧市街の都市構造、旧市街の街区構造、旧市街の筆(地割)の変容をピックアップした。
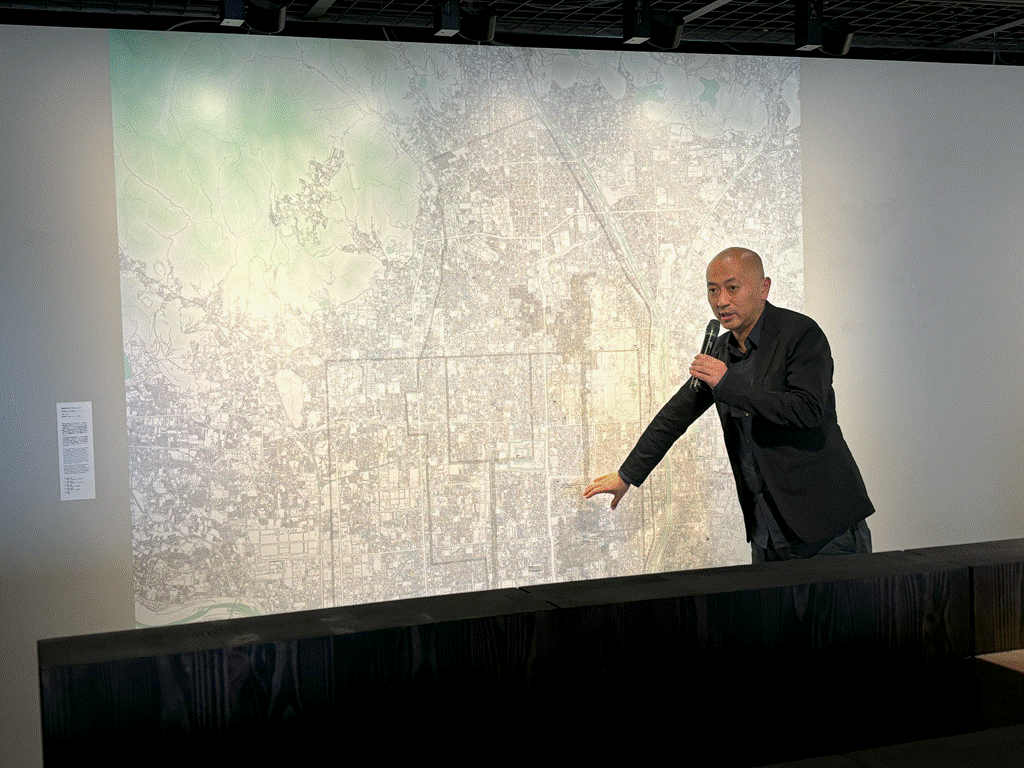
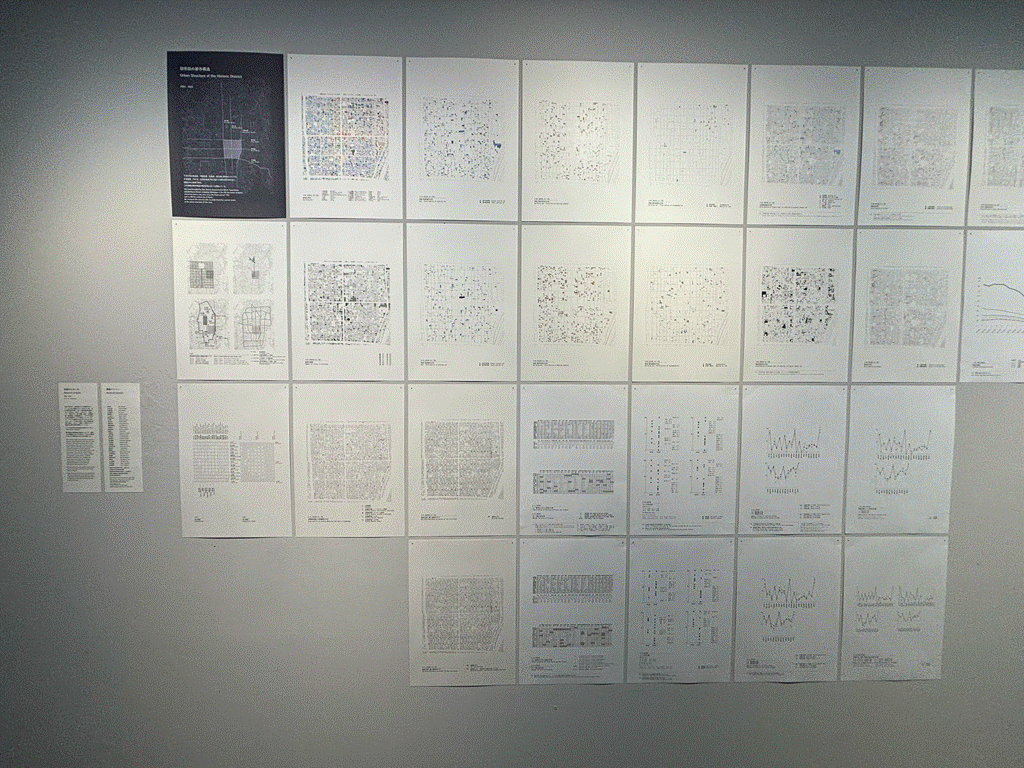
3階では旧市街に完成した6つのプロジェクトを紹介している。魚谷氏の事務所では、町家などの改修に当たってまずは街区の模型をつくって提案をまとめていく。「京都では、街区と建築の間に敷地があるのではなく、都市と街区、建築がシームレスにつながっていく。街区の中央が混とんとしているところに可能性を感じる」。こんな視点が魚谷氏のベースとなっている。
展示もそれと同調している。壁面に旧市街を対象に街区や空地、対象建物をプロットした1000分の1の地図を掲示、200分の1の街区模型、さらには周辺まで含めた50分の1の建物模型を配置。解像度を上げながら各プロジェクトを示した上で、横の画面で完成写真などを見せる。一部は構造のモックアップも展示している。わきの壁面では図面を見ることもできる。
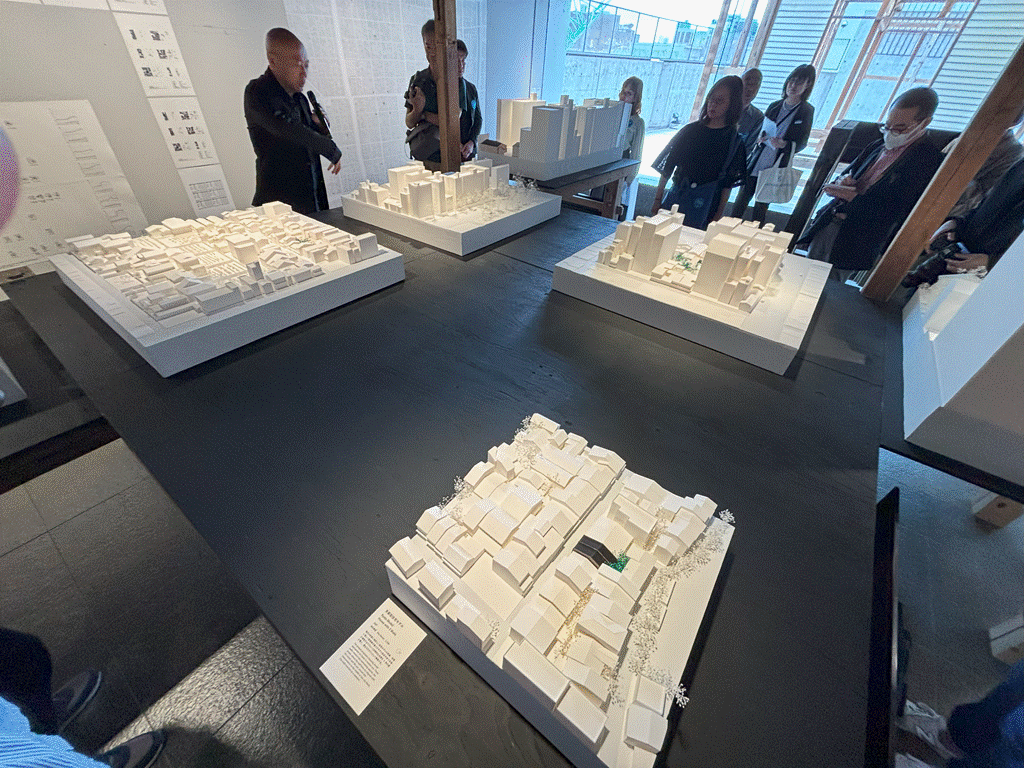
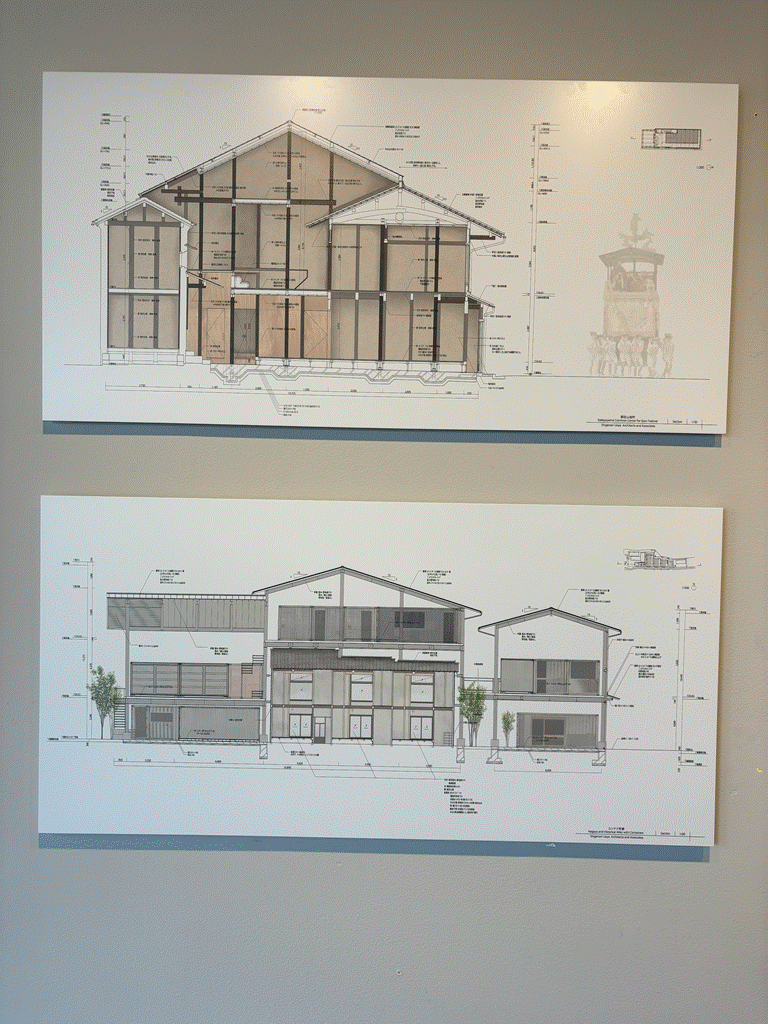
お茶屋建築の木造軸組みを移設しながら活用
3階の中庭の展示は、魚谷氏の新たな挑戦でもある。京都の花街に立つ築約100年のお茶屋建築が取り壊しになることから、伝統構法の木造軸組みの一部を一時的に移設して展示する。建築はその場に在り続けることで、都市との関係が築かれていくと考える魚谷氏にとっては異例のケースだ。展示終了後は、京都府大山崎町に移設し、10年間利用することになっている。その後は、元あったエリアで魚谷氏が長期にわたって取り組むプロジェクトに利用したいと考えている。
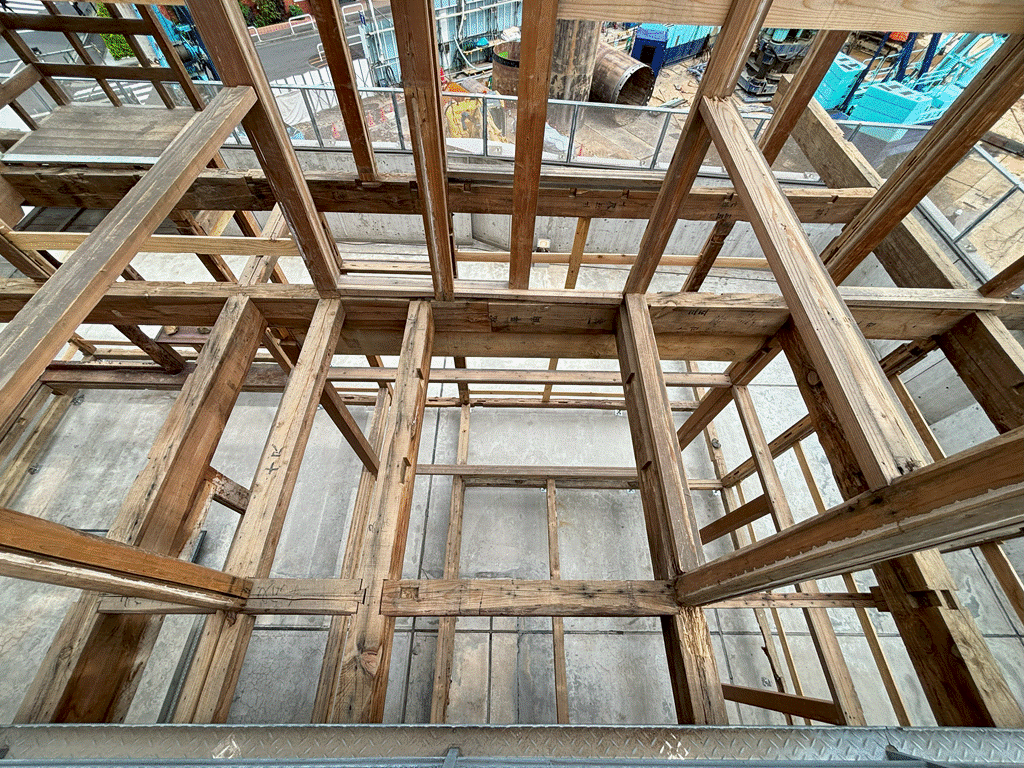

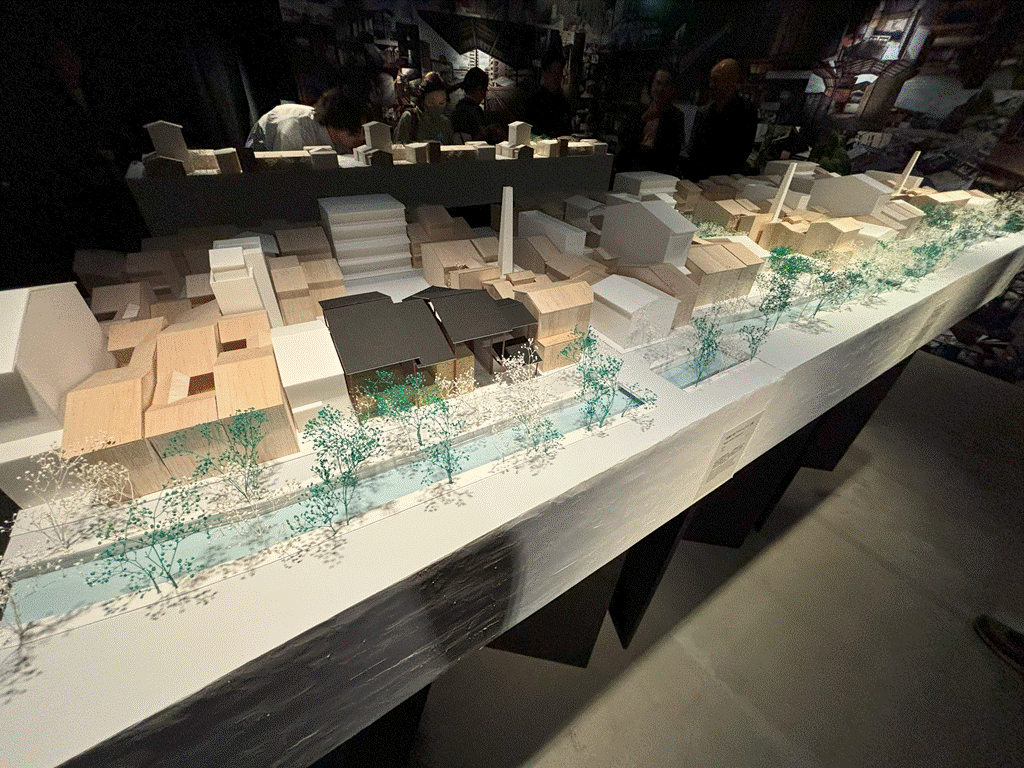
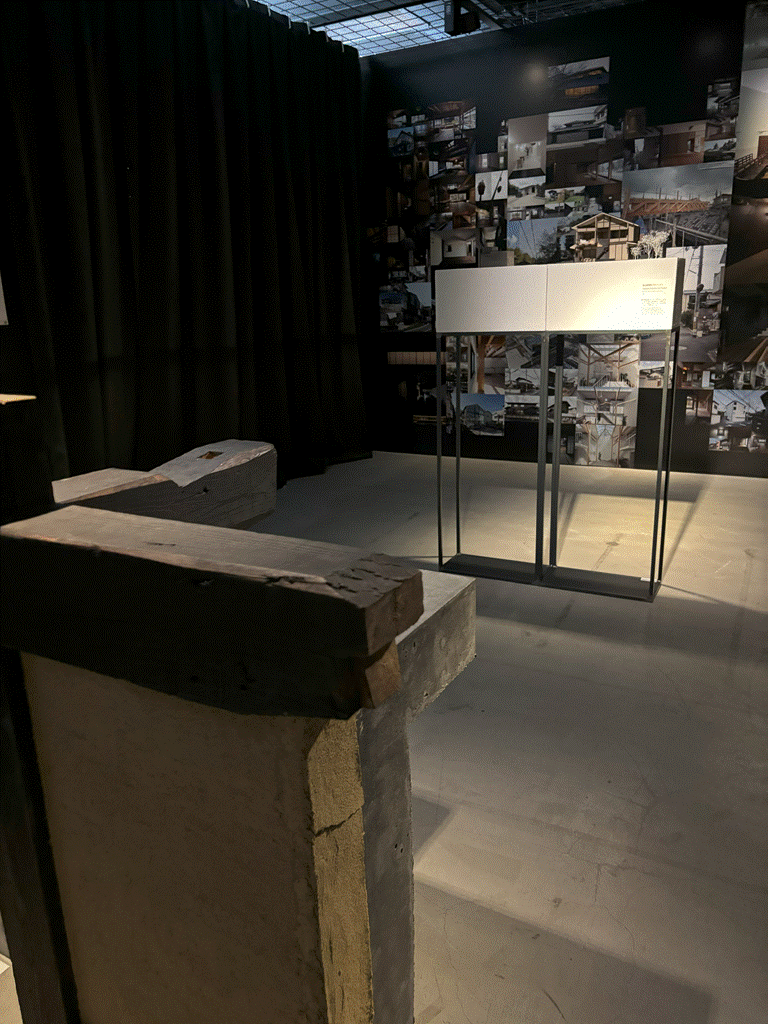
4階は、京都で進行中のプロジェクト4件を、模型中心に紹介するとともに、国内各地、海外で完成したプロジェクトの完成写真を展示する。完成写真は所在地の方角を頼りに壁面にずらりと並べている。4階展示室の入り口に置かれた案内板にはQRコードがある。壁面の写真のプロジェクト名を知りたい人は、QRコードから写真のレイアウトマップにアクセスが可能だ。
4階の内部は、模型も壁面の写真も照明の照度が低く抑えられている。これは魚谷氏の意図だ。全体がすぐ見えるのではなく、その場所に行って携帯の照明で照らすと新たな気づきがあるような発見的な場をつくりたいと考えた。
今回の展示は一見スマートで、短時間で見終わりそうな印象だ。しかし、縮尺が異なる地図、縮尺が異なる街区模型、さらに壁面の図面や完成写真は、それぞれ関連しながらちりばめられており、1回では把握できないほどの情報量がある。1度で展示を見終えようという人は、たっぷりと時間を取って出かけることをおススメする。ちなみに、自分のオフィスが会場に近いこともあって、筆者は2日で3回、会場に足を運んだ。(森清)