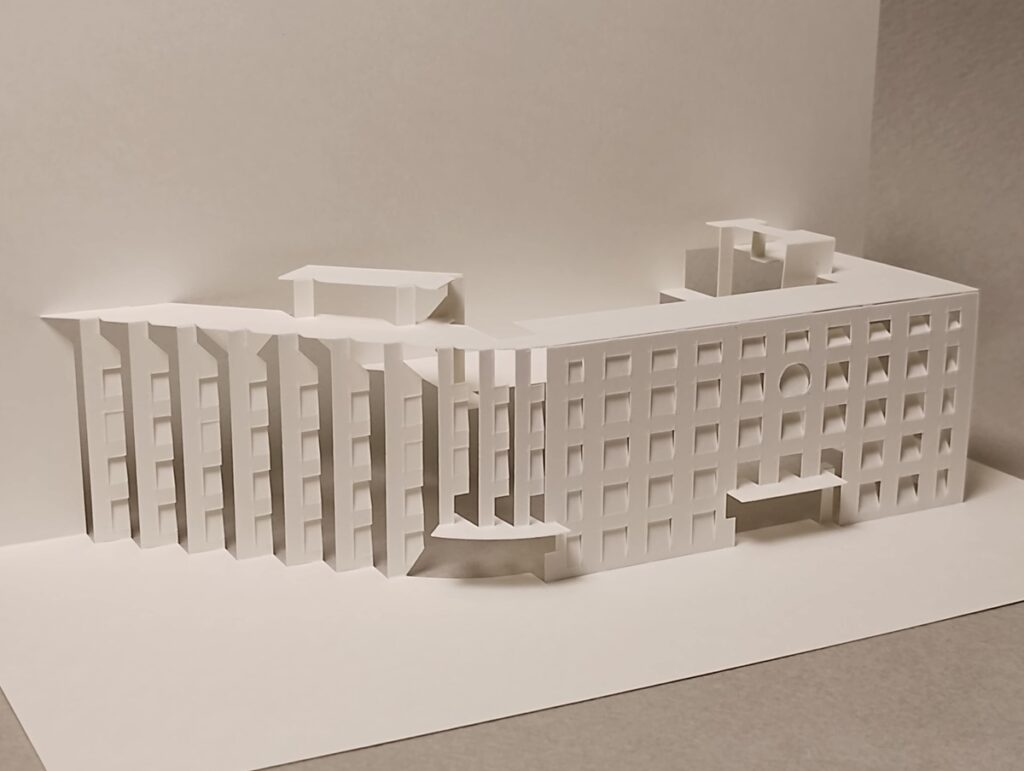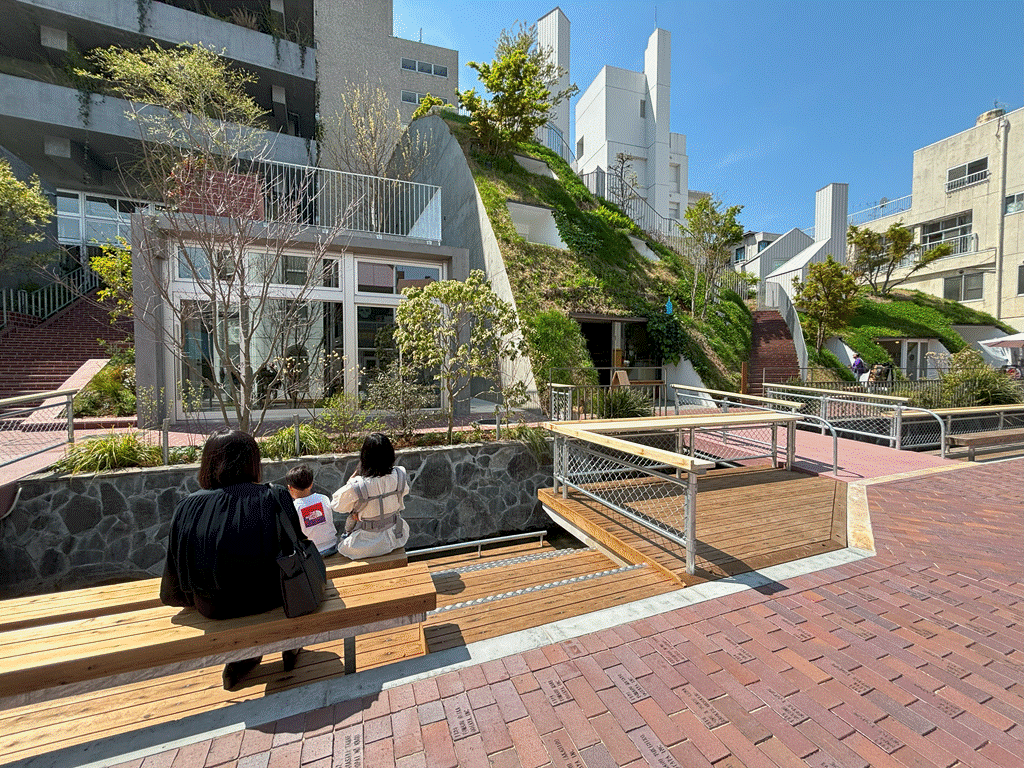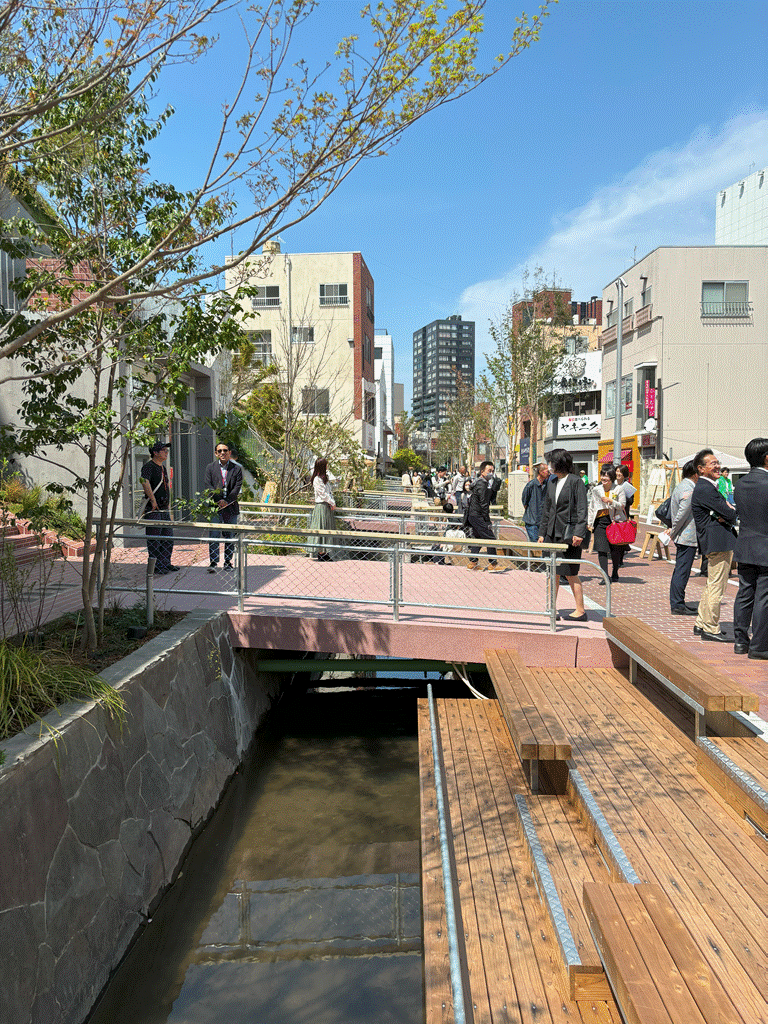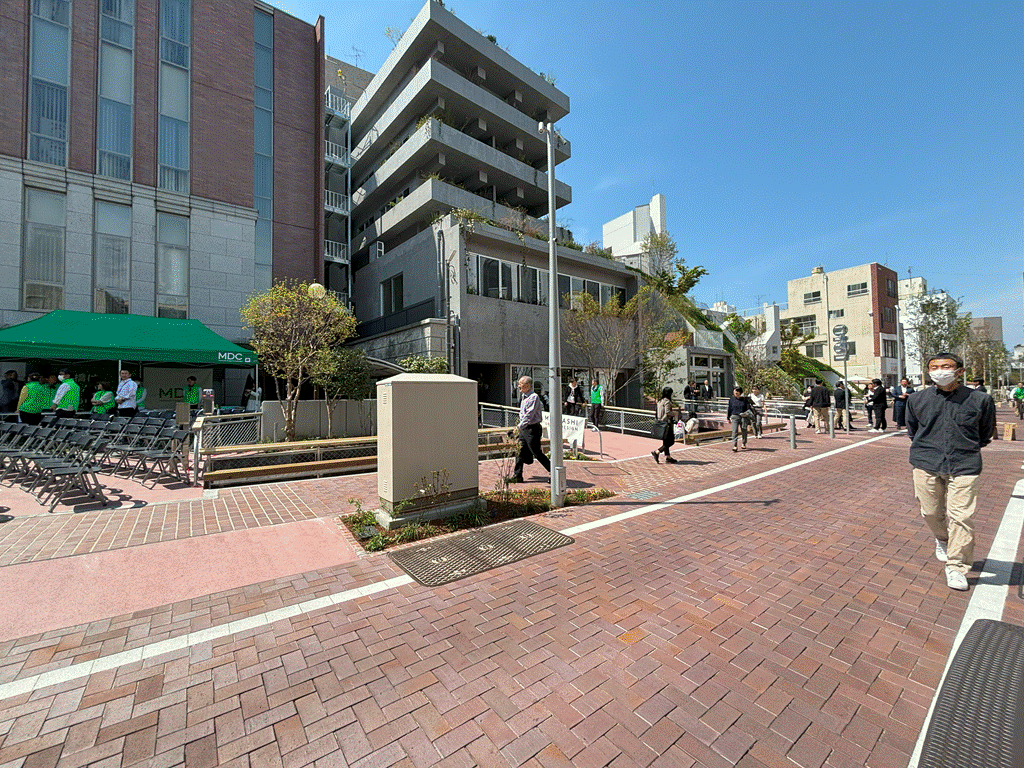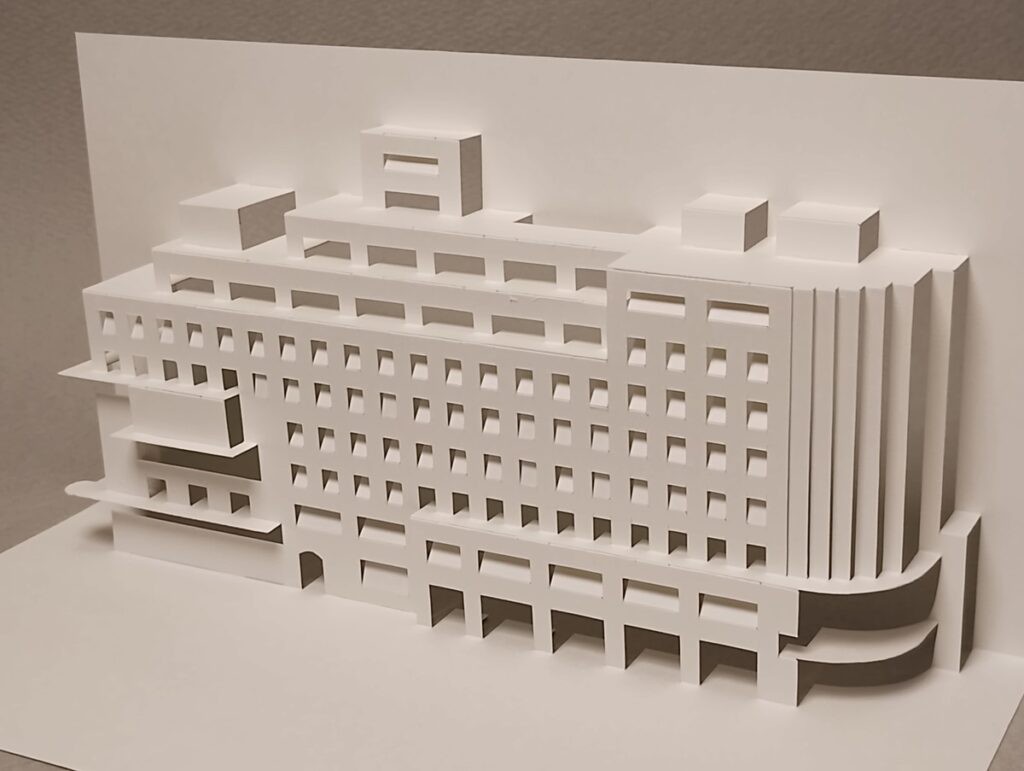いま、最も忙しい建築家の1人、永山祐子氏(それでも、いつ会っても元気!)。建築のプロジェクトだけでも忙しいはずなのに、インスタレーションにも取り組む。そして、いかにも建築家らしい問いを投げかける。だから、見に行かないわけにいかない。4月27日(土)から日比谷公園で始まる「Playground Becomes Dark Slowly」の作品の1つ、「はなのハンモック」だ。

「Playground Becomes Dark Slowly」は、「公園という都市の隙間の中で変化していく日の光を感じながら、自然への想像力を駆り立てること」をコンセプトに、アート体験を提供するイベント。キュレーターを山峰潤也氏が務め、大巻伸嗣氏、永山祐子氏、細井美裕氏ら3名のアーティストが出展する。東京都が主催し、エイベックス・クリエイター・エージェンシーが制作、運営、PR事務局を務める。4月26日にプレス内覧会が行われた。