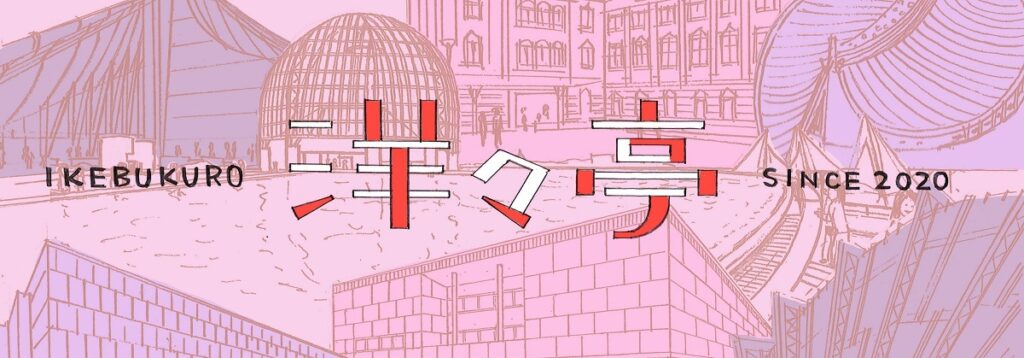東京建築祭が5月26日に閉幕して1週間たったのに、まだ放心状態から抜けられない。


倉方俊輔委員長ほどではないとはいえ、「もし失敗したら…」という重圧がかなりあった。人が集まらなくて空振りだと次につながらないし、人が来過ぎて大混乱になっても次はない。筆者は実行委員の中で唯一のメディア人なので、「なんて無茶なことを煽るのか」と叩かれることも覚悟していた。
結果は想定の5倍以上の人出。恐れていた「人が来過ぎて」という状況だったが、建物前に並ぶ人たちのモラルが高く、大きな混乱は起こらなかった。ボランティアスタッフの誘導も立派だった。1時間待ちもざらという状態だったのに、どの公開建築にも整然とした行列ができていた。並ぶ人のほとんどは建築のプロではなく、普通の人たち。そんな人たちの様子を見て、まるで外国人が日本人を褒めるように「建築好きの人たちはなんて素晴らしいんだ!」と驚く声を何度も耳にした。

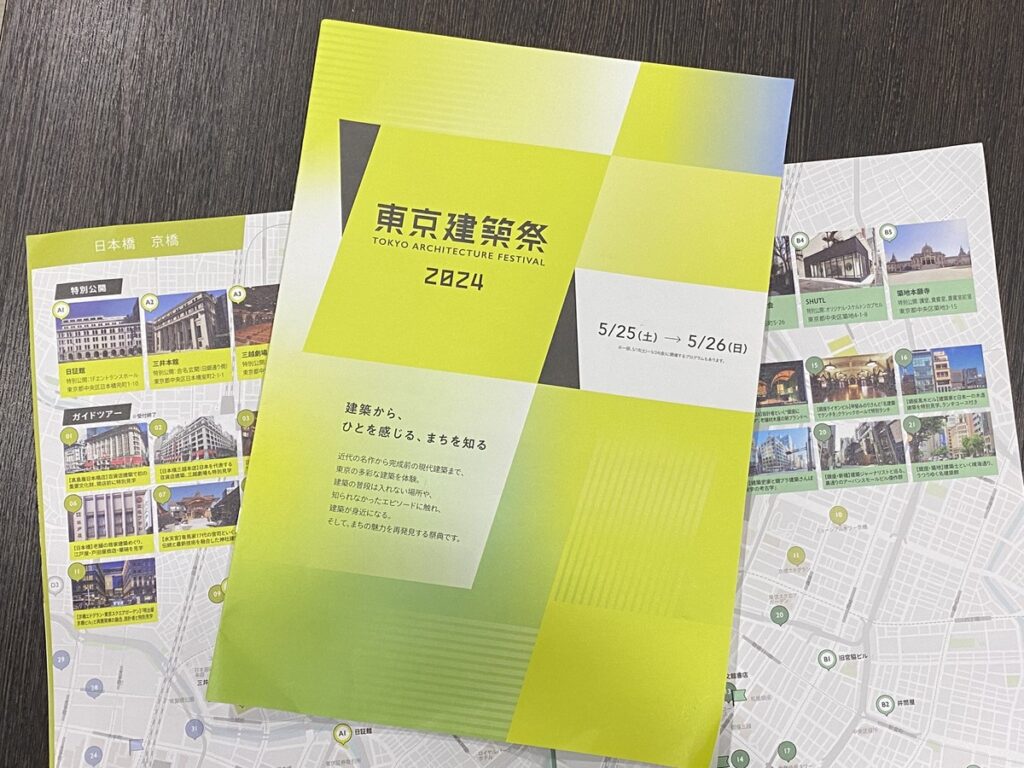
筆者は行列のマナーの良さもさることながら、その長さ=人数にやはり驚いた。事務局の発表によると、「会期中の参加者数はのべ約6万5000人」という(元の発表はこちら)。
あっ、これってまさに“建築文化の民主化元年”! と、その数字を見て思った。筆者の知る限り、建築好きの一般の人の存在が「数字」で明示されたのは日本の歴史上これが初めてだ。
現状の建築好きは1%くらい?
“建築文化の民主化”という言葉は、今年2月にこのコラムで使った言葉だ。
この記事の結びの部分で、「双方のイベント(「みんなの建築大賞」と「東京建築祭」)への関心が重なり、共振し合うことで、“建築文化の民主化”の大きな波動が生まれるのではないか」と書いた。波動は確実に生まれた。
そして、明治維新がそうであったように、民主化を加速するために、数字は大きな指標となる。
「会期中の参加者数はのべ約6万5000人」。これは延べ人数なので、仮に1人が平均2つの建築を見に行ったとすると、3万2500人。東京の人口は約1400万人なので、0.2%(500人に1人)が参加した計算になる。
なぜそんな計算をしているかというと、筆者は以前、あるメディアの取材を受けたとき、「将来の目標は?」と問われ、とっさに「日本の1割の人を建築好きにすることです!」と答えたことがあるからだ。そのときには、直感的に「現状では1%くらいだろう」と思って答えた。
今年、東京建築祭に参加した0.2%の人は、「少ない情報の中で行動を起こすほどのかなりの建築好き」だと思うので、「なんとなく好き」の人を含めると5倍くらいなのではないか。つまり、サイレント層込みでは1%。直感の予想とかなり近い。
倉方委員長の予測は10年後に6.5倍!?
だが、今年のデータは、まだ都民に情報が十分に回りきっていない状態でのもの。倉方委員長は自身のFacebookで、こんなふうに書いていた。
「イケフェス大阪の初年度が、同程度の公開件数で、参加者がのべ約10,000人。(現在は)その6.5倍なので、単純に計算すると、10年後には39万人!」
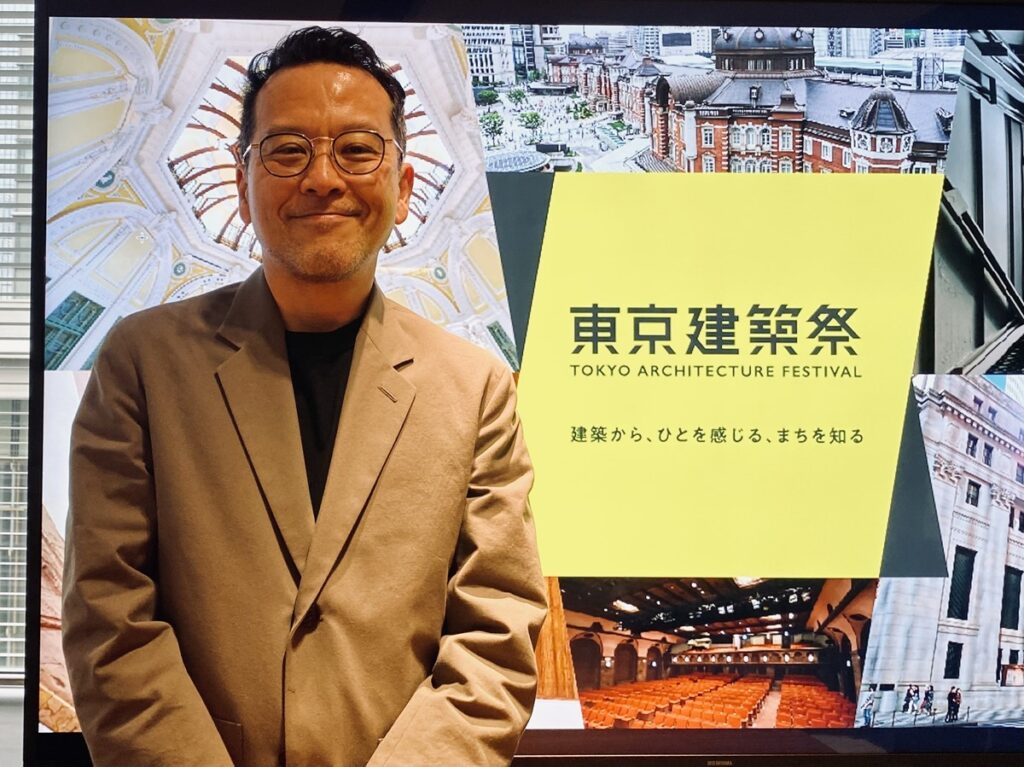
倉方委員長もやはり数字が気になる人のようである。
10年くらい実施すると都民にほぼ情報が行きわたると思うので、その頃までが拡大の勝負だろう。もし倉方予測の「10年後に延べ39万人」が実現されるとすると、上記の宮沢計算式(延べ参加者÷2×5)で算出すると、「サイレント層も含む建築好き」は東京の7%となる。
これは筆者が将来目標に掲げた「1割(10%)」にかなり近い。クビにされない限り、実行委員を10年がんばってみようかな…。
なお、“建築文化の民主化”のもう1つのエンジンである「みんなの建築大賞」は、先日、第2回の実施が公表された。投票はまだ先(2025年1月)だが、「何それ?」という方はこちら↓を見てみてほしい。(宮沢洋)