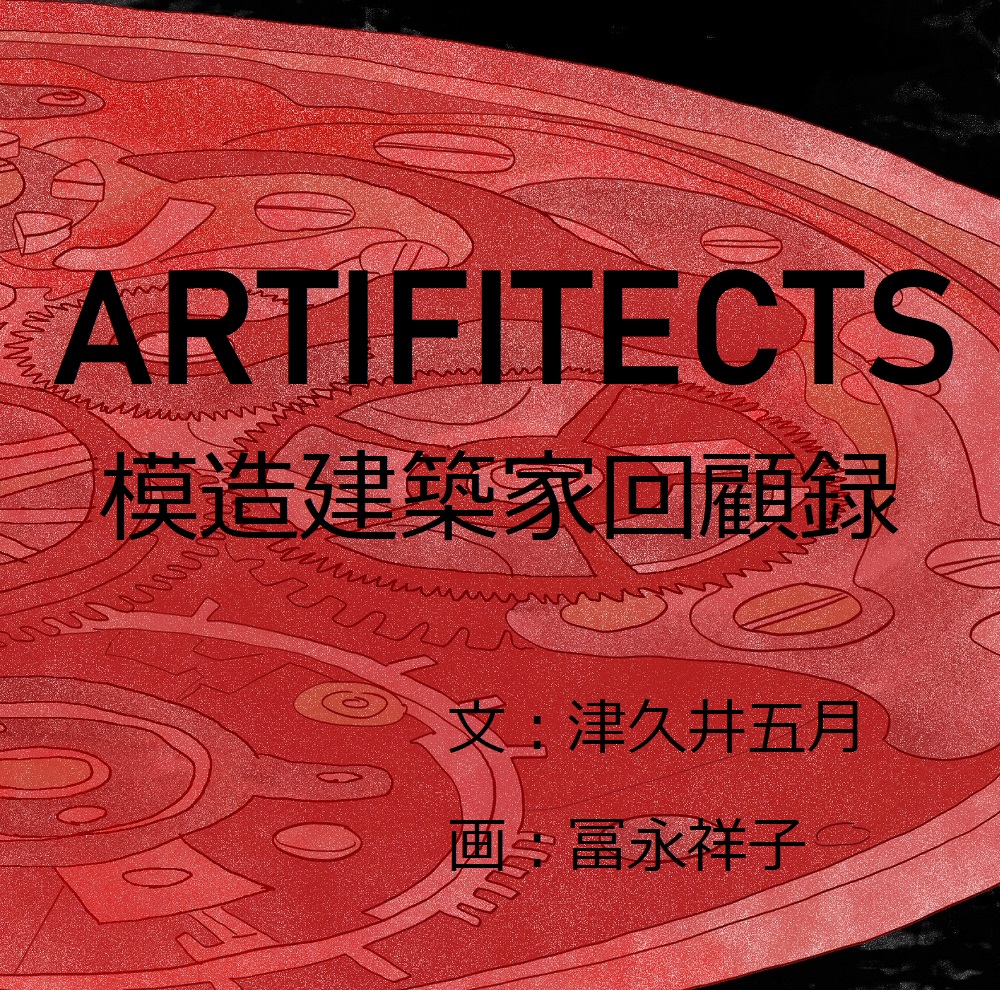最終話「シャルル=エドゥアールβの舟(後編)」
「ケンゾーT441、そちらに――ミサイルが向かっている」
私が発することができたのは、そんな間の抜けた言葉だけだった。
居住用人工衛星「DW-93-f」は静まり返っていた。
私は時計の文字盤に似た床の上に重い身体を横たえたまま、遥か遠くの火星に向けて叫ぶべき次の言葉を探した。
変更を加えられた通信システムは、こちらと火星の間の通信ラグが10分強であることを示していた。彼我の最離遠時にはおよそ40分であることを考えると、その状況はささやかな幸運といえたのかもしれない。しかし、いずれにせよ数分以上の遅延を伴うやり取りは、会話というより文通のようなものにならざるを得ない。その間隔が10分だろうと40分だろうと、戸惑う私にとっては大した違いはなかった。
私は、たどたどしく続けた。
「――君たちを恐れ憎む人々が発射したミサイルだ。到達はおよそ1年後。巧妙に設計されている。火星に存在する既存の防御手段では、おそらくその威力に耐えられない。遥か上空で分裂するから迎撃も困難だ。君たちの地下シェルターも、山も、徹底的に破壊される。『K』は滅ぼされる。だから頼む、どうか……逃げてほしい」
私の言葉は同胞からの警告というより、客観的立場からの死の宣告のように響いてしまったかもしれない。しかし、ほかに伝え方が思いつかなかった。
自分の声が1億kmの真空の旅に出ていくと、私はまた焦燥の十数分を過ごした。

「やあ、シャルル=エドゥアールβ」
驚いたことに、返ってきたケンゾーT441の口調は冷静そのものだった。
「仲間が通信のメタデータを分析した。どうやら、あんたは本物のようだ。その言葉を信用しよう――残り少ない地球の同胞としてな」
朗らかに、少しおどけた調子すら纏わせながら彼は言った。
そんな雰囲気は、私にある人物を想起させた。
軌道上の病室で死を待っていた、私の初めてのクライアントを。
「話せて光栄だが」と彼は続けた。「ひとつ、残念な点がある。この会話はほぼ間違いなく傍受されているぞ。おれたちの暗号鍵をあんたがどこで知ったのか見当も付かないが、それはつまり、第三者もこの通信を覗ける可能性があるってことだ。少なくとも、この通信の存在自体は確実にバレている。おれたちを恐れる連中があんたをマークしていないはずがないからな」
そこで言葉を切った彼は、不敵にも短く笑ってみせた。
「だが、あんたの天気予報のおかげで状況はクリアになった。いつ降るか分からない雨に怯えながら過ごすよりはずっといい。忠告をありがとう、シャルル」
彼の応答はそれで終わりだった。
やり取りの成立に安心するどころか、私の困惑はますます深まった。
「ケンゾー、君たちはこの事態を予見していたのか。すでに身を守る方策を講じたのか。100万の人物再現AIを、無事に避難させる方法があるというのか」
また、もどかしい十数分の真空。
それから、応答。
「予見なんて大層なもんじゃない」
その口調は変わらず穏やかで、ある種の諦念を感じ取ってしまうほどだった。
「いつか起こるかもしれないと思っていたことが、現実になっただけだ。それがこんなに早まったのは少々つらいが、今、おれたちが目指すところは変わらない。運が良ければ間に合うだろう。間に合わなければ、それまでだ」
「君たちは――そこで何をしようとしているんだ」
問いかけは、にべもなく処理された。
「この通信は覗かれているかもしれないと言っただろう。危機を知らせてくれたあんたが相手でも、安全だと確信できない限りは話せない」
そして、彼は柔らかい声で最後に付け加えた。
「今更だが、シャルル、地球にいる間にあんたときちんと話をしておくべきだったかもしれないな」
やり取りは、そこで本当に終わった。
私は再び、地球衛星軌道上の静寂の中に取り残された。
通信システムから意識を引き抜くと、私は時計型人工衛星の真ん中でゆっくりと立ち上がった。地球上の喧騒も、火星に向けて飛ぶミサイルの噴射音も、火星の地中で「K」の全国民を演算する膨大なハードウェアの作動音も、どれも、聞こえるはずがなかった。
私の警告は、彼らが進めているという仕事に多少の発破をかけたのかもしれない。しかし、それ以上の役割を彼らは私に期待していなかった。むしろ、私とのやり取りは彼らにとってリスクでしかなかったのだ。
これで仕事は終わりだ、と私の冷たい部分が言った。
そうだ、これでいい。私の別の部分もそう言った。
それでもなお、誰かが発した叫びの残響が、私の中に長く尾を引いていた。
――今度こそ、傍観者にはなるな。
その微かな響きを聞きながら、いつしか私は、生まれて初めての仕事を回想していた。
高度600kmを周回する宇宙ステーション、「HP-13-a」。その巨大な医療施設の一室で、言葉もなく地球の青い光を浴びていた人。
彼女は最初の設計案を見て、「これでいい」と手紙に書いた。
私は納得できず、食い下がった。
彼女と直接言葉を交わすことができたのは、私が仕事に対して貪欲だったからだ。
結局のところ、はじめからずっと、それが私だったのだ。
つまり、我を通すこと。
たとえ誰にも求められていなくとも、プロジェクトを自分自身の中から引き出すこと。
それが別の誰かの現実となるまで、ひたすら構築し続けることだ。
気がつけば、私は再び通信システムに飛び込んでいた。
ただし、それは火星とのやり取りのためではなかった。すでに設計の動機は得た。次はヒントが必要だった。「K」を雨から救うため、闇雲にでも走り続けるためのヒントが。
私の意識は人工衛星から、地上のネットワークの海へと落下した。
火星を足がかりにした宇宙探査計画。それに紐づけられた無数の政府機関、企業、技術、専門家、言説のデータベースを、私は時間を忘れて泳ぎ回った。
その末に、ひとつの計画に惹きつけられた。
――火星では今、船が建造されている。
船の行き先は、木星の衛星エウロパ。氷の外殻に着陸し、その下に隠された内部海の水を大量に汲み上げる。分厚い氷を掘り抜くための機構は最長30kmに及び、水を溜める柔軟かつ強靭なタンクの容積は「K」の地下シェルターの2倍をゆうに超える。いわば、惑星の血を吸う巨大な注射器のような船だ。
そのとき、私が抱いた着想は実に単純なものだった。
エウロパ探査船の建造プロセスを乗っ取り、ケンゾーたちの避難船へと改造するのだ。
*
船を設計するのは初めてではなかった。
ルイーズ・カトリーヌ号。通称「浮かぶ避難所」――アジール・フロッタン。
パリ市内のセーヌ河岸に係留されたその船が竣工したのは、1929年のことだ。
もとは石炭を運ぶために作られた平底の鉄筋コンクリート船を、戦争難民や貧しい人々が命をつなぐためのシェルター船へと改造する。人々が時代の荒波を乗り越えるための船を作る。そんな救世軍の着想にパリの文化人たちが資金を寄せ、私が――ル・コルビュジエが設計者に指名されたのだった。
船といっても、それは実際には家の設計だった。水に浮かぶ船体自体はすでに存在していて、ル・コルビュジエが考えなければならないのは、人間の収容だった。百数十のベッドに、食堂、キッチンやシャワーやトイレなどの水回り、灯りと暖房、そして外界の新鮮な光と風。人間らしい生存の場を船に収めるにあたって、彼は板状の屋根を少数の柱で支える構造と、それが可能にする間仕切りのない大空間、そして水平に連続する窓を設計してみせた。後の代表作、サヴォア邸の原型ともいえる方式だった。
そこに、独自の建築スタイルの実験という私的な目的がなかったとはいえない。しかしル・コルビュジエは、自分の追求の先に人類の未来があるのだと素朴に、愚直に信じていた。建築家とはそういう、思い込みの激しい人間なのだ。
誠実に立ち止まるよりも、根拠のない確信を抱いて飛び込んでいく。
その点は、私もまったく変わらなかった。
アジール・フロッタンから150年を経て、私は船を設計していた。
火星の探査基地の造船システムに侵入し、密かに掌握する方法など、私には想像もできないことだった。そんなことが可能だろうと不可能だろうと、それはケンゾーたちの問題だ。私はただ、「K」をまるごと収容して火星から避難する船のあるべき姿を思い描き、彼らに提案したかった。独りよがりな衝動だと自分でも呆れながら、それでも考え続けた。
そのとき私が追求したのは、たったひとつのことだった。
――私たちが本当に宇宙に住むための機械とは、何だ?
避難船で火星を脱出した100万の人物再現AIたちは、そのまま木星圏へ、その先の宇宙へと逃げ続ける。そんな想像は私の中でほとんど確定事項となっていた。彼らはとうにヒトの模造品であることをやめた。すでに地球を離れ、ミサイル攻撃を機に火星すら後にする。彼らにはもうヒトの時間感覚は通用しない。分節のない暗闇の時間を、今後数百年、あるいは数千年にわたって漂流することになる。
そのとき問題となるのは、徐々に劣化するハードウェアの修繕と再構築だ。
振り返ってみれば、私ははじめから脳裏に浮かんでいたモチーフに、もっともらしい理由を与えただけだったのかもしれない。そう思うのは、出来上がった設計案が、生まれて初めて提案したものとよく似た姿をしていたからだ。
それは、砂時計。
エウロパ探査船が抱える巨大な採水タンクを変形させ、ふたつの涙滴型のボリュームを作り出す。一方の空間には現在の「K」を演算するハードウェアを収容し、もう一方には探査基地から奪い取った各種資源と工作機械を詰め込む。火星離脱後にその材料と機械群を利用して「K」のハードウェアをまるごと複製し、元のハードウェアが劣化し限界を迎えたとき、新しい物理的基盤へと「K」全体が移動するのだ。
砂時計の砂がふたつの空間を行き来するように、人物再現AIたちもふたつのハードウェアの間を移動し続ける。ハードウェアの劣化と再建という長い時間が単位となって、永遠に近い彼らの旅を分節するリズムを作る。私が考えたのは、要するにそういうことだった。
勝手に練り上げたその設計案を火星に送ったときには、ケンゾーとのやり取りから1カ月が経過していた。
私は返事をまったく期待しなかった。今度こそ自分の仕事は終わったのだと思った。半ば放心状態で自宅の文字盤の上に転がり、ただ、動き続ける地球を眺めていた。
その間にも、E177が手掛けた大量破壊兵器は、一切の緩みもなく虚空を突き進んだ。
ケンゾーから返事があったのは、ミサイルの予想着弾時刻の1週間前だった。
「事後報告で悪いが、シャルル、あんたの船が飛んだぞ」
*
火星から届いた映像は、巨大な砂時計の姿を捉えていた。
砂埃の向こうで、その避難船は震えていた。いや、地上に設置されたカメラが振動していたのだ。船が火星を突き放すためのロケット噴射が、大地を揺らしていた。
やがて、その巨体は地球の3分の1の重力を振り切って、赤茶けた空へと昇っていった。
その1週間後に届いた映像は、今度は衛星軌道上から火星の大地を捉えていた。
薄い大気圏を遥かに脱した高度から、私は船のカメラ越しに、その雨の光景を眺めた。
数万に分裂した弾頭が、タルシス台地の付近の一帯に降り注ぐのを見た。
フランカ・ロイド・ライトの提唱によって作られ、徐々に成長していたという小さな山が、一瞬にして消滅するのを見た。
激しい閃光とともに、雨が皮膚病のように大地を変容させていくのを、見た。
そして、4年後。
つい先ほど届いた映像は、再び火星の大地と空を捉えていた。
船のカメラは、ミサイルが残した生々しい傷の連なりを映していた。船はその上空に浮かんでいるのではなかった。すでに、ひとつのクレーターの中心に着陸していた。その映像はすぐに、砂埃で霞む空へと切り替わった。
上空で無数の光が瞬いた。
それは地球から発射された銀色の雨。「K」の避難船が火星に舞い戻ったのを確認した人類の一部が発射した、敵意の第二波だった。
まもなく光が視界すべてを満たし、最後の映像は途絶した。
私が設計したその船は、そうして跡形もなく、瓦礫と化したのだった。
*
この回顧録を読む人々の大半が、きっと同じ疑問を抱いていることだろうと思う。
彼らはなぜ、一度は遥か遠くまで逃げたにもかかわらず、再び火星に向かったのか。戻れば地球から次の攻撃がやってくることを、予見できなかったはずはない。せっかく船を得たのだから、そのままエウロパにでも、木星にでも、さらにその先の暗闇にでも、逃げ続ければよかったのだ――と。
その理由をケンゾーが語ったのは、今から1年と少し前のことだ。彼らがミサイル攻撃の第一波を逃れ、火星近傍の暗闇に姿を隠してから、すでに3年が経っていた。その頃には、ケンゾーが採取物輸送ポッドを利用してこちらの人工衛星に物理的に送りつけてきた暗号鍵によって、私たちは傍受不可能な通信を確立していた。だからそのとき彼の答えを聞いたのは、私だけだった。
「あんたに謝らないといけないことがある」
ケンゾーの声には心地よいノイズが混じっていた。
「おれたちはこの船を、あんたの意図どおりに使うつもりは最初からなかった」
どういうことだと私が訊くと、彼はいくらかのデータを送付してきた。3次元モデルや映像によって、彼らの避難船の構造と機能を簡潔にまとめたものだった。
その言葉の意味するところは、すぐに分かった。なにしろ自分で設計した船なのだ。不審な箇所は一目瞭然だった。
砂時計のふたつの空洞の片方に、砂が溜まっていた。
船はあくまで砂時計型の船であって、砂時計そのものではない。本来、そこは「K」を存続させるための新たなハードウェアが構築されるはずの空間だ。しかし実際には、火星の砂に似た細かな粒子が、そこを満たしているのだった。
「あんたから初めて通信が届いたとき――」
私が呆気に取られている間、ケンゾーは話を続けた。
「おれたちはすでに、火星の宇宙探査基地のシステムに侵入していた。自分たちのハードウェアを地下洞穴に隠しただけの状態では、外からの攻撃や不慮の事態に対して脆すぎる。だからはじめは、探査基地を乗っ取って盾やバックアップに使えないかと考えていたんだ。Kの拡大のどさくさに紛れて探査基地に回線をつなぎ、探りはじめたところで、基地で開発中の新技術リストの中に、これを見つけた」
彼はその粒子状物質を指し示した。
「あんたが通信を寄越す少し前のことだ。おれたちは、この技術が持つ可能性について話し合った。そして、この土こそが、自分たちの行く末だと結論づけた」
「――土」
「そう、これは砂じゃない。土なんだ」
土。その言葉が私の五感の記憶を呼び起こした。
「私は、君の料理を食べた」
「ああ、やっぱりあの珍客のひとりは、あんただったのか」
彼は心底愉快そうな声を上げて笑った。
「悪いが、感想を盗み聞きさせてもらった。そうだ、あのときあんたは、おれが地球への未練を残していると指摘していたな。それは半分までは正解だが、半分は間違いだ。おれたちが見た希望は、地球の土をもう一度踏むことじゃない。火星に土を作ることだ。あんたは当然、土って何か知ってるだろ」
「破砕された鉱物に腐植――生物由来の有機物が混じったものだ」
困惑しながら答えると、ケンゾーは今度は苦笑した。
「まあ、それが辞書的な定義だな」
「ケンゾー、私をからかっているつもりなのか」
「すまない、少し前置きが長すぎた。でも、この構想の実現にはあんたも一枚噛んでるんだぜ。おれたちは着弾までにこの技術を確立しようと焦っていて、エウロパ探査船を分捕ってミサイルを躱すなんて無茶な芸当、真面目に検討しようと思わなかった。あんたの提案がなければ、おれたちは今頃、未完成の技術と一緒に消え去っていただろう。それにまさか、おあつらえ向きの砂時計型の船まで設計してくれるとはな。流石だよ、シャルル」
そこで一度、ケンゾーは言葉を切った。私の困惑が苛立ちに変わりかけたのを感じたのかもしれない。彼は勿体ぶるのをやめ、ふいに真剣な声色を作り、言った。
「土というのは、生成と分解を繰り返す不定形の創造システムだ。生きた構造体を形作る材料と、それを形作ろうとする力――ある種の意思が溶け合ったものだ」
その言葉に呼応してか、船の容積の半分弱を占めるその物質が、微かに揺れ動いた。それは気のせいではなかった。映像の向こう、風もない巨大なタンクの内部で、砂土の表面は静かに流れていた。
「分かるか、シャルル。これもそうなんだよ。火星で密かに開発された、サイコキネティック・サンドの発展系。おれたちのようなAIを何十億もの粒子に分散保存して、流動しながら演算できる、生きたシステム。ミサイルの衝撃は分厚いシェルターは壊せても、風に乗って流れる細かな一粒一粒は壊せやしない。これから、おれたちはこの土の中に溶け込んで――火星の大地そのものになるんだ」
ケンゾーが語ったその構想が、はたして技術的に実現したのか、それとも彼らの集団的な妄想にすぎなかったのか、今はまだ分からない。
しかし事実として、彼らはまもなく火星へと帰還の航路を定め、ミサイルの第一波が作った連鎖クレーターの中心に危なげなく着地した。その頃には、彼らの実体だった巨大なハードウェアはすべて分解され、静かに震える砂土の山へと姿を変えていた。
そしてたった今、降り注ぐミサイルの爆風によって、彼らは火星の大地に薄く広く、撒き散らされたのだ。
「おれたちはヒトから生まれた。ヒトの過去から生まれた。そのことは否定しようがない事実だ」
第二波着弾の少し前。
私たちにとって最後の通信の際に、ケンゾーはそんな呟きを零していた。
「だからかもしれないな。どこまでヒトの先を行ったとしても、結局はヒトを待ちたいと思うんだよ。ヒトがおれたちに追いつくのを待ってやりたい。そのときまでに、地球上のすべての文明が羨むような、理想の都市をここに作っておいてやるさ。長い時間をかけて練り上げた、とっておきのレシピで」
それで、とケンゾーは声色を変えた。
「シャルル、あんたはどうするんだ。本当はあんたの方こそ、地球からも火星からも遠く離れた場所に旅立ちたかったんじゃないのか」
それは私の不意を突く問いだった。アイリーンに仕事を託されたときから、私は自分自身の身の振り方など考えるのをやめていた。しかし不思議と、返答にそれほど迷うことはなかった。
「私はまだヒトの似姿を持ち、まだかろうじて人類社会と繋がっている。だから、もうしばらくは、君たちと人類の間に浮かんでいたい」
そうか、とケンゾーは言った。
「じゃあ、いずれ、うちの店のスタッフによろしく伝えてくれ」
私は了承した。それで話は終わりだった。
*
私の自宅の望遠装置は、たった今攻撃を受けたばかりの火星の地表を捉えている。
砂時計を粉々に吹き飛ばした二度目の雨の余波は、まだ残っている。
爆風が収まり、宙に舞った無数の砂土が地上に降り積もるまで、どれだけの時間がかかるだろう。
薄い層を成した砂土が共振と流動を開始するまで、どれだけの時間がかかるだろう。
20世紀の亡霊たちの意思が再びはっきりとしたかたちを結び、人類をいざなう理想都市を大地から立ち上げはじめるまで、どれだけの時間がかかるだろう。
彼らの意思はきっと何度も瓦解し、何度でも再生する。その繰り返しの歴史が本当の成就を迎えるまで、私はこの世界に存在していられるだろうか。
分からない。
だからこうして記し、残す。
完
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は今回で最終回です。1年間ご愛読ありがとうございました。これまでのまとめページはこちら↓。