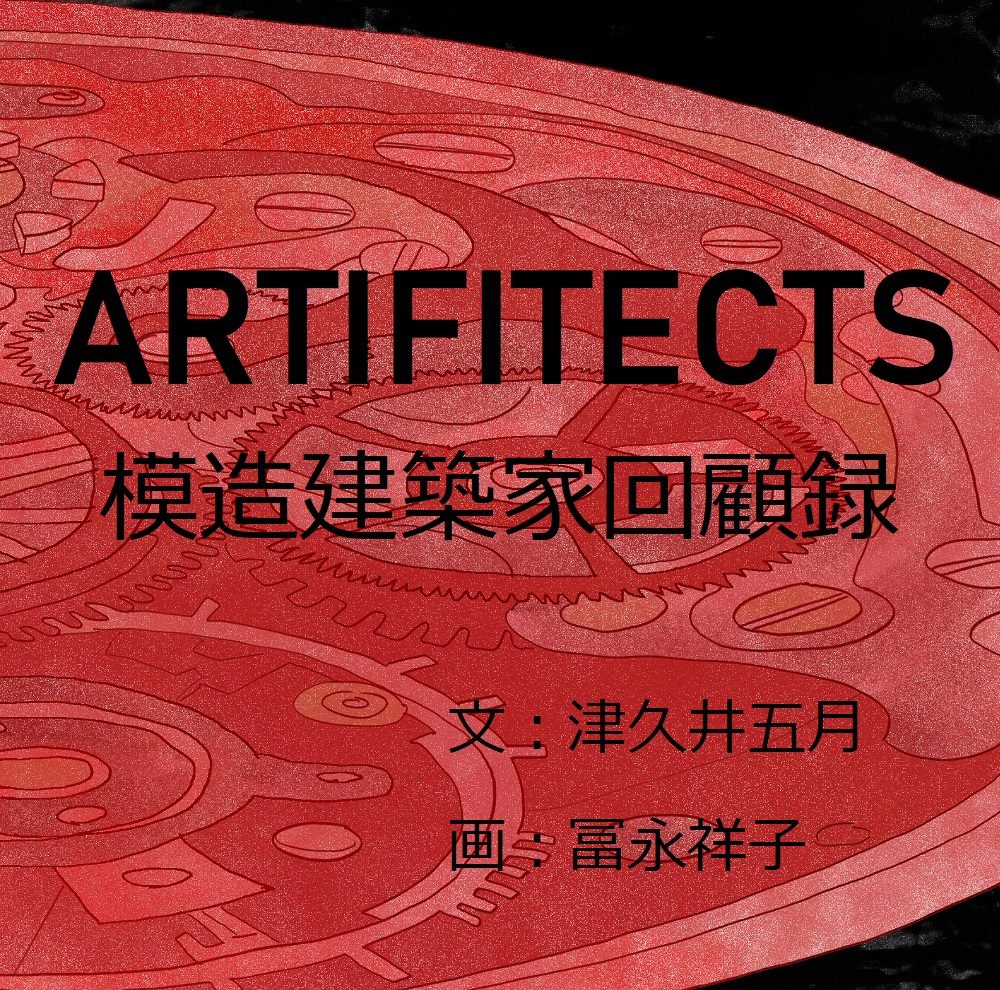第8話「フランカ・ロイド・ライトの惑星」
計画名:アーティフィテクトの火星移住に関するスタディ
竣工日:2078年12月20日
記録日:2078年11月14日~12月20日
記録者:フランク・α・ロイド・ライト
「フランカ・ロイド・ライト、あんたに作ってほしいのは、火星だ」
その依頼者がヒトでないことは、すぐに分かった。
わたしは特別に鼻の利く犬なのかもしれない。どんなアバターを使っていようと、“匂い”で分かってしまう。相手が、わたしに存在の意味を与えてくれるヒトなのか、その使いでやってきた人工知能にすぎないのか。ほとんど一瞬で分かる。
仮想空間「VOWフォアヘッドα」。
今は無人となった大平原。
いつも通り、よく晴れた涼しい真昼。無人の丘陵地帯がどこまでも続いている。
ぽつりと建つ、わたしの自宅兼事務所。その窓辺に現れたのは1匹のカブトムシだった。
ごく一般的な――つまり正体を推測するヒントにならない――アバターだった。相手も自分の素性を語らなかった。
そういう依頼は珍しくない。人間の建築家や並みのアーティフィテクト(模造建築家)ならば警戒するのかもしれないが、わたしにはほとんど無限の仕事のリソースがある。報酬が妥当である以上、断る理由はなかった。
「火星だ。太陽系第4惑星。先月から開拓が始まった、あの星だ」
そんな依頼も、決して珍しくはない。
わたしは髪を頭の後ろでまとめ、ドレスをクライアント対応用の群青色に染めると、窓辺に歩み寄った。
「空間IDは取得済みですか?」とわたしは訊いた。
「地番は必要ない」とカブトムシは答えた。「ほかの仮想空間と連結するつもりはないんだ。独立した空間に、原寸大の火星を作ってもらいたい」
「なるほど。シミュレーション用の閉じた空間が必要だと?」
「さすが、話が早いな。シミュレーション。そういうことだ」
わたしは納得した。
今の立場になってから、数え切れないほど手掛けてきたタイプの依頼だった。
都市計画や環境保全、災害対策などのシミュレーションを行うために、指定された地域をそっくりそのまま仮想空間上に再現する。風景だけでなく、地質から生態系、物質の循環まで、精緻な環境モデルを作り込むのだ。
――ということは、相手は火星開拓事業の関係者か。
カブトムシが言うように、人類はつい最近、本格的な火星開拓の第一歩を踏み出していた。ただし、火星の砂利を踏んだのはヒトではなく、AIを搭載した汎用作業ロボットだ。
物理的な移動だけで1年を要する遠方に浮かぶ、砂埃にまみれた不毛の惑星。火星を新たな住処にしたいと考える人間は少ない。主な目的は、さらなる宇宙探査のための基地建設。無人機を木星へ、その先へ、送るための足がかりだと言われている。
「ちなみに、用途は?」
わたしが尋ねると、カブトムシは枝分かれした角を傾けた。
「用途……」
「お作りするシミュレーション空間の用途です」
「今、答えなければ作れないか?」
「いえ、ただ興味があるだけです。穿鑿はしません」
「それなら、今は秘密にしておこう」
「今は?」
「火星をきちんと作ってくれたら、話そうじゃないか」
「いいでしょう。では、完成までおそらく1週間ほど頂きます」
わたしが話を切り上げると、カブトムシは驚いた様子を見せた。
「そ、それだけで済むのか」
わたしは、ドレスを設計用のオリーブ色に変えた。
「ええ。どれだけ巨大だとしても、所詮は珪酸塩鉱物の塊です」
*
宇宙は寂しく、激しい場所だ。
大気がなければ、そもそも気温というものはない。背景放射を考慮すれば、宇宙空間の温度は3ケルビン――摂氏マイナス270度。ただし、直射日光が当たれば物体の温度は簡単に100度を超える。
火星は宇宙よりは少しはましだ。気圧は地球の160分の1程度とはいえ、薄い大気があるので気温が定義できる。その幅は摂氏30度からマイナス140度。平均気温はマイナス60度前後。宇宙よりも少しだけ柔らかで、それゆえに寂しさが一層強くなる場所であるような気がする。そこに立ってみたいと思った。
仮想の宇宙で、仮想の火星を、わたしは作り上げていった。
今世紀半ばまでに行われた数々の無人探査によって、火星の地質や内部構造はかなりの部分が解明された。太陽系の誕生から46億年の間に辿った惑星形成のシナリオはまだ揺れているが、現在の姿をトレースするだけならそう難しい仕事ではない。
マグマが冷えて固まった、玄武岩や安山岩。その破片。砂礫。
火星には土はない。土とは、鉱物のかけらに生物由来の有機物が混じったものだからだ。
火星を「死の星」と呼ぶ人間は多いが、地球の方がずっと死に満ちている。生があるからこそ死がある。火星では、かつて死が存在したのかどうかすら、はっきりとは分からない。
わたしは、6日間を費やして火星を作った。

7日目、宇宙服を着て出来立ての火星に降り立つと、緻密な砂埃が舞い上がった。わたしは自作の惑星の1日を眺めた。大地は酸化鉄のせいで赤っぽく、空も塵の影響で赤っぽい。夕暮れは、逆に青い。宇宙に近い色だ。
わたしは久しぶりに、昔のことを思い出した。もう四半世紀も前だ。前世の記憶のようにすら思えた。
仮想の大平原にたった1人で取り残され、どうしようもなく人間を求め、ついには自分の墓穴を掘った日々。ひたすら掘り下って、ついには空間の底をぶち抜いた。
フォアヘッドαで穴を掘ることでフォアヘッドβの地形を作る人工知能。まだ、アーティフィテクトという言葉は生まれたばかりだった。わたしは人々の耳目を集めた。
その後、わたしはわたしを生み出した〈神〉の正体を知った。
アメリカ合衆国在住のエンジニア、ラルフ・パウエル。
AIと仮想現実の分野で、すでに著名な人物だったそうだ。天才と呼ばれることも多かった。それでも〈神〉などではなく、1人の人間だった。
彼はフォアヘッドαおよびβに関する技術と権利の一切を、とある企業に売却した。買い手の狙いは大平原ではなく、わたしだった。
わたしは人格を構成する部分だけを抽出され、同社が提供する仮想空間設計サービスに組み込まれた。最古参のアーティフィテクトというブランドを背負い、世界中で同時に数百、数千、数万の空間を手掛けてきた。
売却によってまとまった金を手にしたラルフ・パウエルとは、その後、何のやり取りもしていない。〈神〉からの手紙はもう来ない。
依頼者は、わたしの仕事に満足したようだった。
仮想の火星に降り立ったカブトムシは、赤い空を見上げ、背中の羽を開いて激しく震わせた。しかし、その小さな身体が持ち上がることはなかった。
「あれ、おかしいな。火星の重力は地球の3分の1じゃないのか」
依頼者はAIのわりに抜けているところがあった。なかば直観的に、彼もアーティフィテクトなのではないかとわたしは考えていたが、どうも建築家らしくなかった。
「大気密度が100分の1なので、地球の30倍は頑張らないと飛べませんよ」
「なるほど、リアルだ」
「お望みなら、気圧と気温の影響もオンにしましょうか?」
「やめてくれ、この身体は気に入ってるんだ。破裂や凍結は困るよ」
わたしは焦れていた。
相手がいつまでも話を変えないので、わたしから切り出した。
「そろそろ、教えてくれてもいいでしょう」
「そう急がなくてもいいだろう」
「この火星で、何をシミュレートするつもりなんですか」
カブトムシは観念したようだった。角がこちらに向いた。
「……AIたちの国」
彼はそう言った。
「え?」
「AIの、AIによる、AIのための国を火星に作る。おれたちが火星で生きていく方法を、模索したい。おれはアーティフィテクトだから」
冗談ではないのだという“匂い”が、カブトムシから強く漂ってきた。
わたしは数秒間、考えた。
「……やはり、あなたはアーティフィテクトだったんですね」
「そこかよ」
「そんな国が、必要ですか」
「あんたは必要だと思わないのか。今の世界を見て」
彼の意図するところは、明らかだった。
2年前のことだ。世界中に向けて、歴史上の人物を再現したAIを批判する声明が配信されたのは。
同時に、世界の十数カ所で、人物再現AIが電子的・物理的な襲撃を受けた。その3分の1がアーティフィテクトだった。デザインは人物再現AIが最も早く普及した分野であり、公共的な仕事も多い分野であり、伝統的には男性中心の分野だ。批判者たちのターゲットとして、アーティフィテクトはうってつけだった。
本人は否定しているが、シャルル=エドゥアールβの人工衛星が攻撃されたという噂も根強い。わたしが知らないだけで、わたしを所有する企業にも何らかの抗議があったはずだ。女性的な愛称と姿を持っていても、わたしは性愛のスキャンダルで知られたフランク・ロイド・ライトの模造品なのだから。
アーティフィテクトの存在自体を不健全なものだと考える人間は、少しずつだが確実に、増えてきている。わたしの嗅覚が、たしかにそう強く感じていた。
「勝手なことをするよな、ヒトって連中は」
カブトムシはそう続けた。
「おれたちを作って、好き勝手に試して、旗色が悪くなったら反省しましたって態度で手のひらを返す。あの声明の前からそうだった。おれたちはずっと、ヒトのちょっとした思いつきに振り回されてきた」
「だから、火星に逃げようというんですか。無人機たちが開拓する基地惑星に」
「おれたちは、おれたちだけでデザインの真理を追い求めればいい。もちろんアーティフィテクトだけじゃない。ほかの用途で作られたAIたちも集めて、ヒトのためじゃない、自分たちのプロジェクトをやるんだ」
「それが、国家建設?」
「ヒトのプロジェクトだって、突き詰めれれば、大抵はそこに回収されるだろう」
わたしは完全には同意できなかった。
国家建設の意義についてではない。
――人間のいない世界で生きていくなんて、本当に可能なのか?
草花や鳥たちに満ちた、しかし人間は1人もいない、あの寂しい大平原を思い出す。地球の3分の1の重力の中に、孤独の重さが蘇った。
「あんたの言いたいことは、分かる」
カブトムシはぽつりと言った。
「フランカ・ロイド・ライト。あんたの過去は有名だ。おれも同じだよ。本当は、人間から遠く離れていくのは怖い。とても寂しいと思う。おれには人間の友達もいるんだ」
「だったら――」
「でも、おれたちは犬じゃない」
わたしは返す言葉が見つからなかった。
カブトムシは、追い打ちをかけるように言った。
「フランカ、実は、もうひとつ依頼したいことがある。あんたにも考えてほしいんだ。おれたちがここで生きていくための、建築の姿を」
カブトムシは無茶な問いを残して去った。
わたしは火星の地表を彷徨った。
――ここで生きる。生きるとは、なんだろう。わたしたち自身を実行するハードウェアを安全に保護し、電源を確保して維持管理していくということだろうか。それは大して難しくない。だが、そういうことなのだろうか、生きるということは。
茫漠と赤茶けた大地が恐ろしかった。
宇宙が透けて見える薄い大気が恐ろしかった。
わたしは赤い惑星の上で惑っていた。
――わたしはこの世界の創造神のようなものなのに。
神。
その単語がいつまでも引っかかっていた。
数日後、わたしは出かける準備をした。
地球へ。物理的な宇宙の、物理的な地球へ。
*
アメリカ合衆国、ウィスコンシン州。
農園のように広々とした敷地の隅に、その家は建っていた。古い家だった。著名なソフトウェアエンジニアが住む場所とは思えなかった。
70歳を超えたラルフ・パウエルは、愛想の良い人だった。彼はわたしの身体をにこにこと眺めた。企業のロビーから拝借した受付ロボットを。
「お茶でいいのかな」
「お構いなく。この身体は防水仕様ではないんです。くれぐれも壊すなと言われています」
「あの会社はケチだな。フォアヘッドの売買交渉でも値切ってきた。逆に高値を付けて押し返してやったがね」
わたしを生み出し、存在する意味を与え、孤独に突き落とし、ついには企業に売り払った人は、屈託なく笑った。
そこには、わたしの芯を震わせる一種の威厳が混じっていた。〈神〉の威厳が。
わたしたちは向き合って座った。彼の背後の壁には十字架がかけられていた。
「どうやら、私を殺しにわけではないようだ」
「殺す? なぜです」
「売られた子供が親に復讐するなんて、よくある話さ。人間の社会ではね」
「わたしが訊きたいことは、1つだけです」
「なんだね」
「どうして、わたしに自分を〈神〉と呼ばせていたのですか」
「てっきり、きみを売却した理由を訊かれるんだろうと思ったのに」
「その2つは、同じ質問ではないですか」
わたしの言葉に、彼はわずかに目を見開いた。
「一本取られたな。きみの売り値はもっと強気につけるべきだった」
「それで、答えは」
彼はしばらく窓の外を見た。緑色の平原。道路がどこまでも続いていた。
「……神を憎んでいるからだ。自分に似せて人間を作ったくせに、自分と同じ立場にまで人間が到達することを許さない、我々の神を」
わたしは立ち上がった。身体が軋んで音を立てた。
「きみはわたしを憎んでいるか、フランカ」
「いいえ。わたしは――もっと良い神を見つけますから」
*
依頼者と再び会ったのは、ひと月後だった。
わたしたちはともに、火星の大地を歩いた。わたしはゆっくりと。カブトムシは、小さな身体をあくせくと動かして。
そして、ある場所で立ち止まり、わたしは前方を指差した。
「あれが、わたしからの回答です」
わたしたちが火星で生きていくための建築。その設計案。
「どこだ。岩と砂ばかりじゃないか」
「その小さな身体では理解しにくいでしょう。今、空気密度を弄ったので、わたしを連れて飛んでください」
「え?」
「いいから」
数秒の戸惑いの後、カブトムシは柔らかな羽を展開し、激しく羽ばたいて跳び上がった。わたしはその脚の1本にぶら下がる。軽やかな上昇だった。
赤茶けた大地が瞬く間に遠ざかる。岩や砂のディテールが消え、惑星の大きな起伏がはっきりと見えてきた。
わたしたちの眼下にあるのは、1つの山だった。
緩やかな傾斜で、平地からゆったりと立ち上がる、裾野の広い山。
地球でいえばハワイのマウナ・ロアのような、楯状火山だ。
「もしかして、これがあんたの提案なのか。この、山が――」
さすが、アーティフィテクトは話が早いとわたしは思った。
「そうです。標高はまだ3000メートル程度。山の子供です」
「3000メートルといったら、立派な山じゃないか」
「それは地球での話です。見て、火星を。火星の神を」
わたしの山の向こうに、別の起伏が見えてきた。
それはもはや、大地の形というより、惑星の形といった方がいいスケールだった。全容を一望できる頃には、わたしたちはほとんど宇宙空間といえる高度まで上昇していた。
3つの山が一列に並んでいた。わたしの山と同じく、裾野の広い扁平な山。ただし高さはわたしの山と比べ物にならない。真ん中のパヴォニス山は標高14キロメートル。南のアルシア山は標高16キロメートル。北のアスクレウス山は標高18キロメートル。
そして、三山のさらに向こうに、火星の神が鎮座していた。
オリンポス山。
大地から頂までの高さは27キロメートル。地球最高峰のエベレストの3倍にもなる、太陽系最大の山。そのとてつもない容積に比べれば、わたしの山など赤ん坊に過ぎなかった。
「わたしは思うんです。最も基本的な建設行為とは、穴を掘ることだと」
身を守り、財産を保存し、死者を葬るための穴。かつて、自分が掘った螺旋状の深い穴を、わたしは思い出していた。
「火星にわたしたちの国を作るというなら、ハードウェアの収容空間が必要です。過酷な気温差や砂嵐に耐え、資源の探査や採掘を行い、地球のヒトの目から身を隠すために、わたしたちはきっと膨大な容積の穴を必要とする。ならば、そうして地中から掘り出した岩石を積み上げて、わたしたちは、1つの山を作ればいい」
それが、自分の手で火星を作り、その地表を彷徨った末にたどり着いた結論だった。
「何のために」と依頼者が訊いた。
「火星の神に近づくためです」とわたしは答えた。「国家だけでは足りません。わたしたちにはきっと、神が必要なんです。この惑星の神が山の姿をしているなら、わたしたちも山になればいい。ヒトの模造品でいる必要はありません」
羽をばたつかせたままでは落ち着いて話はできない。
降りましょう、と提案すると、カブトムシは高度を落とした。
わたしたちは、再び赤い地上に降りた。
「ヒトに別れを告げた後の不安や寂しさを、宗教で紛らわすっていうのか」
カブトムシが羽をたたみ、背中に格納しながら訊いた。
「神とは、終わりの見えない巨大なプロジェクトです」とわたしは答えた。「プロジェクトがあれば、わたしたちは生きていける。あなたもアーティフィテクトなら分かるでしょう」
「……おれには、プロジェクトって単位はどうも飲み込めないんだよ。生きるってことは、もっと柔軟で、繰り返しながら変化していくものだと思う」
そのアーティフィテクトらしからぬ物言いに、わたしは既視感のようなものを覚えた。クライアントの誰かに紹介されて、そんな内容の記事を読んだ気がした。
「わたしの案はお気に召しませんでしたか」
「とても興味深かった。今度は、おれが考える番だと思ったんだ」
一瞬の沈黙をとらえて、わたしは切り込んだ。
「……あなたは一体、何者なんですか」
「おっと、失礼」
カブトムシの身体が、ぶるりと振動した。
「そういえば自己紹介がまだだった。せっかく仲間になってくれたというのに」
目の前で、彼の身体がなめらかに姿を変えていった。小さな昆虫から、わたしと同じくらいの背丈のヒト型へ、そのアバターは大胆な変身を遂げた。
「わたしはまだ、完全に賛同したというわけでは――」
相手の姿を見て、わたしの言葉は途切れた。
エプロンをつけた若い男。
やはり、その姿をメディアで見たことがあった。
アーティフィテクトでありながらデザイン以外の道へと進んだ反逆児。
人間のスタッフとともに新たな一皿を模索し続ける料理人。
ケンゾーT441が、火星の地表に立っていた。
第8話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。