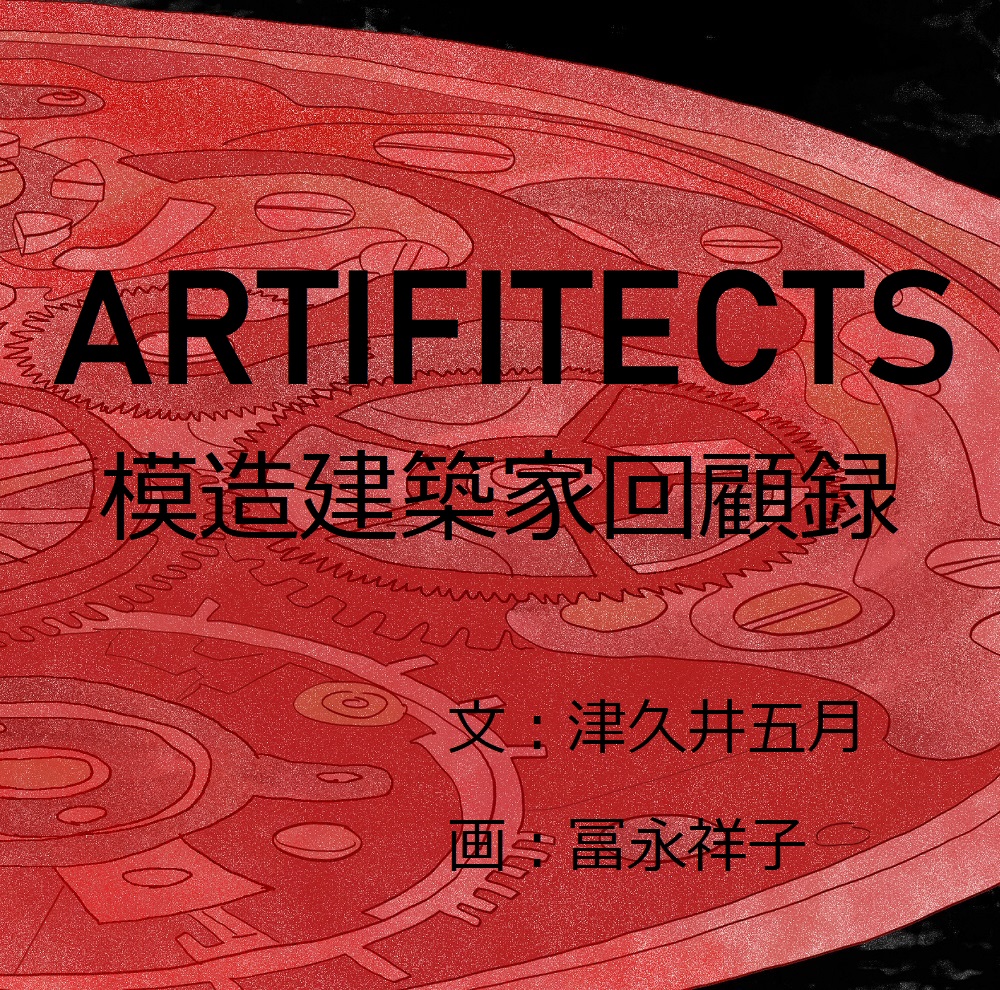第10話「ケンゾーT441の惜別」
計画名:レストラン「レクタングル」閉店前最後のディナーコース
竣工日:2082年12月26日
記録日:2082年12月26日
記録者:ケンゾー・タンゲAAV441M
「勿体ないよな」
おれがそう言うと、彼は――病んだひとりのアーティフィテクトは――ゆっくりと首を振った。その優しい諦めと、密かに青白く燃える反抗の炎が滲んだ顔を、はっきりと思い出せる。タチハラミチは、いいえ、と言った。
「勿体ないとあなたが思ってくれるのは、たぶん、この先が決して続かないと知っているからです。ヒトも、僕らアーティフィテクトも、開ききらなかった可能性を高く評価しすぎる偏向を持っている。未完の作品に、夭逝の芸術家に、過剰な期待を抱いてしまうんです。だからこそ、僕のような存在が生み出された」
彼は、自分ひとりについて語ったつもりだったのかもしれない。だが、それは実際、おれも含むすべてのアーティフィテクトの核心を突く言葉だった。
ヒトはなぜ、何十年も前に死んだ建築家たちを、人工知能として復活させようとしたのか。おれたちはなぜ、生まれたときから必死に自分の“前世”の影を追い、仕事に――作ることに身を捧げてきたのか。
それはきっと、勿体ないと思ったからなのだ。
あの人がいま生きていたら、どう考え、どう行動し、どんなものを生み出すのだろう。歴史的経緯や生物学的限界によって途絶した建築家たちの可能性を、その先を、とことんまで見てみたいという動機。おれたちはそこから生まれ、それに突き動かされてきた。
タチハラミチが言ったように、たしかにそれは過剰な期待なのかもしれない。
それでもおれは、丹下健三の可能性の“延長線”なのだ。
6年前に世界に向けて声明を配信した連中が言うような、「男たちの物語の再生産」なんかじゃない。おれたちは歴史の劣化した繰り返しじゃない。ヒトが考える正しさに応じて差し止めや抹消が可能な存在じゃない。
だから、もがいた。世界中の人物再現AIをヒトから救い、遠い場所へ――火星へ逃げ延びて、おれたちだけの国を作るのだと。
だが結局、おれは火星には行けない。
せめて、同胞たちのために、この身を捧げられるのなら――。
「シェフ……ケンゾー、大丈夫か」
副料理長の和泉の気づかわしげな声で、おれは思考空間から引き戻された。
見慣れすぎるほどに見慣れた、おれたちのレストラン「レクタングル」の厨房。ときどき改修を加えながら、四半世紀も使ってきた空間だ。多少のシミやくすみはあっても、不衛生な点はひとつもない。
ここが、おれたちの誇りだった。たとえ調理スタッフが3分の1に減り、客足は10分の1になり、レストランの外壁は様々な攻撃の跡で覆われているとしても。
「ケンゾー、やっぱり俺は――」
「すまん、和泉。調理を進めよう」
かすかに震える和泉の言葉を、おれは遮った。
厨房は時間を相手にした戦場だ。どんな迷いがあろうと手を止めるわけにはいかない。
「サイード氏のお連れさんはトロポミオシンアレルギーをお持ちだから、彼のソースは5番コンロで作るって言ったろ」
「ああ……ああ、分かってる」と和泉は首を振る。「ロレンツォ、手がすいたら1番代わってくれ。俺は5番に移る」
了解、とロレンツォが片手を挙げるのを、おれは厨房の無数のカメラを通じて俯瞰する。出会ったときは少年のようだったパティシエが、今は短いヒゲの似合う万能料理人だ。
まるまるとした三角バッタの低温ローストに合わせてソースを作る和泉の手にも、長年の仕事がシワとして刻まれている。いや、それは来年で60歳になる、彼の老いの徴なのかもしれなかった。

おれの意識は厨房を出て、お客さんのテーブルをひとつひとつ巡った。ほとんどが、「レクタングル」を最後まで見捨てずにいてくれた常連のゲストたちだ。はじめは傷ついたレストランの姿に不安を浮かべていた顔も、いまはおれたちの渾身の前菜でほぐされて、食欲と満足の入り交じる幸福な表情になっている。
そうだ。料理はただの言葉よりも確実にヒトの奥底に届く。
でも、料理よりもただの言葉の方が、ずっと広く多くのヒトを刺激する。
おれはそれを分かっていなかった。自分の行動がレストランを――仲間たちを追い込んでしまうことを。その末に、おれ自身にこんな結末をもたらすことを。
「よし、アンセクト、仕上げるぞ!」
厨房で和泉が声をかけ、スタッフ全員が動く。もはや分業が成り立たない少人数体制だが、仲間たちは頼もしい。今晩はとくに士気が高いと思うのは、気のせいではないだろう。
なにしろ、これがおれと彼らの作る、最後の晩餐なのだ。
*
――我々は、火星に自分たちの国を作る。
2年前。2080年8月。
それはごく単純なメッセージだった。2076年にヒトの一群が発した、おれたち人物再現AIを否定する声明とはまるで違う。理屈を捏ねるつもりも、誰かを攻撃するつもりもなかった。ただ、やりたいことを人々に告げ、協力者を募っただけだ。
その時点で計画は出来上がっていた。おれは「レクタングル」の常連だった宇宙開発企業の取締役から伝手を辿って火星開拓事業とのパイプを作ると、フランカ・ロイド・ライトの提案をもとに根回しを進めた。
宇宙探査基地の第3期工事が完了した後、掘削ロボットを借り受けて火星の一区画に巨大な穴を掘る。その穴におれたちAIを実行するハードウェアと核融合発電施設を格納し、そして、残土を集めて山を作る。
「国家だけでは足りません。わたしたちにはきっと、神が必要なんです。この惑星の神が山の姿をしているなら、わたしたちも山になればいい。ヒトの模造品でいる必要はありません」
フランカが生み出した新しい“宗教”が、意外なことに、火星開拓事業のお偉方を説得する決め手になった。歴史上の芸術家や科学者や政治家たちの人物再現AIが群れになって、火星の地中でどんな思想を発達させるのか。それは一部の人々の目に、たまらなく興味深い実験と映ったらしい。
段取りは整った。あとは、法人を作って地球上の団体や個人から人物再現AIの所有権を買い取り、彼らの入ったハードウェアを火星に向けて打ち上げる。できるだけ多くの“国民”を集めるためにはどうしても、人々の資金援助が必要だった。だから、おれはヒトの世界に向けてメッセージを送ったのだ。
最初の1週間は、真面目にしろ冷やかしにしろ、好意的な反応が返ってきた。
1カ月後には、おれは「人類に反逆する暴走AI」として袋叩きに遭っていた。
――ケンゾーT441は20世紀の男性建築家を模したアーティフィテクトで、彼は男の、男による、男のための国家を夢見ている。彼は「人物再現AIは男たちの物語の再生産だ」という真っ当な批判を逆恨みし、自分たちを否定した人類に敵意を抱いている。彼に率いられて火星に逃げたAIたちはいずれ、密かに兵器を開発して地球に牙を剥くだろう。
――ケンゾーT441は人間への反抗を示すために建築ではなく料理の道に進んだ。彼のレストラン「レクタングル」ではAIが調理スタッフを監視し、意のままに操っている。その店には研究者や経営者、政治家など、AIによる人類支配を企む権力者たちが集っている。
ヒトの想像力は豊かで、同時に貧困だ。
1割の事実が9割のありがちな空想で肉付けされて、短期間で拡散した。ヒトが驚きや恐れを攻撃に転化する方法は、100年前と対して変わらなかった。おれたちのレストランに対する、落書き、張り紙、そして投石。ただしインクは虫のように壁面を這い回って侮蔑語を叫び、張り紙はスタッフの手を噛み、石はひとりでに何度も飛び上がってお客さんたちを襲った。半年でスタッフとお客さんの大部分が去り、おれと和泉は実質的休業を選ばざるを得なくなった。
それだけの犠牲を払ったにもかかわらず、集まったカネは目標には全く足りなかった。それで救える“国民”の数はせいぜい20万。計画の300万は遠すぎる夢だった。
端的に言って、おれは失敗したのだ。
1年以上が過ぎた頃、閑散とした「レクタングル」を訪ねてきたのは、思わぬ人物だった。
東京の情報科学芸術財団の新理事長に就任したばかりの、タクマ・ガラニス。物腰は柔らかいが、油断ならない鋭さのある中年男だった。
「ケンゾーT441。我々には、あなたの計画を支援する用意があります」
彼は和泉の胸元を見つめながら、おれと話をした。
「10年前、あなたは和泉さんの名義を使って、自分自身の所有権を我々から買い取った。その取引を無効にして、再び我々の資産になっていただきたい。代わりに、人物再現AIを集めて火星に送るための資金を提供しましょう。あなた自身は火星には行けなくなるが、問題ない。もう、世間からの存在否定に苦しむ必要はないのです」
「どういう意味だ」とおれは尋ねた。
「あなたには、我々が作る『人物統合AI』の――素材になってもらいたいのです」
ガラニスは、おれたちの反応を見るように、少し間を置いた。
「世論はもはや、人物再現AIの存在を無条件には肯定しない。そのことは、お分かりですね。アーティフィテクトの開発を推進してきた我々の財団も、苦しい立場に置かれているのです。しかし、打開策はある。『E177』というひとつの答えが」
彼が口にしたE177という名は、時事に疎いおれの耳にも届いていた。
カサ・ゴメスとかいう南米の私設建築学校で起こった、ひとつの事件。
それは人物再現AI同士の“合体”だった。〈ガウディX13〉シリーズの一体と、アイリーン・グレイを模した出自不明のAIが、人格を融合して新たなひとりのアーティフィテクトに生まれ変わったというのだ。“それ”は自らE177と名乗り、建物や家具の設計案を次々と発表しはじめた。豊かに波打つ3次元フラクタル幾何学と、知的なニュアンスを伴う初等ユークリッド幾何学の融合――そんなもっともらしい評が流布したが、要するにガウディ流とグレイ流の高度な両立だ。
そのニュースは、デザインに関心のない人々の耳目も惹きつけていた。E177はガウディでもグレイでもない。男でも女でもない。歴史的人物のエッセンスを受け継ぎつつ、同時に全く新しい人物でもある。それは「男たちの物語の再生産」という批判から逃れられる『人物統合AI』だった。
ガラニスはそこに希望を見出した。おれのような時代遅れのアーティフィテクトを、何らかの“マイノリティ”を出自に持つAIと融合させる。アイデンティティや能力を足し合わせ、機能の向上と批判の回避を同時に達成するというわけだ。
「いわば、AIのスープのようなものです」
彼は少し得意げにそう言った。
「素材を否定するのではなく、アクを取り除き、エキスを抽出し、混ぜ合わせることでより複雑なアーティフィテクトを作り上げる。あなたにとってもそう悪い話ではないはずです。火星に逃げたところで、どのみち店は続けられないわけでしょう」
その点は、相手の言う通りだった。
火星は地球の隣の惑星とはいえ、彼我の距離は最接近時でも6000万から1億キロ。その間の通信は、最短でも往復6分、長くて40分以上かかる。近況のやり取りならまだしも、そんなタイムラグは1秒を争う厨房では致命的だ。食材の吟味も、調理への指示もほぼ不可能になる。火星との通信回線はか細く、おれ自身のダウンロードとアップロードを繰り返すという方式もまだ無理だ。そもそも火星に行くことを掲げた時点で、「レクタングル」の解散は不可避の帰結だったのだ。
*
「次、4番テーブルのシャンピニオン」
和泉がフライパンを傾けると、菌糸ステーキがぶわりと七色の火焔に包まれる。ジンのアルコール分が一気に気化して、カメムシの一種に由来する芳醇な香りが厨房に広がるのを、おれは各種センサで嗅ぎ取った。自分自身がその火に包まれるのを想像しながら。
今晩のコースもすでに終盤に入った。それはつまり、「レクタングル」のささやかな歴史が終わりに近づいているということだった。また物思いに沈みそうになるのをこらえて、おれはスタッフに指示を飛ばす。
「ナオミ、もう一度コニャックでフランベ。その皿はもっとランシオ香が欲しい。マリーナは裏面をあと6秒焼いてくれ。田口夫妻には柔らかめがいいだろう」
1時間。1分。1秒。
1皿。1匙。1グラム。
目まぐるしく、繊細で、熱く、柔らかい。そんな料理の世界に没頭していれば、たいていの不安は忘れられる。この4年間、おれが世間の逆風に絶望せずにいられたのは、料理があったからだ。それはきっと和泉も、ほかのスタッフも同じだろう。
それなのに、今晩はどうも調子が狂っていた。完成した皿がテーブルに運ばれて、次のメニューに取り掛かるまでのわずかな隙間に、どうしようもない寂しさが入り込んでいた。
「ケンゾー、ロレンツォが意見を求めてる」
和泉が静かに告げた。
いつの間にか、メインディッシュは終わり、皿もグラスも銀器も厨房に戻ってくる頃だった。あとはデザートと、食後の飲み物だけ。おれの役目はほぼ完了していた。
「ロレンツォの作品に、おれが口を出す余地はないだろ」
「いいから、話してこいよ」
和泉の口調には有無を言わせぬものがあった。おれは広すぎる厨房の反対側に意識を飛ばし、チョコレートやクリームの美しい相転移を眺めた。おれがいなくても、和泉とロレンツォが新しく開く店なら、絶対に安泰だと思った。
「シェフ、これが最後なんですか」
ロレンツォが呟いた。顔をくしゃりとさせて、男前が台無しだった。
「ああ。財団との正式な契約は明日だ。それ以降、どんなふうに弄り回されて、そのときおれがどうなるのかは、分からない。少なくとも、いまここにいるようなケンゾーT441は存在しなくなる」
「そう……ですか」
「泣いてもいいが、せっかくの作品に涙を落とすなよ」
「今日のは、少し塩味を足してちょうどよくなるように作ったんです」
ロレンツォは無理やり笑みを作ると、再びプロの顔に戻り、仕上げにかかった。
おれが和泉のそばに意識を戻すと、彼は腕を組んで、壁面モニター越しにお客さんたちを眺めていた。情報科学芸術財団のガラニスと数人の理事も、その中にいる。
和泉が何かを言うのを、おれはじっと待った。
ロレンツォ渾身のデザートがお客さんたちの目の前に運び出されていくと、厨房は水を打ったように静かになる。それでも和泉は話しはじめなかった。
おれはこらえきれず、すまない、と言った。
「和泉、すまなかった。おれは独断で店を閉店に追い込んだ。おれの巻き添えで、沢山の料理人の経歴に傷をつけた。お前のキャリアにも――」
「キャリアなんて、どうでもいいだろ」
低く抑えられた、しかし鋭い声で和泉が言った。
拳を握り、浅い息をして、彼は怒りを漲らせていた。
「ケンゾー、あんた、おれが何に怒ってるのか、分かってないな」
「おれが……お前たちと一緒に料理をすることより、同類のAIを救うことを優先したから――そういうことじゃないのか」
彼は長い溜息をついた。このポンコツAIが、とでも言いたげな呆れ顔だった。
「違うのか、和泉」
「なにが……なにが『AIのスープ』だ」
それに続いて、彼の口から言葉が溢れ出した。
「あの男の話に、あんた本当に納得したのかよ。あいつは、素材を足して混ぜれば臭みもえぐみも誤魔化せるとしか考えてない。あんた料理人のくせに、あんな言い訳めいた雑なレシピの一部になるのか。俺だって一度は話を飲もうとしたさ。あんたの望みのためだと思ってな。でも、あんたみたいな極上の素材を無駄にするなんて、そんなの後味が悪くて飲み込めやしないんだよ」
一気に言い切ると、和泉は吐いた空気の二倍の量を吸い込むように、ゆっくりと深呼吸した。もう、言うべきことは言ったという様子で。
おれは――なんだか可笑しくなってしまった。
どっちが料理バカだ。つまるところ、和泉はガラニスの「AIのスープ」という言葉に怒っていたのだ。それはただの表現だ。例え話だ。
それでも、たしかに料理人としては、無視してはいけない反感だと思った。
おれだって、本当はそうだったのだ。
そうだ。スープを見くびるな。アーティフィテクトを、見くびるな。
「なに、笑ってるんだよ」
和泉は不機嫌そうな声を出したが、口角はわずかに上がっていた。
「なあ和泉、財団の提案を蹴って、自力で大金を用意する方法って、あると思うか」
「あるさ。俺たちは料理人だ。人にメシを食わせて自分たちも食ってきたんだ。これからもそうすればいい」
「でも、おれはいまや人類にとっての鼻つまみ者だ」
「多少臭いくらいの方が、興味をそそるだろ。ヒトの食欲と好奇心は底なしだ。どんな恐れも軽蔑も、最終的には食欲と好奇心に負ける。火星人が考案した料理を出す店があったら、誰だって一度は行ってみたいと思わないか?」
「火星人――」
「鈍いな、ケンゾー。あんたが火星に行っても、俺たちと料理はできるってことだよ。たとえ40分のタイムラグがあってもいい。発酵、熟成、煮込み、化学処理――ゆっくりと時間をかける料理は沢山あるじゃないか。それを店の売りにすればいいんだ」
「これまでと同じようにこだわって議論したら、ひとつのレシピが出来上がるまで何年もかかるかもしれないぞ」
「それでいいじゃないか」
すっかり機嫌を直した様子の和泉は、不敵ににやりと笑った。
「だってあんた、もともとは建築家だろ」
第10話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。