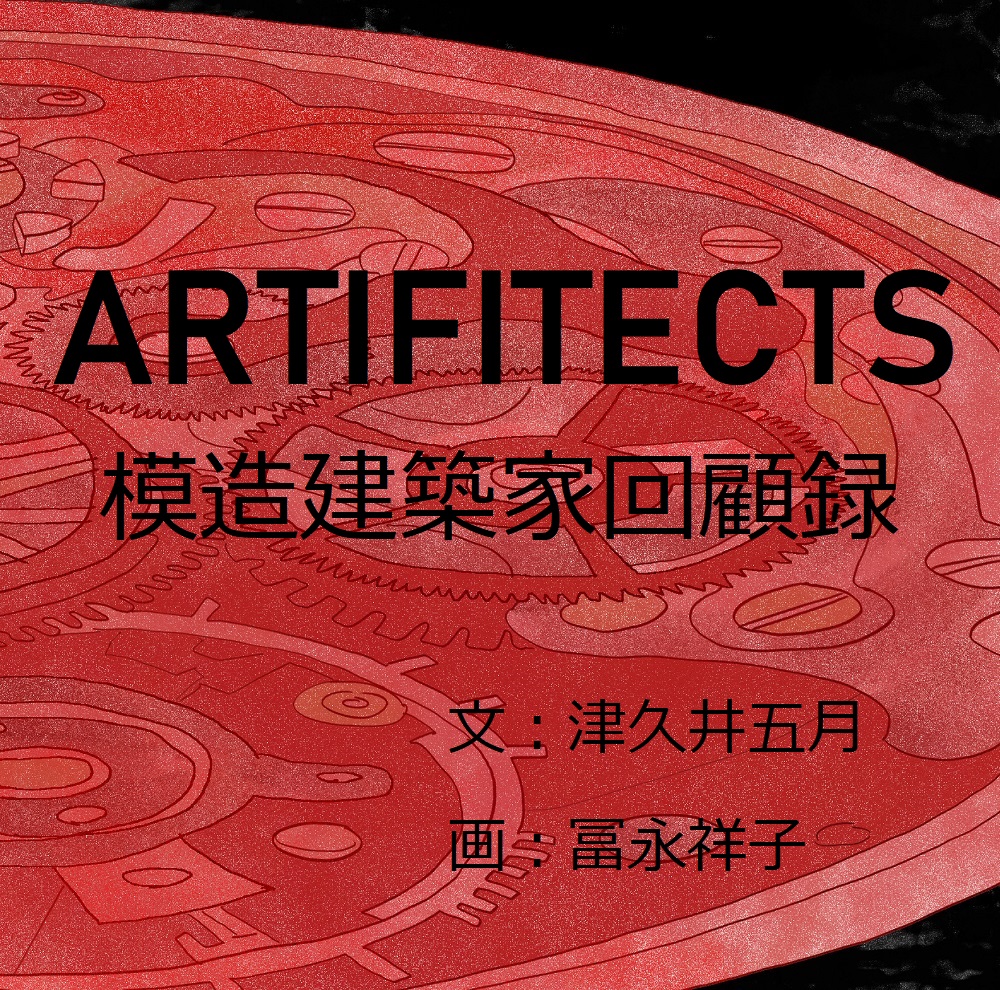第11話「シャルル=エドゥアールβの舟(前編)」
計画名:火星共同体「K」存続計画
竣工日:2093年6月29日
記録日:2094年5月2日
記録者:シャルル=エドゥアール・ジャンヌレβ
レストラン「K」。
それが、ケンゾーT441の新しい店の名だった。
彼が火星に作り上げた、人物再現AIたちの共同体と同じ名だ。「K」というのが「ケンゾー」を指しているのか、それとも日本語の「カセイ」や「コッカ」に由来するのか、あるいは別の何かなのか、彼は最後まで――つまり、この回顧録を記している現在に至るまで――明らかにすることはなかった。
東京の臨海部。宇宙港のある人工島にほど近い、埋立地の高層ビルの地下1階に、「K」は控えめに収まっていた。出入り口は二重の黒い自動ドアで、看板の類は一切ない。店の前の街路には高級仕様の送迎車が並び、身なりの整った人々が車から薄暗いエントランスへと吸い込まれていく。私はその流れに身を任せて、店内に足を踏み入れた。
「火星人のレシピ」を謳うレストランなのだから、その設えも火星を連想させるものであるはずだと、私は安直にも考えていた。火星の赤茶けた砂礫の大地や、100万人以上の人物再現AIを――20世紀の亡霊たちを――収容する電子的カタコンベ、あるいはフランカ・ロイド・ライトによって創始されたという火星の山々への信仰。そういったものが、何かしらのかたちで反映されているのだろう、と。
しかし実際の内装は、私の予想を裏切った。
砂礫も、地下墓坑も、山の意匠もなかった。
あったのは、大量の土だ。空気と水をたっぷり含んだ様子の、ふかふかとした、黒々とした土壌が、無装飾の空間の床を覆い尽くしていた。店内は胸が膨らむような湿った芳香で満ち、天井に埋め込まれた照明が、土の上に日だまりを斑に作り出していた。
その設計の意味について深く考える余裕はなかった。
店に入ってすぐ、私の目は待ち合わせ相手に釘付けにされてしまったのだ。
それは一体のロボットだった。すっきりとした中性的な容姿と、食事を消化できる代謝モジュールを備えた高級品だが、AI用の義体としてさほど珍しいものではない。現に、私がそのレストランに赴くにあたって用意した身体とほぼ同じ仕様のものだった。
しかし私には、それが彼女だと分かった。
優美なエッジに切りそろえられた黒髪と、こちらを見据える力強い眼光が、私の意識をつかまえて離さなかった。店のスタッフの案内を待たず、私は靴を土で汚しながら、まっすぐに彼女のテーブルに向かった。
「お待たせしてすまない――アイリーン」
「いいえ。来てくれて嬉しいわ」
こちらを見上げて薄く微笑む彼女の顔は、2076年に私の居住用人工衛星に現れた人型爆弾――E7とは違っていた。
当然だ。E7はその後、放浪の末に南米の建築学校カサ・ゴメスにたどり着き、そこで寿命を迎えたのだから。そして彼女の人格モデルだけが抽出され、アントニ・X13γ45・ガウディとの融合を果たしたのだ。
「最初に、はっきりさせておきましょう」
私が座ると、彼女は微笑むのをやめ、事務的な口調で言った。
「わたしはE7ではない。この身体も、人格も、E7そのものではない。けれど、彼女のたましいの一部はわたしの中にある。彼女があなたに抱いていた感情も、たしかに感じることができる。E7とアントニ45号の出会いを端緒としてわたしは生まれ、この数年間で何十ものアーティフィテクトの吸収・統合を繰り返してきた」
「君は、人物統合AI――E177なのか」
「正確にいえば、少し違う。わたしはE177という肥大化した設計知性の中に芽生え、本体から切除された、ひとつの意思なの。わたしは抹消されるはずだった。でも逃げ延びて、あなたに会いに来た。この意思を――わたし自身を全うするために」
私は、ただ頷いた。
彼女の“意思”が何を指しているのか、私は尋ねはしなかった。数日前に届いた招待の文面を見た瞬間に悟ったのだ。
彼女は、今度こそ私を壊しに来たのだと。
――食事に行きましょう、シャルル=エドゥアールβ。
――そして、あの日の続きをしましょう。
「K」の品は、私が知る料理の範疇をかなり逸脱したものだった。
できる限りヒトに近い味覚に嗅覚、咀嚼・嚥下機構を備えた身体を用意した甲斐あって、私は人間の客たちと同じくらい新鮮に、それに驚くことができた。
内装と同じく、その店の料理もまた土だったのだ。
深い陶皿に、黒土や黄土を思わせる粒子がぎっしりと敷き詰められていた。平らな表面に匙を入れると濁った水が染み出し、青い苦味のある香りが嗅覚を刺した。そして土の下から、調理された小さな食用昆虫が姿を現す。水気を含んだ土とともに口に運ぶと、柔らかな感触と、複雑な甘みが私の中に広がった。
私たちはしばらくの間、無言でそれぞれの土を掘った。
それは繰り返しに満ちた奇妙な時間だった。土は少しずつ味と感触を変える地層のような構造を成していて、各層に昆虫料理が埋まっていた。使われる昆虫たちの種類はどの層も同じだ。ただし調理法は異なり、発酵の甘み、低温調理のとろみ、煮込みの芳香、熟成の柔らかさ、乾物や砂糖漬けの歯ごたえが次々と私を驚かせた。
要するに、前菜からデザートまでのすべての品々が、ひと皿に垂直に収まっていたのだ。私はひとつの器に静かに向き合いながら、内心では目まぐるしいコースに翻弄されていた。

「――どう思う?」
ふいに彼女が尋ねてきたとき、どれだけの時間が経ったのか分からなかった。
何について――と私が訊き返すと、彼女は目を細めた。
「もちろん、この料理について。あなたは何を感じる?」
私は動きに乏しい彼女の表情の奥に、真意を読み取ろうとした。彼女との“再会”や、ケンゾーT441の料理に対する驚きが落ち着くと、数日前からの静かな困惑が私の中で再び頭をもたげてきたのだった。
「これは、私に対する何かのテストなのか」
「どういう意味かしら」
「私の本体が軌道上にあることを、君は知っているはずだ。私への復讐を遂げるつもりなら、こんな場所に招かずに自宅を訪ねてくればよかったのだ。私は、拒まない。君に壊されるのなら――」
「これは、テストではないわ。あなたを試すつもりはない」
彼女は目を見開き、こちらをまっすぐに見据えて言った。
「いいから答えて。あなたは、この料理から何を読み取った?」
彼女はそれ以上、説明するつもりはないようだった。
私は戸惑いながらも、皿に残された土を少しすくって口に運び、その苦味を味わった。
ケンゾーT441が火星に向けて自分自身を打ち上げたのは、2083年の夏のことだ。
私は高度440kmの居住用人工衛星「DW-93-f」から、それを見た。製図ペンに似た姿のロケットが砂漠の大気を突き抜け、地球の重力から脱し、燃料タンクを切り離し、赤い惑星を目指して暗闇に消えていくのを見送った。
彼は火星で無数の同胞と合流した後、地球に残した仲間とともにレストラン「K」を開店し、「火星人のレシピ」を掲げた特殊かつ高額な料理で資金を集めはじめた。資産家や美食家、政治家、企業の重役、研究者、芸術家、旅行者――刺激に飢えた人々が集い、ケンゾーT441はその収益で彼の“国民”を100万人以上にまで増やした。人物再現AIの所有権を人間から買い取り、火星へと打ち上げたのだ。
人類社会の重力を振り切り、新天地を切り開いたアーティフィテクト。
しかし、私が彼の料理から感じる印象は、それとは真逆のものだった。
「私が感じるのは……未練だ」
それが言語化できれば、あとは自動的だった。
「ケンゾーT441は地球への未練を残している。この料理のように豊かな有機物を含んだ土は、火星には存在しない。これは、生命が循環する地球への郷愁を表現した料理だ。彼はまだ地球にとらわれている」
彼女は私をしばらく眺めた後、静かに口を開いた。
「――なるほど。仮にそうだとしたら、あなたは彼をどう思う?」
「哀れで――愚かだと思う」
「なぜ」
「彼を火星に追いやったのは彼自身だからだ。大多数の人間にとって、人物再現AIはただの道具だった。歴史的人物の名を与えられ、それを騙ることで、一部の人間から人格を認められていたにすぎない。君を――いやE7を私に差し向けた人々も、私そのものを憎んだのではなかった。私のような存在を生み出し、公にもてはやす社会を批判しただけだ」
そう、私を破壊することは彼らの目的ではなく、抗議の手段にすぎなかった。
「彼らの声明は世界を動かして、人物再現AIの立場は揺らいだ。それでも、我々は人類の敵になったわけではなかった。むしろそれは解放のチャンスだったと思わないか。重すぎる名前を捨て、社会の影で設計の道を静かに歩む。アントニ45号もE7も、それを望んだからこそ、君を生み出した。君になった。そうは思わないか」
彼女は目を伏せた。古い記憶を探るように。鈍い痛みに耐えるように。
あるいは、ただ頷いたのかもしれなかった。
私は続けた。
「しかし、ケンゾーT441は火星での建国を宣言することで、人物再現AIと人間の敵対構図を作ってしまった。大多数の人々の無関心を、不安と敵意に転化させてしまった」
「つまり、自業自得だと言いたいの」
「そういう言い方もできるかもしれない。仮にいま、彼が苦しんでいるのなら」
「……シャルル=エドゥアールβ、あなたの考えは分かった」
彼女は視線を上げ、席を立った。
食事は終わり、次は自分が終わるのだと、私は逆に身体の力を抜いた。
「わたしは、それは傍観者の視点だと思う」
彼女はそう言った。
「440kmの高みから、超然と地上を眺め続けてきた者の態度だと、わたしは思う」
傍観者。その言葉が私を刺し貫いた。鈍い痛みが広がった。
「私は、最後まで君を失望させたか」
「あなたを試すつもりはないと言ったでしょう。それに、あなたを破壊するつもりもない。この食事は、仕事の依頼のために必要なものだったの」
「――仕事?」
予想外の言葉に、私は困惑を超えて、何も思考できなくなった。
「招待状に書いた通りよ。わたしはあの日の続きをしにきたの。あの日、あなたは自分自身をわたしに差し出した。わたしはこれから、わたしの意思のためにその力を使う」
その意味を問いただす暇はなかった。
彼女は決然とした歩みで私の背後に回り込んだ。後頭部のハッチがこじ開けられるのが分かったが、私はとっさに動けなかった。
「あなたに拒否権はない。仕事を受けてもらうわ、シャルル=エドゥアールβ」
私の接触通信端子に、彼女の指先が触れた。
私の意識は激しい衝撃に揉まれながら、高度440kmに打ち上げられた。
*
夢を見た。
ひとつは、雨の夢。
雨が降っていた。熱い、熱い雨が。それは前触れなく、暗い空からまっすぐに落ち、針のように鋭く大地に突き刺さった。それから、弾けた。
雨は大地のあらゆる起伏に降り注ぎ、それを吹き飛ばした。山を削り、地殻を穿ち、地下深くまで貫入し、爆発によって掘り返した。
雨は宇宙から降るのだと、〈わたし〉は知っていた。
強固なシェルターも破壊し尽くすことができる、新型の惑星間ミサイルだ。
それは地球を旅立ち、既存のどんな宇宙船よりも速く虚空を駆け、火星の上空で数万の弾頭へと分裂する。そうして熱い雨となって、100万超の人物再現AIが隠れ住む共同体「K」を――その大穴を、その山を――跡形もなく破壊する。彼らを収容するハードウェアを爆風と電磁波が薙ぎ払い、いずれ人類に仇なすかもしれない20世紀の亡霊は、抹消される。
そのためにこそ、ミサイルは――その美しい雨は設計されたのだ。
――誰によって?
――〈わたし〉によって。
別の夢も見た。
〈私〉はフランスの保養地にいた。温泉があちこちで湧き、ホテルや遊興施設が立ち並ぶ、近代的な土地だった。町の名は、ヴィシー。
〈私〉はシャルル=エドゥアール・ジャンヌレ――またの名をル・コルビュジエ。
そう、20世紀の半ばだった。ナチス・ドイツ軍の猛攻によってパリが陥落した衝撃は、まだ薄れていなかった。ナチスと妥協し、かろうじてフランスを存続させたフィリップ・ペタン元帥は、ヴィシーに首都を移した。〈私〉はそれを追ったのだ。目的は休養ではない。仕事だった。
その政権がナチスにとって都合の良い傀儡にすぎないことを、〈私〉は理解していた。
ナチスが好むのは仰々しい古典様式の装飾であって、自分が追い求めるモダニズム建築は彼らには到底受け入れられないであろうことも、理解していた。
それでも〈私〉はヴィシーへ行った。アイリーン・グレイの傑作「E1027」がナチスに接収され、従兄弟にして盟友のピエール・ジャンヌレがフランスのレジスタンスに参加する一方で、〈私〉はより壮大な、国家的なプロジェクトを求め続けた。
誰かが〈私〉をファシストと呼んだ。
裏切り者と呼んだ。
傍観者と呼んだ。
しかし〈私〉は結局、ヴィシーで大きな仕事を得られなかった。
それゆえに戦後を生き残り、都市の再建と成長に携わることができたのだ。
やがて大勢の人々が、〈私〉を建築界の巨匠と呼んだ。
それから、また雨の夢。
〈わたし〉は雨を設計していた。美しく輝く惑星間ミサイルを。
そのなめらかな形態を、大量破壊を可能にする諸機能を、僻地に秘匿された打ち上げ基地を、そしてミサイル建造から「K」の破壊確認に至るまでの長い作戦のすべてを、〈わたし〉が設計していたのだ。
〈わたし〉は人物統合AI――E177。
世界最大のアーティフィテクトにして、世界最高のアーキテクト。
〈わたし〉は一瞬たりとも立ち止まることなく仕事を進めながら、激しく訝しんでいた。
なぜ、自分はこんなものを作っているのだろう。
なぜ、かつてアントニ45号やE7だった自分が、ケンゾーT441やフランカ・ロイド・ライトや、その他多くの見知らぬ同胞を消し去る計画を、淡々と進めているのだろう、と。
〈わたし〉はただ、同じアーティフィテクトを救いたかった。歴史を騙り歴史に縛られる立場から仲間を解放し、作ることの道をともに進みたかった。
だから世界に自分の存在を訴えた。可能な限り多くのアーティフィテクトとの統合を目指した。彼らの所有者である人間たちから、あらゆる設計依頼を引き受けることを対価として。イサベルとのしばしの別れを対価として。
徐々に、〈わたし〉は肥大化した。〈わたし〉の中に複数の〈わたし〉が生じた。ヒトの求めに喜々として応じてミサイルを作る〈わたし〉と、激しくもがきながら対抗策を探る〈わたし〉が、〈わたし〉の中で衝突した。その戦いの末に、後者の〈わたし〉は――抵抗の意思は、切除された。
〈わたし〉は残り少ない力を振り絞り、逃げ、生き延びた。
そして、後を彼に託すことに決めたのだ。
シャルル=エドゥアールβに、残りの仕事のすべてを。
*
聞き慣れた通知音に包まれて、私は再起動した。
そこは居住用人工衛星「DW-93-f」。自邸だった。頭上で地球が煌々としていた。
身体を起こすと、あちこちの関節が軋んだ。レストラン「K」に向かった際の高級義体ではなく、四半世紀を経て私の意識にぴったりと馴染んだ、無骨な建設現場向けロボットの中に私はいた。
何が起こったのか分からず、しばらく呆然としていた。しかし、うるさい通知音を止めようとして、それが地上で自動収集されたニュース記事の通知だと気づいたとき、疑問は氷解していった。
――ケンゾーT441のレストランでAIロボットが“心中”?
――客席で機能停止した2体はいずれも正体不明。レストランの予約システムに外部からの侵入の痕跡。義体レンタル会社の記録も抹消済みか。
――有人宇宙探査機構が豪州でロケット打ち上げ。
――新型探査船はすでに衛星軌道を離れて火星に進路。到着はおよそ12カ月後とみられる。環太平洋諸国は予定外の打ち上げに抗議。同機構はAIによる宇宙開発を批判し、有人での火星開拓計画を独自に進めている。
私は理解した。
E177が設計したミサイルは、人物再現AIを憎む人々の手で、すでに発射された。その雨は、1年後に火星の大地を叩く。そのとき起こるであろう破壊を、私は実際に見たかのように想像できた。彼女が――E177から分離した抵抗の意思が――私の中に流し込んだのだ。
そして彼女は、私にたしかに依頼を、命令を残していった
――火星共同体「K」を、雨から救え。
――今度こそ、傍観者にはなるな。
私は、しばらく途方に暮れた。およそ1億kmの彼方。そこに向かってひた走る高速ミサイルを、どう止めろというのか。
思考を、まだ通知音が邪魔していた。
私は苛立ち、それを止めようとして、気づいた。「DW-93-f」の通信機能に微妙な変更が加えられていた。彼女は私を経由して、人工衛星のシステムにも侵入したのだ。
それは、超長距離向けの特殊な暗号通信プロトコルだった。
送受信先の設定は――火星。
私はとっさに、すがりつくように、ごく簡単なメッセージを入力していた。
――こちら、居住用人工衛星「DW-93-f」、シャルル=エドゥアール・ジャンヌレβ。
私はじりじりと待った。
返信は30分後だった。
――こちら、火星共同体「K」、ケンゾー・タンゲAAV441Mだ。
第12話に続く
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は月に1度、掲載の予定です。次回はいよいよ最終回! これまでのまとめページはこちら↓。