【取材協力:朝日新聞社】
京都国立近代美術館で2021年3月7日まで開催中の「分離派建築会100年 建築は芸術か?」展に合わせて、本展をどう見るか、分離派建築会をどう捉えるか、などを3人の方に話してもらった。2人目に登場いただく津久井五月さんは、大学院まで建築を学んだ後、自身の表現の世界をSF小説に求めた人だ。
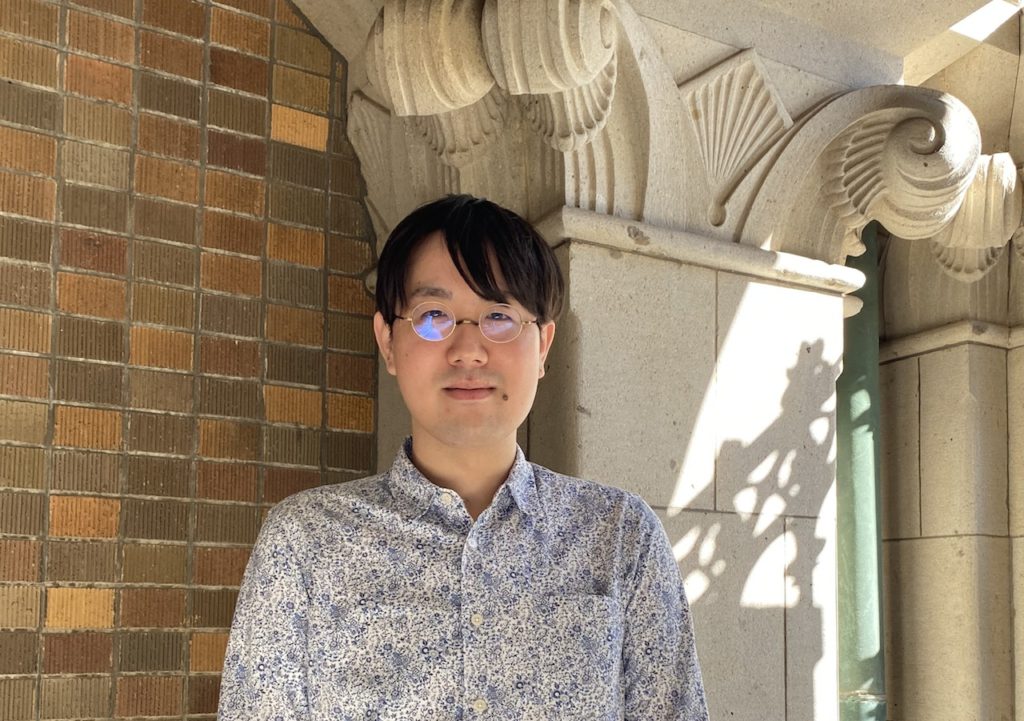
コンピュテーショナルデザインを学んだ学生時代を思い出して
──津久井さんは分離派建築会の結成メンバーと同じ東京大学建築学科のご出身です。ご自身の学生時代を重ね合わせながら展覧会をご覧になったところもあるのではないでしょうか?
分離派建築会はこれまで、反体制というか、佐野利器や内田祥三といった構造の先生への反発から生まれたという文脈で語られてきましたよね。でも建築史家の加藤耕一先生が、そのような二項対立の構図で必ずしも割り切れるものではない、当時の建築学科ではカリキュラムの改変など教育改革を推し進めていて、彼らはその結果として必然的に登場した、という論考を図録でお書きになっています。それを読んで、なるほどと思うと同時に、自分の学生時代を思い出しました。
僕が建築学科に進んだのはちょうど、3DCADなどのデジタル設計ツールを使って建築を考えることが教育レベルに下りてきた時期なんです。3年生のときに取った「算法通論」という授業は、その年からコンピュテーショナルデザインを教える内容に大きく変わり、それまでコンピュテーショナルデザインの授業はなかったので、4年生や大学院生も受講していました。設計課題に取り組むごとに、デジタル設計ツールを使う人が増えていき、デジタル設計ツールで新しい造形やアイデアを試そうという気運に揉まれていたなあと思います。
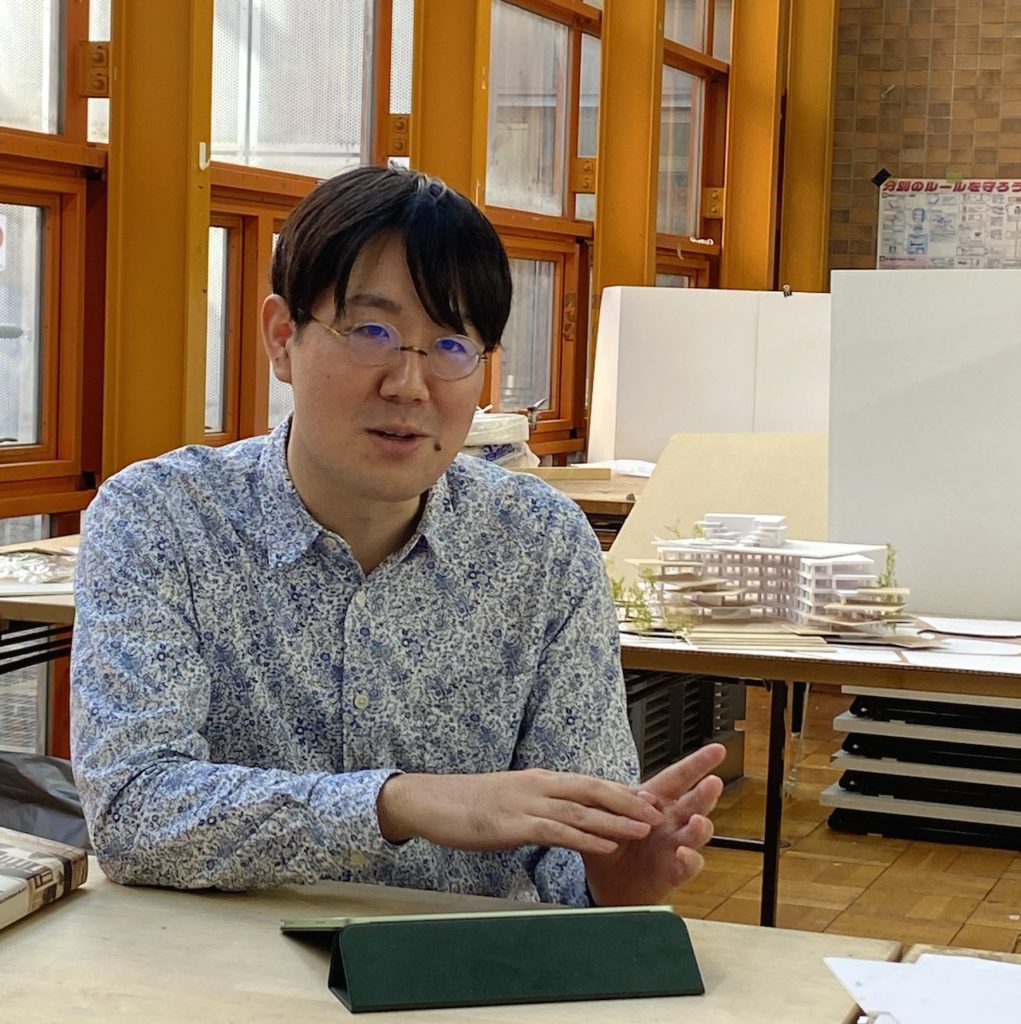
当時はまだコンピュテーショナルデザインは、模型を中心に置いた既存の建築設計からすると異端のように思われていたかもしれません。でも、先駆的にそれに取り組んでいた人たちは別に、二項対立的な感覚ではなかったと思うのです。
大学院では建築生産を専門とする野城智也先生の研究室に入り、BIMの研究などをしました。建築の設計方法論とからめてBIMを見るのはなかなか面白い世界で、ただ3次元の造形をつくるのではなく、もっと広い視野で建築設計を理解したいなあという感触を得て学業を終えました。
──ウィーン分離派(セセッション)が好きなことから、分離派建築会にも興味を持っていたとのこと。セセッションに惹かれたきっかけは?
僕は文科三類から建築学科に進んだんです。もともとは現代詩を研究したいと思って大学に入りました。現代詩を勉強するとロシア・アヴァンギャルドなどにも触れることになるんですね。それで美術にも興味があったので美術史を勉強して、セセッションに出会いました。
美術の観点で眺めると、建築史におけるモダニズムの圧倒的な存在感に驚きます。美術史のなかでモダニズム建築は、セセッションやアールヌーヴォー、アールデコなどと同等に歴史の1ページでしかなく、特に突出して語られることはありません。むしろ装飾的なもののほうが美術史においては幹であると僕は理解していて、セセッションなどは正統なものに見えました。だから建築学科に進んで、モダニズムがいまだにこれだけ大きな影響を与えていることを知ってギャップを感じたものです。僕は建物の外壁などをデザインするイメージで建築学科を選んだのに、いきなり空間についての抽象的な話があったりして。
──分離派建築会の人たちまでは、立面図の重要性を認識していましたよね。展覧会で分離派建築会の卒業設計の立面図を見ると、この時代までは立面図で表現しようという考えがあったことがわかります。その後、立面図の役割はどんどん小さくなっていったように思います。
展覧会では最初に、西洋の様式建築を参照した日本の初期の近代建築の紹介があり、その次に、分離派建築会のメンバーによる、個人的な主題にもとづいた卒業設計の立面図が並びます。あの立面の対比はわかりやすいですね。

集団を名乗る効果は大きく、独特の磁場が人を惹き付ける
──展覧会で他に注目したものは?
民藝運動や宮沢賢治の農民芸術の文脈に関心があるので、第4章(田園へ向かう「足」)は面白く見ました。特に瀧澤眞弓の「日本農民美術研究所」は、山本鼎が始めたという農民美術運動を含めて興味深かったです。農民の生活改善運動に根差した公共的な建築で、自己の表現をからめてバランスを取るという刺激的な実践が、大正期に地方で試みられていたんだなと。今の建築には見られないチャンネルではないでしょうか。

また、単純に形として良いなと思ったのは「東京朝日新聞社」の社屋です。分離派らしい意匠が一つの洗練に向かっていると感じました。

──展覧会ではどんなところを面白がると良いでしょうか?
分離派建築会の舞台だった1920年代の東京や日本がどんな世の中だったのか、時代的な背景と結びつけて展示を見ると理解が深まるように思います。僕は民藝運動や同時代の工芸などを頭の片隅に置きながら、この時代に試みられた様々な実践の一つとして見ました。そのような前提なく、建築学の内部の議論だけを追っていくと、結局この人たちは何がしたかったのだろうというふうに思えてしまうかもしれません。
それと展覧会で最も面白かったのは、分離派建築会は一人ひとりの実践の形はかなり違うけれど、分離派建築会と名乗ったから「塊」として後世に残ったということ。展覧会を開くにしても本を出版するにしても、「我々はこういう集団です」と名乗ることの効果や機能は相当あるのだなと思いました。
分離派建築会と、昨今のアート界で活発な「アート・コレクティブ」(アーティスト・コレクティブ、単にコレクティブともいう)の動きはすごく似ている気がします。コレクティブは集団の意味で、プロジェクトに合わせて形成されることもありますが、基本的には明確なゴールを持っていないし、メンバーの主義主張が完全に同じでもない。だからもやもやしている。でも「塊」になることで、ある種の運動を起こしたり、ポジションを取ったりすることができる。分離派建築会が100年後の今、顧みられていることを通して、コレクティブの存在意義やパフォーマティブな効果がわかりました。
もし分離派建築会が現代に存在したら批判されたでしょう。完全なるボーイズクラブですから。時代を考えれば仕方がないのですが、展覧会にも図録にも女性の名前は出てきません。でも実は、コレクティブには根源的にそういう部分があります。つまり、決して開かれたものではない。現代に存在するコレクティブもジェンダー的な偏りがないわけではなく、その偏りが創作・批評活動において致命傷になった例も見られます。
建築の世界ではユニットという集団形態もありますね。ユニットと違ってコレクティブは集団の輪郭が曖昧で、どこに向かおうとしているのかわからない漂流感がすごくある。僕が卒論で取り上げた「シチュアシオニスト・インターナショナル」(※)も一種のコレクティブで、彼らは結局、どのような方法で何を目指すのかということが内部でかなりぶれがあり、それゆえに研究するといろいろな語り方ができる面白さがありました。
※1957年から72年にかけて、フランスをはじめヨーロッパ諸国において芸術・文化・社会・政治・日常生活の統一的な批判・実践を試みた前衛集団。または彼らによって刊行された機関誌の名称。
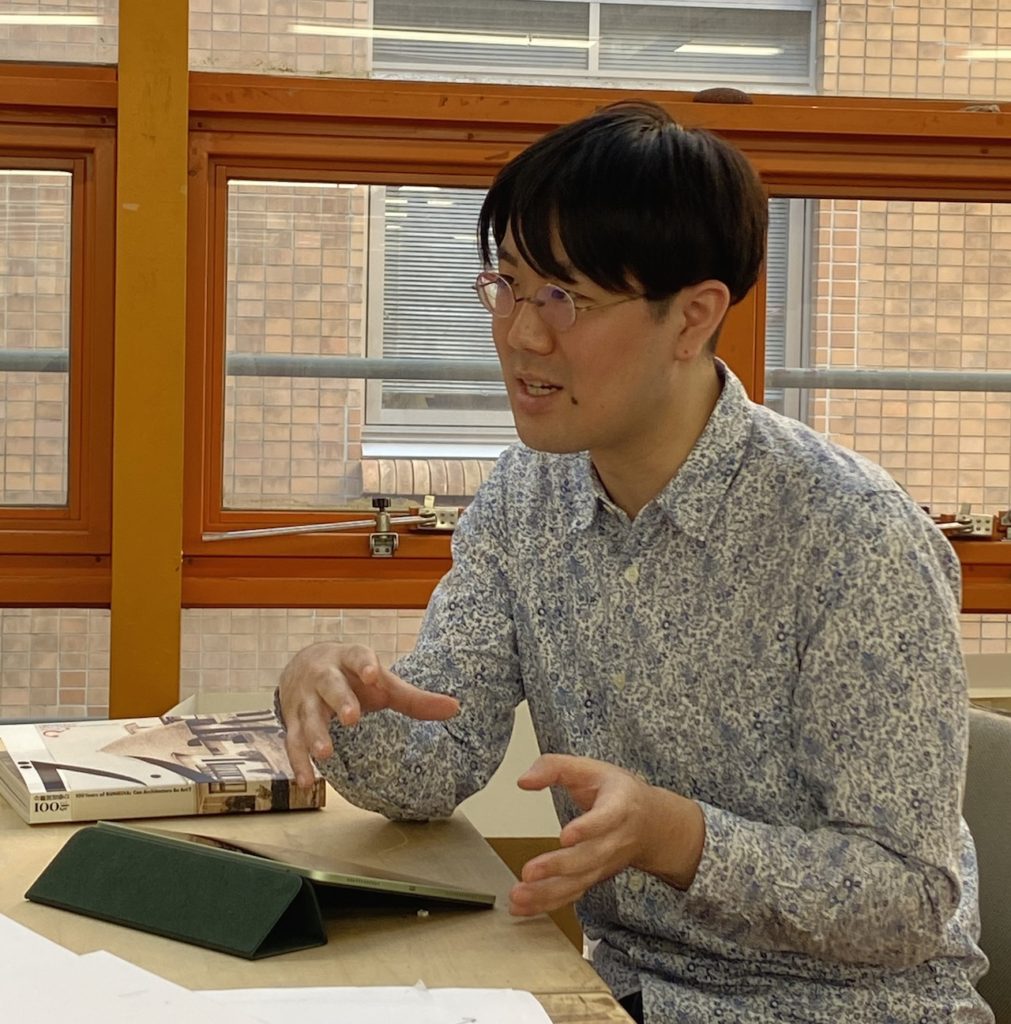
僕がなぜシチュアシオニストに惹かれたのかを考えると、曖昧さをかなり含んでいるからだと思います。今個人的に関わりのあるコレクティブも、集団としては曖昧で、向かう先が揺れ続けているけれど、なんとなく魅力的に感じる。集団独特の磁場があり、それに惹き付けられる。つまり、エモい(笑)。セセッションにしろ、ラファエル前派にしろ、美術史上にはそういうコレクティブがいくつもあります。分離派建築会もその一つと見ると、面白くありませんか?
(後編「都市の未来像を提示した博覧会パビリオンにSF的な想像力が表れる」に続く)
(聞き手:磯達雄、宮沢洋、長井美暁 構成:長井美暁)
〈展覧会情報〉
分離派建築会100年 建築は芸術か?
会場:京都国立近代美術館
会期:2021年1月6日(水)~3月7日(日)
※会期中に一部展示替えがあります。前期:1月6日~2月7日/後期:2月9日~3月7日
開館時間:9:30〜17:00(入館は閉館の30分前まで)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間は変更となる場合があります。来館前に最新情報をご確認ください。
休館日:月曜日
観覧料:一般1,500円、大学生1,100円、高校生600円、中学生以下は無料
Webサイト:京都国立近代美術館
