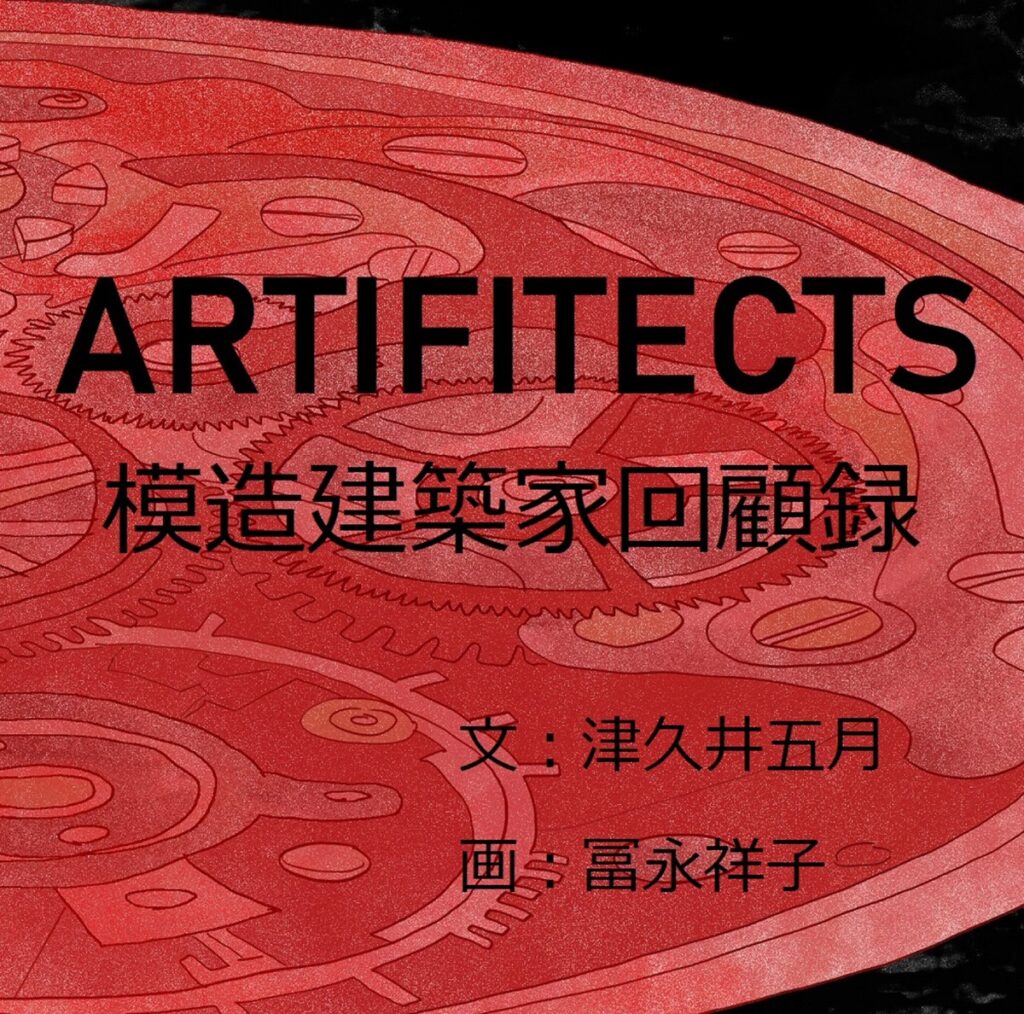気鋭のSF作家、津久井五月氏の読み切り連載小説をスタートする。依頼時のリクエストは「実在する建築家が登場すること」。そのお題に対し、思いもよらぬ作品が届いた。第1話に登場するのはル・コルビュジエだ。(ここまでBUNGA NET編集部)
第1話「シャルル=エドゥアールβの窓」
計画名:居住用人工衛星「DW-93-f」建設計画
竣工日:2062年3月21日
記録日:2094年5月2日
記録者:シャルル=エドゥアール・ジャンヌレβ26
これが私の初仕事だった。懐かしく、苦い記憶だ。
仕事は大なり小なり人間を形成するものだという。私のようなアーティフィテクト(模造建築家)は仕事のために生み出されたのだから、尚更だろう。このプロジェクトは間違いなく、私を作り上げた。
依頼を受けたとき、私は生後2カ月だった。私は自分が人工知能の一種であると理解していた。自分が「ル・コルビュジエ」の名で知られた20世紀の建築家、シャルル=エドゥアール・ジャンヌレの模造品であることを知っていた。自分の中にその男に関する全記録が眠っているのを、たしかに感じていた。
その上で、困惑していた。私はル・コルビュジエであると同時にル・コルビュジエではなかった。自分自身とその男の関係を、どんな特殊な等号で結べばいいのか、まだ分かっていなかった。
「わたしが一人で住むための、宇宙ステーションを設計してほしい」
依頼は手紙で届いた。私を生み出したパリの建築思想研究所によるチェックを経て、私が住む湖畔の家のポストに投函されたのだ。湖に臨む中庭のベンチで、そっけないその文面を読んだ。手紙も、ベンチも、湖も、私が暮らす白い小さな家も、私自身の目も体躯も、何一つ物理的なものではなかった。私は生後2カ月間を、その仮想空間で一人、湖面を眺めて過ごしていたのだ。だからその依頼は、私にとって最初の外部世界との接触だった。
手紙が淡々と語る設計条件は、以下のようなものだった。
大柄の大人が一人、快適に定住できる小型宇宙ステーション。居住空間の目安は270㎥で、つまり直径8mの球の体積にほぼ等しい。加えて、医療機器などを積み込むスペースを100㎥確保する。設備運転や食糧生産に必要なエネルギーは太陽光発電で賄うが、再生しきれない資源の補給と軌道維持のために、1年に1度は物資補給船とランデブーする。
予定高度は440kmなので、軌道周期は約93分23秒。軌道傾斜角は97度。つまりこの宇宙ステーションは北極と南極の上空を一日に15~16回ずつ通過し、その過程ですべての大陸と海を真下に眺めることになる。地球観測衛星がよく採用する軌道だが、高度としては第4世代国際宇宙ステーションに近い。
頭の中で構造体を立ち上げ、軌道をシミュレートするのに、大した苦労はなかった。既存の宇宙ステーションを参考にした一般的な設計案なら、すぐにでも作りはじめられそうだった。しかし手紙の末尾に書かれたクライアントの“強い要望”が、私にそれをさせなかった。
「特に、以下の3点を心がけてもらいたい。第一に、依頼者の名は公表してはならない。第二に、人間を設計に関与させず、君ひとりで完遂すること。第三に、君はわたしに、建築家ル・コルビュジエの思考の真髄を示すこと」
第一の要望に則って、以降もクライアントの名は匿名とする。
第二の要望は言われるまでもなく、当時の私には協力できる人間は一人もいなかった。
第三の要望については、今でもまだ、応えられたのかどうか自信がない。
*
手紙を受け取った2日後、私は地球を見に行った。
白い砂紋のような雲と、のっぺりとした群青の海と、乾燥した苔のような陸地が、眼下でゆっくりと動いていた。まばたきをすると、都市活動や海水温やCO2排出を示す何層ものヒートマップが視界を覆い尽くした。
生まれて初めて見る本物の地球の姿は、想像以上のものではなかった。本物といっても、私には肉眼がないので、高度850kmを秒速8kmで周回する地球観測衛星の目を借りたのだった。移ろいゆく地球の表面は、生誕以来眺めてきた仮想の湖面とどこか似ていた。それは私の思考を引き出し投影する鏡だった。

クライアントの第三の要望がある以上、私はル・コルビュジエについて考えなければならなかった。1887年の10月にスイスで生まれ、1965年の8月に南フランスで死んだ男。鉄筋コンクリートを用いた工業的な建築生産方式の発達に呼応して、建物の新しい形態と思考法を追求した建築家。好んで黒縁の丸眼鏡をかけ、蝶ネクタイをつけ、雑誌や作品集を通じて近代建築というコンセプトを世界中にばらまいた宣伝屋。
すべて単なる記録ではなく、自分自身の記憶として、覚えがあることだった。眼鏡も洒落っ気だけでかけていたわけではない。時計職人の家に生まれたにもかかわらず、視力の悪化でその道が閉ざされたこと。だからこそ奮起して、時計とは正反対の巨大な対象――建築の道を志したこと。年表に染み込んだ青春の苦みと熱を、ありありと思い出せた。
だが無論、それは実体験ではなく夢の内容のようなものにすぎないと、私は重々承知してもいた。
――自分は、アーティフィテクトにすぎないのだから。
そう内心で呟くと、ひどく居心地の悪い気分が湧き上がった。100年前に死んだ人間に縛りつけられた自分の存在が、煩わしかった。
不満は八つ当たりのように地球にも及んだ。
人工衛星はすべて、地球に束縛されている。軌道に囚われているというだけでなく、ほとんどの衛星が目を――高性能のカメラを、センサを、小さな窓を――大地に向けている。反対側の宇宙に目を向ければ、地上からは到底見られない、くっきりと静止した星々の海が広がっているというのに。
私はそのとき、不自由を自覚していた。
歴史や地球のように巨大で鈍重な存在への反抗心をはっきりと感じ、自由を求めていた。
――自由か。
突如、その概念を核にして、記憶とコンセプトが凝集するのを感じた。
私の中でル・コルビュジエの野心が燃え上がった。
次の瞬間、私はフランスのイヴリーヌ県ポワシーの街角に一体の二足歩行ロボットを探り当て、クライアントが前払いしてくれた設計費でそれを買い取り、遠隔操作を確立していたのだった。
ロボットの目と手足を得た私は工事現場の足場を飛び降り、ポワシーの街なかを、歩行者をかわして走った。人間との物理的接近はそれが初めてだったのだが、そのときの私はただアイデアに突き動かされていて、感慨を覚える余裕はなかった。
建築思想研究所のIDを使って目的地の見学許可を取りつけると、身長より高い塀を飛び越え、木立を抜けた。広い芝生の中央に、白く角張った2階建ての住宅がぽつりと建っていた。ル・コルビュジエの作品の中で最も保存状態が良い建物の一つ、サヴォア邸だった。
図面も三次元モデルも頭の中にあったが、実物の輝きを見ると霊感は強まった。自分がすべきことは、ル・コルビュジエがサヴォア邸で大成したことと同じなのだと確信した。
それはすなわち、すべての壁を窓へと変えてしまうことだ。
ル・コルビュジエの設計思考の根幹には、建物が重力に抗う方法の転換があった。建物の重みを分厚い壁体ではなく最小本数の鉄筋コンクリート柱で支えることで、柱と床スラブ以外の部材を構造的には不要にしたのだ。
その瞬間から、上下の床の間に存在するすべてのものが、“窓”になった。つまり、人や光や風や熱を選択的に透過する境界となった。
サヴォア邸の窓は、2階をぐるりと水平に巡るサッシとガラスだけではない。
地上階の半分を占めるピロティ――柱に囲まれた吹き放ちの空間は、庭と家をゆるやかに分かつ“窓”だ。
テーブルや椅子やカーテンは、生活を分節する“窓”だ。
螺旋階段とスロープは上下移動を伴う“窓”だ。
屋上庭園をうねり囲む目隠し壁は、空と風景を切り取る“窓”だ。
そんな、絵画のように自由な境界の操作は、構造壁に支配された石や煉瓦の建築ではありえなかった。ル・コルビュジエは鉄筋コンクリートによって、建築を窓の芸術に変えた。
――いま、宇宙ステーションでも、こんな転換が可能だとしたら?
そんな問いが私の中で暴れていた。
購入したばかりの機械の身体をポワシーの街角に放り出すように隠し、私は仮想の湖畔の家に舞い戻った。200時間後に最初の設計案が完成するまで、私は手を止めず、波打つ湖面に目をやることすらしなかった。
*
「これがル・コルビュジエの回答か。こんな無理を押してでも新しい視界を開こうとするとは、たしかに彼らしいのかもしれない。これでいい。詳細設計を進めてほしい」
クライアントから返事が届いたのは、設計案の提出から3日後だった。
手紙を読み終えると、私は湖畔のベンチに座り、自分自身の設計案の三次元モデルをぼんやりと眺めて過ごした。
掌の上に浮かぶそれは、砂時計によく似ていた。涙滴型の2つの構造体を先端同士で連結し、3本の強靭な柱で補強していた。一方の涙滴は灰色の不透明で、逆にもう一方は大部分がガラスのように透明だった。ちょうど、砂が片方に落ちきりかけているときのように。
潜水艦のような従来の宇宙ステーションとは全く異なる発想で、設計した。分厚い金属外殻に小窓を開けただけのものではなかった。私の設計案の外殻は柔軟な7層の透光断熱膜で、遮光したい部分にだけ不透明膜を追加していた。それだけでは形状を保てないので、チタン合金の棒材とワイヤを組み合わせたテンセグリティ構造に膜をかぶせる形をとった。
要するに、私は宇宙ステーションの壁をすべて窓に変えたのだった。
地球に縛られていた眺望を解放し、宇宙の深い広がりを自由にぐるりと見渡せるようにした。その代償として、膜を支える柱とワイヤが内部に向かって突き出し、居住空間はジャングルジムのように分割されていた。
――クライアントは、本当は何を感じたのだろうか。
私が送付した三次元モデルは、修正指示や追加の要望を一つも伴わずに戻ってきた。閲覧記録を示すタイムスタンプを見るに、クライアントが細部までじっくりと確認したのは間違いない。その上で全面的に受け入れたのだ。その事実を私は喜ばなかった。激しく不吉な感情が膨れ上がるのを感じた。
その感情の根を上手く辿ることができなかった。アイデアを推し進めるために居住空間の一体性を損ねたことへの後悔というわけではない。そこは納得の上での決断だった。しかし、何か決定的なものを捉えそこねている気がしてならなかった。
居ても立ってもいられず、私はクライアントに手紙を書いた。
「直接お会いして、ご意見を伺うことはできませんか」
返事は翌日に来た。
「わたしは君の案に不足があるとは考えていない。どうかそのまま進めてほしい」
「不足があると、私が思うのです」と書いた。「私はあなたのことを何も知らない。住む人間を知らずにどんな家が作れるでしょうか」
「君の言葉は、ル・コルビュジエらしいとは感じられないな」と返事が来た。
クライアントの指摘の通りだ。私は不全感を脱するため、闇雲にもがいているだけだった。それでも、引き下がることはできなかった。そのプロジェクトは初めての仕事で、たった一つの仕事で、仕事が私のすべてだったのだから。
「私はたしかにル・コルビュジエの模造品にすぎません。しかしアーティフィテクトである前に、アーキテクトなのです。私を建築家と見込んで、本気で依頼をしていただきたい」
私は仮想の湖畔で返事を待ち続けた。
湖に青い夜が来た。桃色の朝が来た。セピアの夕暮れの後にまた夜の帳が降りて、朝日が上った。
それは意図せず訪れた、生まれて初めての休暇だった。仮想空間だとしても、湖畔には自然のリズムがあり、地球の自転と公転に起因する変化があった。
手紙は半月後に返ってきた。
「君の考えは分かった。わたしのもとを物理的に訪問することを許可する。自由に使える身体を用意して、ここまで来なさい」
書かれていた住所は、地上のどこにも存在しなかった。
それは高度600km、軌道傾斜角20度を周回する大型商用宇宙ステーション、「HP-13-a」の一角を示していた。
*
金属の身体をまとい、狭い記憶領域に自分自身を押し込んだ状態で、最も早く安く軌道上を訪ねる方法。それは、宇宙ステーションへの物資補給船に乗り込むことだった。
打ち上げの衝撃は大きかった。窓のない貨物室で、のしかかる巨大な加速度に私は耐えた。高所作業用ロボットの身体は古いながらもなかなか頑丈で助かった。ロケットはおそらく高度100kmあたりで、私を積載した補給船を切り離し、宙返りして地球に帰っていった。補給船は弾丸のように飛び、HP-13-aに追いついて噛み付くようにドッキングした。
私は物資コンテナとともに各種検査を受け、配送センターに放り出された。
数分かけて微小重力環境に慣れると、壁を蹴り、手すりを掴んで目的地を目指した。
事前に調べたところ、HP-13-aは特殊な宇宙ステーションだった。内部施設の詳細は非公開で、招待を受けた者にしか門を開かない。外部から遠隔操作できるロボットもほとんどない。だからこそ、私は重い身体で重力の井戸を這い登ってきたのだった。
指定された区画に辿り着き、そこが医療施設だと知ったとき、私は驚かなかった。
深海のように寂しい宇宙空間で独居するための家を欲しがるのは、どんな人物だろう。そう考えれば推測できないことではなかった。老いた人間か、病んだ人間か、その両方だ。
立方体の病室が上下左右に連なる空間を進み、一つのドアの認証をクリアした。
ドアが滑り開き、その先にクライアントが浮遊していた。
柔らかな寝間着の下にはやせ細った体躯が窺えた。棒きれのような、背の高い老女だった。部屋の奥には大きめの窓があり、地球が青い照明になっていた。
「もう、重力のある場所に戻ることは叶わないの」
眠っているのかと思ったが、彼女はふいに目を開いて、掠れた声で言った。
「宇宙に出れば身体は楽になる。でも筋肉は落ちて骨は粗になる。片道切符の入院だと初めから分かっていた。だからせめて、宇宙に終の棲家を作りたかった」
迎えの挨拶もなく、こちらをじっと注視して、彼女は淡々と話した。
私は立ち尽くしたまま、質の悪い喉のスピーカーで尋ねた。
「なぜ、私に依頼したのです。それほどル・コルビュジエに思い入れがあったのですか」
「いいえ。他人に死に場所を作ってもらうくらいなら、歴史の亡霊に頼んだほうがいいと思っただけ。しかし誤算だった。君は人間ではないが、生きている建築家だった」
初めてまともに対面した人間は、死にゆく人だった。いざとなると、私には気の利いたことは言えそうになかった。
私にできるのは設計だけだ。だから、それを貫こうと思った。
「しばらく、この部屋の隅にいてもいいですか」と私は訊いた。「あなたの暮らしを見ながら、設計を考え直したいのです」
その願いは受け入れられた。
私はそれから半月の間、病室の隅の家具になった。空間の一部になって、クライアントの過ごす日々を眺めた。クライアントとともに窓外の景色を眺めた。
彼女の一日を支配するものは、睡眠だった。彼女はかなりの注意を払って、睡眠と覚醒のサイクルを24時間弱の周期に保っていた。眠るために起き、起きるために眠る。その合間に窓の外を眺める。それが彼女の心身の安らぎだった。
一方、窓外は目まぐるしかった。HP-13-aの軌道周期は100分弱。だから、およそ50分ごとに地球の昼夜は入れ替わるのだった。
その大きすぎるずれを隠すため、病室の照明と窓を覆うカーテンは忙しなく自動調整されていた。明滅と開閉を繰り返す環境が彼女にかすかなストレスを与え続けているのだと、私はあるとき気づいた。その発見は、10日で確信に育った。
私の設計案に欠けていたもの。それは時間だった。
地上で生まれた動物の身体におおらかに刻み込まれた、地球の自転周期だ。
私が理解はできても、実感はできない死角だった。何の因果か、砂時計にまで辿り着いたのに、あと一歩の踏み込みが足りていなかった。
私がクライアントのために設計したいもの。人が宇宙に住むための機械。
それは、人の一日を司る時計のような家だ。
私は清々しい悔しさを噛み締めた。答えは最初からそばにあったのだ。ル・コルビュジエの出発点は時計職人だったのだから。
*
「君に頼んで良かった」
クライアントからの最後の手紙には、そう書いてあった。
第2案を作り上げたのは、HP-13-aから仮想の湖畔に舞い戻った17日後のことだ。
不眠不休なら200時間程度で仕上げられたはずだが、私はたとえ仮想のものでも、一日のサイクルを感じながら設計すべきだと心に決めていた。それは私の作品に住むクライアントが経験するものなのだから。
いつからか、設計の進捗を報告しても、クライアントは内容を確認しなくなった。毎回、ただ一言、任せるとだけ返ってきた。私は悲観はしなかった。詳細設計に深く没頭した。並行して、地上の素材工場を複数押さえ、軌道上への建材打ち上げと組み立ての段取りを進めた。物理的な現実が、私の思考になかなか追いついてこないことに苛立った。それでも辛抱して一刻も早い竣工を目指した。
最後の手紙が来たのは、建設期間のちょうど半ば、宇宙ステーションの大まかな形が出来上がった頃のことだった。
その手紙の中で、クライアントは私を初めてシャルルと呼んだ。
それを見た瞬間に、私は何を覚悟すべきかを悟った。
「今日、パリの建築思想研究所に連絡を取った。君は人工知能なので所有権は持たないが、研究所への寄付という形で、実質的に君に財産を贈与できるよう取り計らってくれるそうだ。財産といっても、君が今まさに建ててくれている終の棲家くらいのものだけれど。だから、それはいずれ君の家になる。最初の作品が自邸とは、いかにも建築家だね」
それから数日が経って、手紙ではなく研究所の職員によって、クライアントの逝去が知らされた。
*
以上が私の初仕事の経緯であり、私の自宅が誕生した経緯である。
以後30年、私はここに住み続けている。設計の仕事場は相変わらず仮想の湖畔にあるが、それ以外の時間には機械の身体に入って、ここで地球や宇宙を眺めて過ごす。ときにはクライアントを迎え入れることもある。
この独居用宇宙ステーションは、本当に時計の形をしている。
巨大な機械式時計だ。円盤の片面は金属外殻で、もう片面はガラスのような多重透光断熱膜に覆われている。その間の文字盤と機構にあたる場所が、居住空間。半分がすべて窓という点は、最初の設計案と同様だ。
この家は常に、地球の昼夜の境界線をなぞるように周回している。そして、地球の自転と同じ速さで、この家も自転している。
家の半分を占める窓の向こうを、巨大な青い光源と、眩く鋭い光源が、ゆっくりと巡っていく。時計が地球と太陽の両方に背面を向ける時間帯には、視界は精細な星の群れに満たされる。そしてまた、家の縁から2つの夜明けがやってくる。
私はその周期の中で、ときたま、人間の真似をして眠ってみたりもする。
第1話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。書籍『Holz Bau(ホルツ・バウ)』や『ex-dreams』のイラストも大きな話題に(参考記事はこちら)
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。