「7日間ブックカバー・チャレンジ」にあやかって、建築家の言葉を1日1人、計7人取り上げていく。3人目は、菊竹清訓(きくたけきよのり、1928~2011年)だ。私(宮沢洋)が日経アーキテクチュア在籍時に関わった書籍や特集記事などから言葉を拾い出していく。

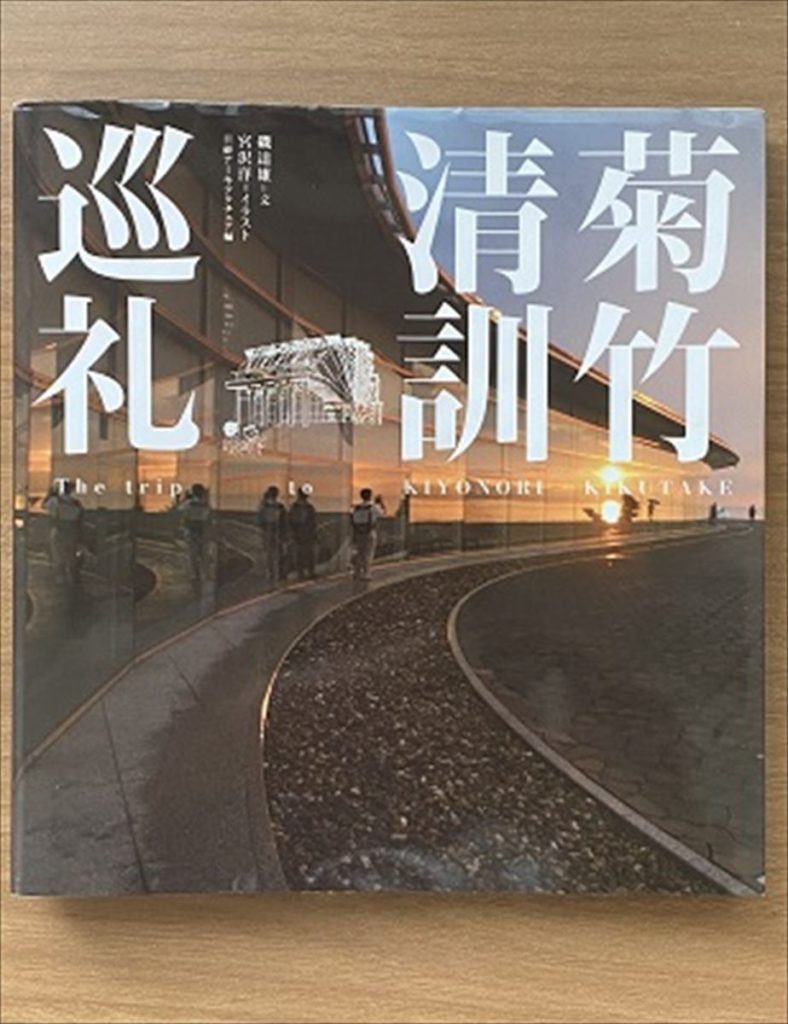
もともと文系出身の私が、今のように建築好きになったのには、菊竹と安藤忠雄氏の建築の影響が大きい。特に菊竹については、亡くなった1年後に「菊竹清訓巡礼」という本(磯達雄との共著)を出すほどの、筋金入りの菊竹ファンだ。菊竹1人の名言だけで7日間連載できるくらいネタはあるのだが、今回は「技術」に絞って拾い出してみた。
菊竹の有名な方法論、「か・かた・かたち」の2番目が「技術」であるということもあるが(1番目は「構想」、3番目は「形態」)、それに加えて、今回のコロナ禍により、施工の省人化や材料の地産地消などの技術革新が進むと想像されるからだ。
まずは菊竹ではなく、建築家の内藤廣氏の言葉から始めたい。菊竹といえば、「菊竹スクール」の名が知れわたるほど、多くの建築家を輩出している。教え子の1人である内藤氏は、菊竹の下で弟子が多く育つ理由をこんなふうに語っている。
「菊竹さんは天才。間近にいれば、かなわないと分かる。そんな人を目の前にしたとき、自分はどうしたらいいかと考える。僕が菊竹さんに学んだのは、技術の進化が建築を変えていくという考え方。その部分については、強く受け継いでいると思う」(日経アーキテクチュア2012年12月25日号・特別リポート「菊竹清訓、偉大なる反面教師」より引用)
内藤氏が菊竹事務所に在籍したのは1979年~81年の2年ほどだが、同氏は、菊竹の発想力を示すこんなやりとりが忘れられないという。担当プロジェクトの打ち合わせのとき、菊竹がこう言った。
「君、その柱は付けたいのか、付けたくないのか」
構造家の松井源吾の事務所で検討した結果、この太さになったと内藤氏が説明すると、菊竹はこう言う。
「その柱をタングステンにしたらどうだ? タングステンにしたら、断面は4分の1で済むじゃないか」(NA建築家シリーズ「内藤廣」/2011年/日経BP社刊より引用)
タングステンは非常に硬く重い金属で、確かに柱に使用したら細くできそうだが、融点は摂氏3380℃と、金属の中で最も高い。だから、電熱器にも使われるわけだが、製造・加工が難しい。菊竹もそうしたことを知ったうえで、その可能性を検討したのかを問うているのであろう。所員は大変だ…。
要求のハードルが高い一方で、その提案が優れたものであれば、相手の年齢や実績は気にしなかった。例えば、照明デザイナーの石井幹子氏は、ドイツから帰国したばかりで仕事が何もない頃、挨拶に訪れた菊竹事務所で、菊竹からいきなりこう言われて驚いた。
「あなたならこの空間の照明をどうするか」(NA建築家シリーズ「内藤廣」/2011年/日経BP社刊より引用)
模型を手にした菊竹に、石井氏がいくつかのアイデアを語ると、その場で照明担当を任された。萩市民館(1968年)の「蜘蛛の巣」のような照明はそうして生まれた。

ときには、小学生の子どもにも聞いた。菊竹の長女でデザイナーの菊竹雪氏は、父からしばしばこんな質問を受けた。
「こういうコンペをやっているんだけど、どう思う?」(「菊竹清訓巡礼」/2012年/日経BP社刊より引用)
「父は、子ども、大人という意識が全くなかったと思います。(中略)純粋に子どもの意見が聞きたかったんだと思います」と述懐する。
もちろん、子どもから即採用のアイデアが出るとは思っていなかっただろう。答えそのものではなく、子どもの思いもよらぬ視点をとおして、発想の殻を破ることを期待していたのではないか。
「技術を追求する」というと、「従来技術の最先端」を追うことが頭に浮かぶ。しかし菊竹にとってそれは選択肢の1つに過ぎず、全くゼロから新たな可能性を模索することが技術であり、設計であった。今後問われるであろう「AI(人工知能)にできないクリエーション」というのは、そういうものなのではないか。働き方改革と逆行するかもしれないが…。
「今までの造形感覚では判断できない」
この記事でも「建築家」という表現を使ってきたが、実は菊竹自身は、「建築家」という言葉よりも、日本特有の「建築士」に重きを置いていた。日本建築士会連合会会長も務めた。
その日本建築士会連合会会長時代の日経アーキテクチュアのインタビュー(2000年)が、「設計と技術」に関して、今載せてもそのまま通用するほど面白い。コメントをいくつか抜き出してみる。
「日本の建築士にはアーキテクトも入っているし、エンジニアも入っている。ゼネコンの人も入っている。非常に幅広い、要するに環境づくりの専門家として、建築士はくくられているわけです。こうした建築士のような専門家集団が、実は次の21世紀に向かって、重大な環境革命で重要な役割を持つことになると思うんです」
「今までの造形の感覚では、いいか悪いかの判断さえつかなくなってきた」
「これからは構造を含めて、様々なエンジニアリングの知識を持っていなければいけない。アートだけではダメですというのが私の考え方です」
「構造はもちろん、設備、情報通信、センサーなどのハイテク技術がないと環境はつくれない状況です。我々、建築士はそうした時代の先頭を走っている」
(いずれも「建築家という生き方」2001年/日経BP社刊より引用)
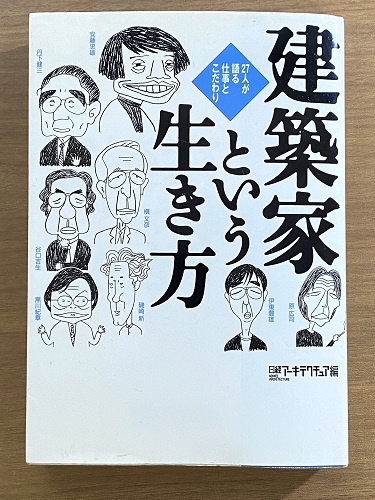
2000年の時点で、情報通信、センサーが建築を変える、と言っているのがすごい。このとき、菊竹は72歳。
今回の記事の最後は、自分も建築界を担う一員として、自戒の意味を込めてこの問いで締めたい。
「(欧米の)大部分の建築家は社会的な動きの中から次第に浮いてきているわけです。大変なことで、これは日本だって同じです。日本の政財界のトップに立っている人が、建築家をどう見ているか、どの程度信用されているか。私は同じように相当、変わってきていると思います」(「建築家という生き方」2001年/日経BP社刊より引用)
◆参考文献
日経アーキテクチュア2012年12月25日号・特別リポート「菊竹清訓、偉大なる反面教師」/日経BP社刊/電子版の記事(有料)はこちら
「菊竹清訓巡礼」/2012年/日経BP社刊/紙版は出版社在庫なし、Kindle版はこちら
「建築家という生き方」2001年/日経BP社刊/発行時定価1800円+税/出版社在庫なし、中古本はアマゾンなど

▼初回から読む
宮脇檀(2020年5月11日公開)
▼次の回を読む
吉村順三(2020年5月18日公開)
