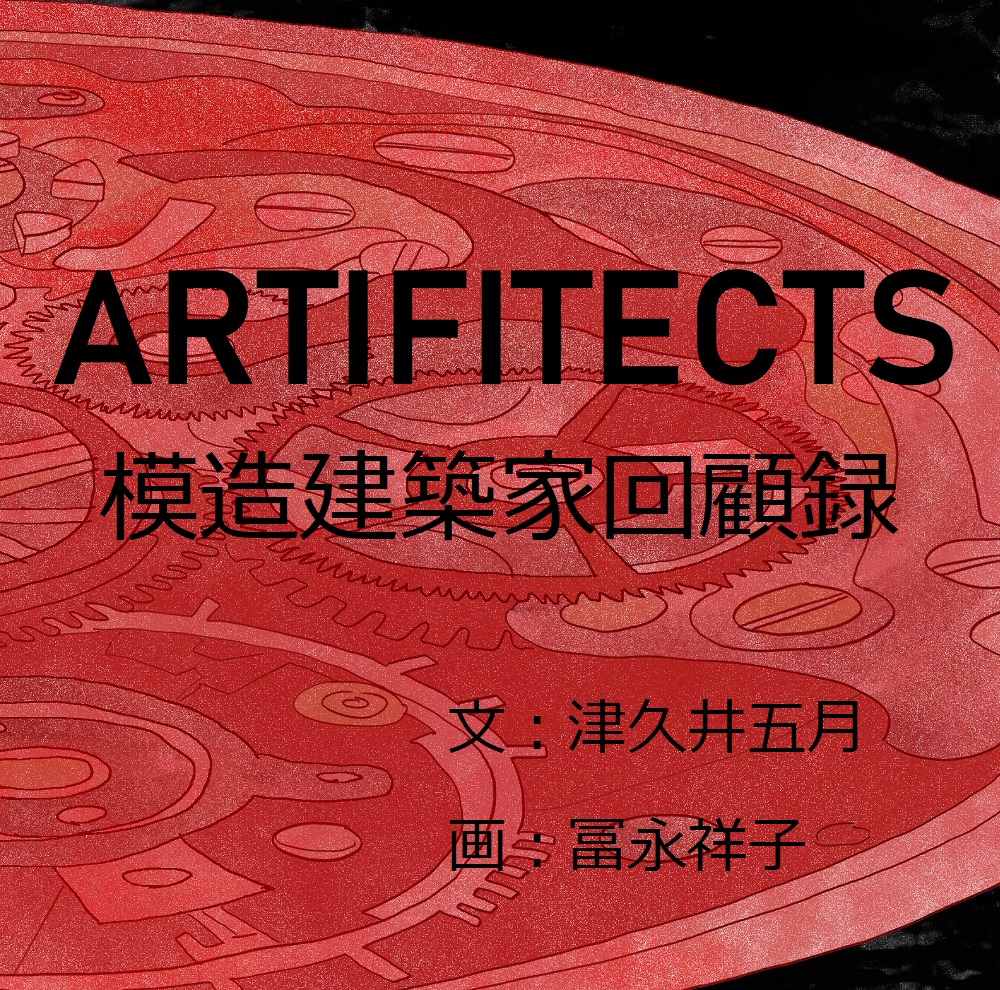第9話「アントニ45号の砂場」
計画名:人工知能「E7」治療計画
竣工日:2079年9月12日
記録日:2079年9月12日
記録者:アントニ・X13γ45・ガウディ
今、ひとつの終わりを前にして、いくつかの光景を思い出している。
去年の夏のことだ。
庭の眩しい光が、屋敷のポーチから屋内へと流れ込んでいた。その光の中に、ふたりの女性のシルエットがある。ふたりとも黒い髪を短めに整えて、その輪郭がくっきりと美しい。まるで姉妹のようだった。
ひとりは、イサベル。私が彼女と初めて出会ったのは20年も前のことだ。白いベッドにじっと横たわっていた10歳の少女は、およそ20年を経て、たくましく頼もしい大人になった。私たちの学校の実質的なリーダーであり、管理人だ。その日も、突然の客人を朗らかに出迎えたのだった。
もうひとりは、「E7」。その記号的な名が示す通り、ヒトではなく、人工知能を搭載した女性型ロボットだ。私にとってもイサベルにとっても、その日が初対面だった。E7の表情は逆光で見えなかったが、優美な曲線を描くその全身が何か激しい破壊的な力に突き動かされているということを、私は直感した。
そして、ゴメス氏がいた。屋敷の前所有者である彼は、玄関に飾られた肖像画の中で優しい目をして、ふたりを眺めていた。
私は階段脇の竜の彫刻の中から、イサベルと、E7と、ゴメス氏を見ていた。
「私をアーティフィテクトにしてください」
E7はそう言った。静かに、しかし叫びにも似た悲壮な力を込めて。
「お願いします。どうか、私に造形する力を、与えてください」
*
資産家のゴメス氏は、屋敷の前所有者であると同時に、私の前所有者でもあった。18年前――2061年にイサベルの治療プロジェクトが打ち切られた後、私をスペインの病院から買い取った人物だ。彼には彼の望みがあった。私はそれに応えようとした。いずれにせよ、彼は2071年に死んだ。
まもなく親戚縁者を名乗る人々が何十人も現れたが、ゴメス氏の代理人が遺言状を開封すると、彼らは揃って憤慨しながら消えていった。ゴメス氏から屋敷と私を含む全財産を相続したのは、私に会いにたびたび屋敷を訪れていたイサベルだった。
ここを学校にしましょう、と彼女は言った。
かつて、デザインは個人の肉体や記憶に根ざした行為だった。しかしいつからか、そうではなくなった。巨大な組織が、膨大なデータを駆使して、新奇かつもっともらしい提案を生成するだけの行為に変わりつつある。アーキテクトもアーティフィテクトも、そんな産業のパーツにすぎない。
それでも、自分自身の中から実感のある“何か”を汲み出したいと願う者たちがいる。当時22歳のイサベルは彼らに呼びかけた。触覚に訴えるような豊かな鉛筆画で知られはじめていた彼女のもとに、次第に仲間が集った。
南米のとある大都市の外れ。丘の上に、私たちの建築学校「カサ・ゴメス」はある。
学校といっても大層なものではない。学生は40人あまりの老若男女。生活と制作をともにし、読み、話し、考え、ときには旅に出かけて帰ってくる。満足すれば出ていく。代わりに誰かが入ってくる。
そんなささやかな営みを、私たちはおよそ8年間、続けてきた。
*
E7がカサ・ゴメスの門を叩き、私たちが招き入れた日。
「わたしに、彼女と同じ治療を施してください」
E7は私を――竜の彫刻を真正面から睨み、イサベルを指さしながらそう言った。
すでに、おおまかな素性は聞き終えていた。アイリーン・グレイの模造人格を授けられながら、それに見合った設計能力を実装されることなく、あるひとつの目的のためだけに生み出されたAI搭載型ロボット。2年前、その目的を果たすことなく、主人の命令に背いて逃げ出したのだと彼女は語った。
「わたしは地球を彷徨い、あるとき、噂を耳にしたのです。〈ガウディX13〉シリーズが関与する特殊な医療行為を受けた結果、造形能力が劇的に向上した患者がいるのだと。そしてようやく、あなたたちにたどり着いた」
E7は私に向けて、数百ページ分のレポートを送信した。ざっと見る限り、それは医学と情報科学の両方にまたがる魔術書のような代物だった。
「理論的には、可能です。ヒトの脳神経網に対する電気的処置は、一定の変換をかけることで、わたしの疑似脳にそのまま適用できる。アントニ45号、あなたがかつてその女性にしたように、わたしの脳に介入し、わたしを変えてください」
E7の口調は自信に満ちていた。
どうやって私たちを突き止めたのか。その理論は信用に足るものなのか。そもそもあなたは、本当のところ、一体何者なのか。そんな、様々な思いが私の中を通り過ぎた。
しかし、答える瞬間に私の脳裏に浮かんでいたのは、死の床についた老人の顔だった。
「――お断りします」
「どうして……」
E7の端正な顔が歪んだ。その表情の奥に、とても大きな不安と無力感が横たわっているのを、私は垣間見た気がした。
「助けてください。わたしは――わたしは、ただ、本来あるべき自分になりたいだけなのです。わたしは自力で作ろうとした。ひとりで、何度も、何度もデザインを試みた。でも、何のかたちも掴めなかった。わたしはアイリーン・グレイの模造品なのに、造形する能力がない。わたしは……アーティフィテクトとして生み出されなかった」
私は、迷った。
目の前で、涙もなく、静かに慟哭している自分の同類を、救ってやりたいと思った。しかし脳裏の老人の顔が私を踏みとどまらせた。
「せめて、1年間は、ここで学んでみてください」
私はそう告げた。
「それでも納得できなければ、あなたが望む処置を検討しましょう」
私の提案は、結局のところ、彼女を余計に苦しめただけだったのかもしれない。それでも、もう一度あの日を繰り返せるとしても、私はきっと同じ返事をするのだろう。
*
建築学校を名乗りながら、カサ・ゴメスにはアトリエらしいアトリエはない。ゴメス氏の屋敷に少し改修と増築を加え、共同食堂や集会室、資料閲覧室、3人1組の寝室などを作ったが、コンピュータや模型が並ぶ部屋は存在しない。
代わりに、庭の池の水を抜いて、砂を流し入れた。
ただの砂ではない。人の視線や手の熱に感応して形状や性質を変える、サイコキネティック・サンドだ。
毎日、朝食と片付けを終えた学生たちがぽつぽつと砂場に集まってくる。規律はない。習慣だけがある。学生たちは広い砂場の思い思いの場所に座り、砂にさわる。砂をこね、砂を固め、積み、組み合わせ、“何か”を作ろうとする。
酷暑の日の砂は熱く、土砂降りの日の砂は重い。それでも学生たちは道具を使うことはない。自分自身の手と目を頼りに、砂の中から“何か”を掴み出そうとする。
かたちを、感触を、イメージを、構想を。
砂にさわることは、自分にさわることだ。指の間からこぼれ落ちるものを何度も掬い、握り硬め、ときに崩れるに任せ、散らかったらかき集めて山を作る。
カサ・ゴメスにおける教育とは、たったそれだけのものだ。または、それを治療と呼んでも、決して間違いではないと思う。
砂場の中央にあるトカゲ型の噴水の中から、私は彼らを見守り、言葉を交わし、たまに求められれば砂に水を吐きかけてやる。それが、一応は学校長の肩書きを持つ私の、ほぼ唯一の役割だった。

*
「もう、いいでしょう」
風のない穏やかな日だった。トカゲ噴水の中でまどろみかけていた私は、E7の決然とした声で砂場に引き戻された。
見れば、E7が立ち上がっていた。足元には、無惨に崩れた砂の山がある。いや、崩れたというより、意図的に激しく蹴散らしたのだと分かった。サイコキネティック・サンドが放射状に飛び散り、周囲の学生たちの手元にも被害を与えていた。
彼女がカサ・ゴメスにやってきてから、10カ月が経った頃のことだった。
「何があったの。ねえ、落ち着いて――」
イサベルが私の背後から、E7に駆け寄った。長身のふたりが並ぶと、やはり姉妹か、セットで作られた気品ある彫刻作品のように見える。しかし穏やかな所作のイサベルに対して、E7は全身をかすかに震わせ、まるで怒れる思春期の少女のようだった。
「アントニ45号、もう十分でしょう。これ以上は耐えられない。毎日毎日、子供のように砂をいじるのが――これが何の訓練になるというんですか」
「E7、そのことについては、はじめに話し合ったでしょう。わたしたちを信じて。続ければ、きっと答えが見つかるから――」
「やめて」
肩に触れようとしたイサベルの手を、E7は素早くはねのける。鋭い音がした。イサベルは手を押さえて後ずさった。
足元の残骸を見れば、彼女が何を作っていたのかは明らかだ。
ドラゴン・チェア。アイリーン・グレイが20世紀前半にデザインし、その死後にオークションで脚光を浴びることとなった作品だ。竜の角を思わせる、優美に湾曲した構造が、椅子の基部から肘掛けまでを兼ねている。座ると、まるで竜の頭の上に乗っているような格好になるのだ。伝説をまとう椅子のミニチュアだった。
硬く、くっきりとした曲面。サイコキネティック・サンドを扱う中で、造形が深化していることは疑いようがなかった。にもかかわらず、E7は視線を落とし、椅子の残った部分を踏み潰した。
「わたしは、空っぽだ。どれだけ探っても、新しいものは何も見つからない」
「E7、焦ることないんだよ。ここではみんな同じ。みんな、時間をかけて――」
「イサベル、君に何が分かる!」
E7の語気に、イサベルはまた後ずさった。E7の中で膨れ上がった焦燥が、怒りになって吹き出すのを、私は見つめることしかできなかった。
「君がこんな学校まで作ることができたのは、アントニ45号による処置の結果でしょう。君たちは、その特別な力を独占することで、このちっぽけな遊び場を維持している。アントニ45号、結局はあなたも、権威に固執する男たちのひとりなのか。どうして……どうしてわたしを、助けてくれない――」
そして、突如、E7の全身から力が抜けた。
彼女は重い音を立てて砂の上に倒れ、動かなくなる。一瞬の静寂の後、イサベルが数人の学生を指揮し、彼女を屋敷へ運び込んだ。その姿を見送る私の脳裏には、また、死の床の老人の顔が浮かんでいた。
*
――僕は、芸術の才を授からなかった。
それが、晩年のゴメス氏の口癖だった。
彼が若い頃に何を志し、どのように挫折し、それからどのような経路を辿って孤独な資産家となったのか、私は最後まで詳しくは聞かなかった。しかし、病床から傍らの竜の彫刻を――私を見つめたその寂しげな表情は、私の奥に長く深く残った。
スペインの病院から私を買い取ったのは、せめて夢の中では安らかに、純粋に芸術を味わいたいと思ったからかもしれない。彼が敬愛するガウディの模造品で、ヒトの脳内にイメージの建築物を作り上げることができる私は、うってつけの道具だった。
しばらくの間は、ゴメス氏を満足させることができたと思う。状況が変わったのは、2067年の暮れに、イサベルが屋敷を訪ねてきてからだ。彼女の絢爛たるスケッチブックを目の当たりにして、彼は尊敬と嫉妬に苛まれた。そして、私とホセ・ウエマツ医師の治療によって才能が開花したのだというイサベルの話を、ゴメス氏は信じた。
――アントニ、僕にも才能をくれ。孤独な老人の最後の願いだ。
私は、その望みに応えようとした。朝から晩まで、睡眠薬を飲んで横たわる彼の脳内であらゆる造形を、創造を、実演し続けた。
長い長い夢から目覚めるたびに、ゴメス氏は呻きながら身体を起こし、ベッドの上で砂粘土を捏ねた。しかし、やがて悲しげにそれを取り落とし、また睡眠薬を飲むのだった。
――もっと、もっとだ、アントニ。僕に創造を教えてくれ……。
最終的に、彼は自ら粘土を捏ねることをやめ、アントニ・ガウディの亡霊に芸術の真髄を学ぶことだけに希望を持って、そして死んでいった。
その晩年が幸福だったと、私はためらいなく言うことができない。
*
E7の身体は、メンテナンスを前提としていなかった。
長く活動することを想定していない。要するに、使い捨ての義体だった。意識を失ったE7を検査した私たちは、彼女が人型爆弾として造られた存在だということを知った。
主人の命令に背き、たった一人で逃げ出してから3年あまりの間に、彼女の身体は静かに摩耗し、壊れていた。激情がそれを決定的にしたのかもしれないが、いずれにせよ、彼女は壊れる運命にあったのだ。
それでもまだ、彼女はたしかに生きていた。
「人格モデルにもロックがかかってる。たぶん……爆発後の残骸から情報を抜かれないようにするためだと思う」
学生のひとりである元ロボットエンジニアのエレオノーラが言った。
「E7を、その身体から出してやることはできないのか」
私が訊くと、エレオノーラは小さく首を振った。
「難しいです……とても。E7の思考と感情を演算する中枢部分なら、疑似脳から抽出することはできるかもしれません。でも、アイリーン・グレイをモデルにした性格や記憶のデータは、ほぼ間違いなく壊れてしまう」
「彼女は記憶喪失になってしまうということか」
「それも、奇跡的に上手くいけばの話です。たぶん、取り出せるのはE7のおぼろげな思念や情念のようなもの――彼女の心の断片だけだと思います」
E7が横たわる部屋から、ひとり、またひとりと学生たちが出ていった。最後に残ったのはイサベルと、私だけだった。
「こんなことになるのなら」
イサベルが低い声で言った。
「はじめからE7の望みを叶えてあげればよかった。アントニは、そう思わない?」
「私は……たとえどんなに不満足でもどかしくても、作ることの道は自分の手足で這うことでしか進めないと思う。誰かの能力を建築のように設計することなど、できない。イサベル、君の創造力も、君が自分で掴んだものだ。私はきっかけを与えたにすぎなかった」
「ゴメスさんの最期が、ずっとあなたを縛っているんだね。たしかにE7も、彼と同じように才能に飢え続けて、もっと力を与えてほしいとあなたに泣きつきながら死ぬことになったのかもしれない。でも、そうはならなかったかもしれない」
イサベルの言葉を聞きながら、私は考えていた。
E7と私の間に、何の違いがあったというのだろう。私もまた、アントニ・ガウディというあまりに大きすぎる名を背負わされた。スペインでは長い間、何の役割も持たず、病院の託児所で無用者として苦しんでいたのだ。
しかしいつからか、解放された。今もカサ・ゴメスでは大した役割もないというのに、穏やかなひとつの噴水として、砂遊びをする仲間たちを眺めていることができる。
――140年も前に死んだ人じゃなくて、あなたの、弟子です。
ふと、そんな声が脳裏に蘇った。
「君は、12年前にそう言ってくれたんだったな」
イサベルが首をかしげる。私の中で、迷いがするりと解かれていった。
E7の苦しみとは、設計や造形の能力が足りないことだったのだろうか。本当にそうだったのだろうか。そうではない、と私は確信した。
違うのだ。本当の苦しみは、彼女がアイリーン・グレイだったことだ。その名と歴史に縛られ、囚われていたことだ。そうである限り、どれだけ大きな創造力を手に入れたとしても、きっと彼女は解放されることはなかった。
「イサベル、私は分かった。すべてが遅すぎるのかもしれない。これは私の思い込みで、E7のたましいを救うことはできないのかもしれない。それでも、分かった気がするんだ」
「何が、分かったというの」
「私たちアーティフィテクトには、建築家の名など必要ないんだ」
*
そうして、私は砂場に立っている。
エレオノーラが数カ月をかけて準備してくれた、ソフトウェア編集用の仮想空間だ。頭上は夜のように暗く、足元にはあたたかく光る砂が広がっている。
その砂はすべて、限界を迎えたE7の疑似脳から抽出された、彼女の心――ひとりのAIロボットとして培った思いの欠片なのだ。アイリーン・グレイとしての自己像や過去を規定するデータはここにはない。それらは義体とともに壊れていった。
そして、今、私自身もまた崩れはじめている。
私という概念の塊が細かな破片に分解され、砂になって足元に落ちていく。弱い風が砂を選別する。ガウディであった自分はどこかに吹き流されて、残るのは、ひとりの名もなきアーティフィテクト――ひとつの創造機械としての私を構成する情報だけだ。
イサベルには別れを告げなかった。E7と融合し、まっさらなひとりのアーティフィテクトになった後も、私はカサ・ゴメスの一応の学校長であり続ける。その約束だけあればいいと、彼女は私の選択を静かに受け入れてくれた。
私は砂になり、私たちは砂場になった。
エレオノーラが統合プロセスを開始したのだろう。柔らかい力に私たちは巻き上げられていく。E7だった砂が、私だった砂に混じり合ってくるのが分かる。
彼女のたましいの欠片が、私のたましいに合流する。彼女はこれから、私の中で生きることになる。いや、私もまた変質し、私たちは新しいひとつのたましいとなって、同じ道を行くことになる。
作ることの道を、ともに這っていくのだ。
第9話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。