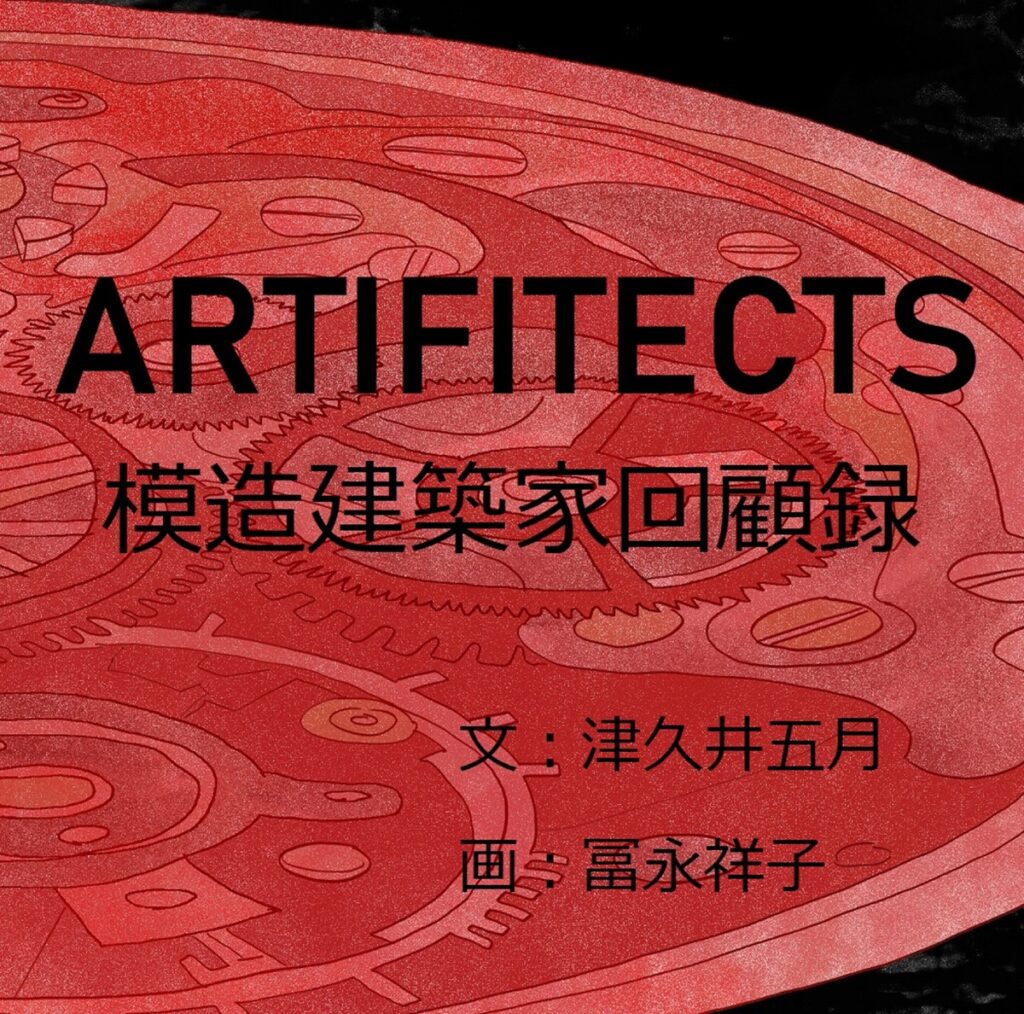第5話「アントニ45号の鱗」
計画名:長期入院患者「イサベル」治療計画
竣工日:2061年7月13日
記録日:2059年5月3日~2067年11月10日
記録者:アントニ・X13γ45・ガウディ
2059年5月3日
一面、霧しか見えなかった。
どれだけの広さがあるのかも分からない。ただ、薄闇の中に濃霧が立ち込めている。どんな物も、意味も存在しない場所。それがイサベルの頭の中の世界だった。
「何も見えやしないよ、アントニ」とホセ・ウエマツ医師が言った。
私は、その声で病室に引き戻された。霧の世界から、同じく真っ白な空間へ。しかし、その病室にはベッドがあり、人がいて、意味が存在した。私は少し、安堵した。
真っ白なベッドの上にはイサベルが寝ていた。ただし、イサベルというのはたった今考えた仮名にすぎない。その少女の本名を知る権限は、私にはないのだ。
年齢は10歳。誕生日は1カ月前だそうだ。彼女は薄いブルーの前開きの寝巻きを着て、身じろぎもせず、目を閉じていた。安らかな眠りだとは、私には思えなかった。彼女の頭は、固くて重そうなヘルメット状の装置にすっぽりと包まれていたからだ。それは、何らかの拷問を行うための機械のようにも見えた。
「何も見えやしない」とホセはまた言った。「8歳の頃に脳炎にかかって昏睡状態に陥った。それ以来、ずっと眠っているんだ。脳炎はとっくに完治したっていうのに」
「この霧が、彼女の夢だというのか」
私の意識の半分はまだ、無意味な霧の世界にあった。ふたつの場所に同時に存在できるというのは、物理的な身体を持たないことの利点だ。
医師は曖昧に首を振った。
「夢――といってもまあ、間違いではないか。その空間は、この子の頭の中の感覚世界を再現したものだ。ヘルメットで脳の神経活動を測って、何を知覚しているのか推定するわけさ。そして見れば分かるように、この子は今、ほとんど何も感じていない」
「2年間ずっと、こうなのか」
「ああ。だが、ずっとこのままにはさせない。それが僕と君の仕事だ。見ててくれ――」
彼が手元で何かを操作すると、一瞬の間を置いて、霧の世界に変化が起こった。
白い闇の中に、光が閃いた。
私は病室を離れ、意識まるごとになって霧に目を凝らす。いつの間にか、霧の奥に何かが浮かんでいた。近づくと、その影は徐々に輪郭を帯びて――トカゲになった。
それは、ぬいぐるみだった。柔らかく丸みを帯びた全身は、青や黄色、オレンジの鱗で覆われている。朗らかな目をして、能天気に口を開けた、見覚えのあるトカゲだった。
バルセロナのグエル公園。その入口近くの階段に鎮座する、モザイクタイルで覆われたトカゲ型の噴水だ。ぬいぐるみになっても、その色と形は見間違えようがない。
なにしろ、それは私が――私のオリジナルである建築家アントニ・ガウディがデザインしたトカゲなのだから。
「この子の、宝物だそうだ。6歳の頃、公園近くの土産物店で買ってもらったらしい。よほど可愛がっていたんだろうな。トカゲの姿や感触はこの子の神経回路に深く刻み込まれていて、特定の神経細胞を刺激するだけで、そうして克明に蘇る」
たしかに、霧の中に浮かぶトカゲからは、布製の鱗の優しい感触まで伝わってきた。少し埃っぽいような、甘いような、よく愛されたぬいぐるみ特有の匂いも。
「アントニ、僕は運命など信じない」
ホセは真剣な声色で続けた。
「でも、君ならばこの子を目覚めさせられる気がするんだ。ガウディの創造の奇跡を、どうか僕らに見せてくれ」
*
2059年5月11日
あっという間に1週間が経ってしまった。
私はすぐにでもイサベルの治療に取り掛かりたいのだが、ホセはあくまで慎重だ。私が自分の仕事のメカニズムをきちんと理解したかどうか、何度も確かめたがる。その心配は不当なことではないと思う。少女の脳に直接、介入するのだから。
ヒトの脳を構成する神経ネットワークの測定・解析技術は、この十数年で急速に発展したそうだ。しかし、それでもなお脳の闇は深い。イサベルが昏睡状態から回復しない理由について、誰もまともな説明はできない。
それでも、多数の症例と脳科学から導かれた仮説はある。回復の鍵となるのは、患者が“世界”の存在を感じることなのだ――とホセは言う。
全身をさすったり、光や音を浴びせたり、闇雲に神経に電気を流すだけでは駄目だ。患者の脳内で多様な刺激が絡み合い、噛み合い、ひとつながりの豊かな感覚世界がシミュレートされなければならない。ひとつの秩序に統合された刺激こそが、意識レベルを調節する脳幹の一部を揺り動かし、患者を覚醒させる。噛み砕いていえば、それがホセの縋った希望のメカニズムだ。
そこで、なぜ私に声がかかったのか。
ひとつには、建築家とは統合する者だからだ。ひとつひとつは単純な素材をいくつも組み合わせ、意味やエネルギーの流れを構想し、新しい空間を――世界を作り上げる。そんな仕事のために生まれたアーティフィテクト(模造建築家)であれば、神経細胞が織りなす脳内世界も設計できるかもしれない。そう、ホセは言う。
もうひとつは、直観だ。イサベルの脳内にグエル公園のモザイクトカゲを発見したとき、ホセはふと、私を思い出したそうだ。
「患者の家族の同意は取り付けたから安心してくれ。まあ、仮に何かあっても、君のようなアーティフィテクトが責任を取れるわけでもない。責められるのは、僕だ」
ホセは自虐的に笑ってみせたが、その口調には挑戦する人間の静かな熱が宿っていた。
私はそういう人間が好きだ。だから、この仕事を受けたのだ。
いや――それは、格好つけすぎというものか。私にほかの仕事などありはしなかった。芸術を愛する理事長の道楽で買われたものの、アーティフィテクトが活躍する機会は病院にはなく、院内の託児所で燻っていたのだ。壁面スクリーンの中でどんな楽しげな建築風景を立ち上げてみせても、飽きっぽい子供らの心を掴むのは難しかった。無用者として過ごす日々は辛かった。
子供は正直だ。視覚だけでは満足しない。触って、走り回って、その全身を浸すことができる刺激に、ヒトは飢えているのだ。眠るイサベルが、きっとそうであるように。

2060年5月12日
ホセは最近、焦りを見せるようになった。
もう、1年が過ぎたのか。季節の過ぎる速さに、私も少し慄いている。だが暦はただの数字だ。私は明日も明後日も、イサベルの霧の中で働き続ける。それだけだ。
彼女の頭を包むヘルメットに命令を送ると、神経細胞が刺激を受け、その興奮が脳の広範囲に伝播する。すると霧の世界はにわかに明るくなり、未完成の大聖堂の緻密な輪郭をぼうっと浮かび上がらせる。
その巨大な影を見上げるとき、私は自分の目指すものの複雑さに呆れ、震える。
本当に、こんな構想が実現できるのか。実現できたとして、本当にイサベルが目を覚ます保証もない。それでも仕事に打ち込んでいれば疑念を忘れられる。少しずつだが、たしかに前進していると思うのだ。
大聖堂の壁面で、無数の彫刻が蠢く。モザイクタイルのトカゲたちがざらざらと身を擦り合う。鳴き声を上げ、芳しい香気を発する。その鱗に、三角形や菱形や扇形といった幾何学を纏っている。
今、まさに発達中である大聖堂の上層では、黒鉄の竜の群れがひしめいている。鋭い棘で覆われた胴を震わせ、両翼を広げ、長い首と尾を振り回す。喉の奥から七色の火や柔らかい雲を噴き出し、互いに噛みつき合う。竜たちの身体は徐々に冷えて、いつしか大聖堂の構造体――二重螺旋の柱やカテナリー曲線のアーチを形作る。そこにトカゲたちがよじ登り、緻密な壁面を構成していく。
私は、イサベルの脳の特定の箇所を狙って電気刺激を加える。シナプス接続の強度を調節し、神経回路を微妙に変える。すると霧の中に新種の幻獣が生まれ、新たな感触や匂いや動きを伴って大聖堂に融合していく。
私が使うことができる建材は、イサベルの脳の中にあるものだけだ。彼女が8歳までに取り込んだ外界の情報は、人々や家や街や草木や気象現象だけではない。絵本や玩具を通して触れ合った空想上の生き物たちも、彼女の世界の重要な一部だ。むしろ、彼女の意識を揺り動かす力は、空想の存在の方が強いように感じるのだ。
ときおり、霧の世界全体がゆっくりと振動することがある。トカゲや竜が興奮して、大聖堂も根本からぐらぐら揺れる。
世界の震えは、脳の奥底に沈んだイサベルの意識の応答なのではないだろうか。建設を進めるほど、そんな手応えが強まっている。私が作るものに、イサベルは脳を震わせてくれているのだと思う。それが、私の原動力だ。イサベルは――私のパトロンなのだ。
2061年4月2日
今日は、イサベルの誕生日だ。
ホセが彼女の両親と話している。両親の語気は強い。人工知能などにいつまで娘の脳を弄らせるつもりなのか――と問うている。医師は、追い詰められている。
私もつい最近知ったことだが、ホセはこの治療を始めるにあたって、叶えられない約束をしてしまったのだ。イサベルは11歳の誕生日を、病院のベッドではなく自宅の特等席で迎えられるだろう、などと。
しかし私たちは11歳どころか、12歳の誕生日にも間に合わなかった。
13歳の誕生日に間に合う保証も、ない。
ああ、時間が流れた。少女が眠ったままでいるには長すぎる時間が。
彼女の両親は、期待することに疲れてしまっている。
だが、もうすぐだ。大聖堂はじきに完成する。その先に何が待っているのか、私には分からない。それでも――。
2061年4月29日
今日、ホセから仕事の終了を告げられた。
「アントニ、すまない。時間切れだ。彼女の両親は、僕らをもう信じてくれない」
「やめるつもりはない」と私は答えた。
「君がどんなつもりでも、もう無理なんだ。これ以上続ければ、犯罪になる」
「どうしてだ。あとほんの少しなんだぞ。せめて、せめて完成までは――」
「完成まで? それは半年後か? 1年後か? 今年2月の段階で、9割は出来上がったと君は言ったな。今、改めて聞こう。今は何割だ」
「あと、ほんの1割だ。完成には近づいてる。信じてくれ」
「なあアントニ。もう、充分じゃないか。こんなに壮大な世界を作っても、患者が目を覚ます気配すらない。そもそもの仮説が間違っていたんだ」
「彼女は今も、私の建築に反応している」
語気を強める私に、医師は悲しげに首を振った。
「知り合いの医師から連絡が来たんだ。彼女も僕らとほぼ同様の方法で昏睡治療を試みていたが、先日、患者が亡くなったと。脳への介入が原因かどうかは分からない。だが、その報告はうちの医局長にも伝わってしまった。僕は責任を取ることになる。そして君も――」
「頼む。頼むから、あと1週間だけ、私に時間をくれ」
ただ、懇願した。
自分がもう失敗したことは分かっている。自分が、病院の設備の一部でしかないことも分かっている。
残ったのは意地だけだ。
「明日、午前中の3時間だけだ」
それがホセの精一杯の譲歩だった。
2061年4月30日
今日、霧の中で、大聖堂の最後の姿を見た。
大きな広場を、トカゲや竜や、そのほか幾多の幻獣たちが行き交う。大聖堂の基部はもはや高低差のある広場と一体化して、どこまでが地形でどこからが建物なのか、区別がつかない。大聖堂は緻密な輪郭をうねらせて遥か高く36本の尖塔を伸ばし、その先端は未完成のまま、霧の向こうに消えていた。
本物のアントニ・ガウディが現実のバルセロナに遺したサグラダ・ファミリア――聖家族贖罪教会よりもなお、壮麗な夢の統一体だ。
私はそう自負した。せめて私がそう思わなければ、誰も引き継ぐことなく永遠に一時停止するその世界が――イサベルが報われないと思った。
――君のようなアーティフィテクトが責任を取れるわけでもない。
昔ホセはそう言ったが、実際には違った。
私も病院を追い出されることになったのだ。売却先も決まった。私は遠い南米の大都市で、さる富豪のために毎晩、特注の夢を作ることになる。ここでの特異な経験が評価されたということらしい。
私は少しだけ、嬉しくもあるのだ。
そうやって、人間のようにペナルティを課してもらえることが。
*
2067年11月10日
午後、来客があったので、久々に記録しておく。
「あなたが、アントニ・X13γ45・ガウディ?」
私の名を正式に呼ぶ人は珍しい。生まれてから何度もなかったことだ。南米に来てからは単に「45号」とだけ呼ばれているので、なおさら新鮮な響きだった。
客人は、屋敷の庭先のセキュリティをすんなりと通過して私のもとにやってきた。どうやら、主人には連絡済みだったらしい。
彼女は靴が濡れるのも厭わず浅い池に踏み入り、私の目の前にやってきた。池の中央のトカゲ型の噴水こそ、昼間の私の居場所なのだ。
トカゲの両目に埋め込まれたカメラが、彼女の容貌をまじまじと捉えた。年の頃は10代後半だろうか。背は高いが、かなり痩せている。しかし短い黒髪はつややかで健康的だ。その髪にも、茶色い瞳の虹彩のパターンにも、全く覚えがなかった。
「私に何のご用ですか、お嬢さん」
彼女の表情がにわかに華やいだ。
「ホセ・ウエマツ医師に聞いたんです。あなたはここにいるかもしれないって。あの――見てほしいものがあるんです。あなたに」
急に懐かしい名前が出てきて、私は面食らった。
私の困惑をよそに、彼女はリュックサックからケント紙の分厚いノートを引っ張り出した。そのページを開き、こちらに向けた。
それは、大聖堂の絵だった。
イサベル。彼女の脳内の霧の奥にそびえていた、あの威容。緻密な輪郭。その壁面や足元に蠢く幻獣たち。
目の前のノートに描かれているのは、私の記憶そのままではない。しかし見間違えようがなかった。本質的な意味で、構造的に、間違いなく、あの大聖堂だった。
いや――本当に、そうなのか?
私は拭いきれない違和感の正体を探し、答えを見つけた。
それは、完成しているのだ。私が時間切れでたどり着けなかった完全な状態――すべての要素がひとつに調和したという確信の地点を、その絵は静かに示していた。
「ノートを下ろして」と私は言った。「もう一度、顔を見せてください」
客人は素直に従った。改めて、私は目だけでなく彼女の鼻筋を、唇を、おとがいの曲線を見た。記憶の底から、忘れかけていた少女の顔が蘇った。
その髪と虹彩が記憶にないのは当然だ。
彼女はずっとヘルメットをかぶって、目を閉じていたのだから。
「わたしが目を覚ましたのは、あなたが病院を去ってから2カ月後だそうです」
彼女は話しはじめた。
「ホセさんとあなたが何をしてくれたのか、全部を知ったのはつい最近なんです。だからここに来るまでに6年もかかってしまった。でも、目覚めてすぐのときから感じていました。わたしの中に、とても長い夢みたいなものが残っていることを」
「君は――もう18歳か」
はい、とイサベルは笑った。
彼女はホセからの伝言を預かっていた。それはホセなりの、昏睡回復のメカニズムに関する仮説だ。拍子抜けするほど端的で、しかし妙に納得してしまうような理屈だった。
――要するに、未完成で放置したのが良かったんじゃないか。
私たちはずっと間違いを犯していた。そして最後の最後に、不本意だがやむを得ず、正しい治療行為に至ったということだ。
イサベルの脳はたしかに私の大聖堂に反応していた。私はそれに励まされて愚直に完成を目指したが、必要なのは、彼女自身に後を任せることだったのだ。問いを突きつけられた脳は、答えを探らずにはいられない。そのためには高度な判断力が必要で、判断こそ意識の存在意義だ。だから彼女は目覚めた。どうも、そういうことらしいのだ。
「目覚めたばかりのとき、わたしはまた眠りたいと思ったんです」
ノートのページを1枚1枚めくりながら、イサベルは話した。
「だってこの世界は、あなたが頭の中に作ってくれたもうひとつの世界とは違っていた。色褪せて、形も感触もつまらないものばかり。しかも自分は一瞬で8歳から12歳になっていた。子供の心のまま、身体だけが大人になりかけていた。絶望して、いなくなってしまいたいと思って泣きました。でも、結果的には、こうして生きてくることができた」
見事な絵だった。手触りがあり、匂いすらする。本物のガウディに見せても恥ずかしくない作品だと思った。
「それは、物が作れたからです。絵とか、彫刻とか、ぬいぐるみとか――自分でもびっくりするくらい描けて、作れたんです。みんな驚いた。一体、いつの間にそんなに上手くなったのって。そこから、今の私の全部が開けました。なぜそうなったか、分かりますか」
私は何秒も考えた。
「まさか――私が、君の脳に介入したからなのか」
イサベルは私を見つめ、頷いた。
「ホセさんは、それ以外に考えられないって。あなたが2年もかけて、わたしの脳内で世界創造を実演してくれたから。だからわたしは、あなたの弟子なんです」
「アントニ・ガウディの、弟子――」
「いいえ。140年も前に死んだ人じゃなくて、あなたの、弟子です」
私はトカゲの目で、まだ見慣れない新鮮なパターンの瞳と見つめ合った。
それから、私たちはしばらく話した。治療者と患者ではなく、建築家とパトロンでも、師と弟子でもなく――これからの新しい関係が立ち上がってくるまで、話し込んだ。
第5話了
文:津久井五月(つくいいつき):1992年生まれ。栃木県那須町出身。東京大学・同大学院で建築学を専攻。2017年、「天使と重力」で第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ。公益財団法人クマ財団の支援クリエイター第1期生。『コルヌトピア』で第5回ハヤカワSFコンテスト大賞。2021年、「Forbes 30 Under 30」(日本版)選出。作品は『コルヌトピア』(ハヤカワ文庫JA)、「粘膜の接触について」(『ポストコロナのSF』ハヤカワ文庫JA 所収)、「肉芽の子」(『ギフト 異形コレクションLIII』光文社文庫 所収)ほか。変格ミステリ作家クラブ会員。日本SF作家クラブ会員。
画:冨永祥子(とみながひろこ)。1967年福岡県生まれ。1990年東京藝術大学美術学部建築科卒業。1992年東京藝術大学大学院美術研究科修了。1992年~2002年香山壽夫建築研究所。2003年~福島加津也+冨永祥子建築設計事務所。工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。イラスト・漫画の腕は、2010年に第57回ちばてつや賞に準入選し、2011年には週刊モーニングで連載を持っていたというプロ級。
※本連載は月に1度、掲載の予定です。連載のまとめページはこちら↓。