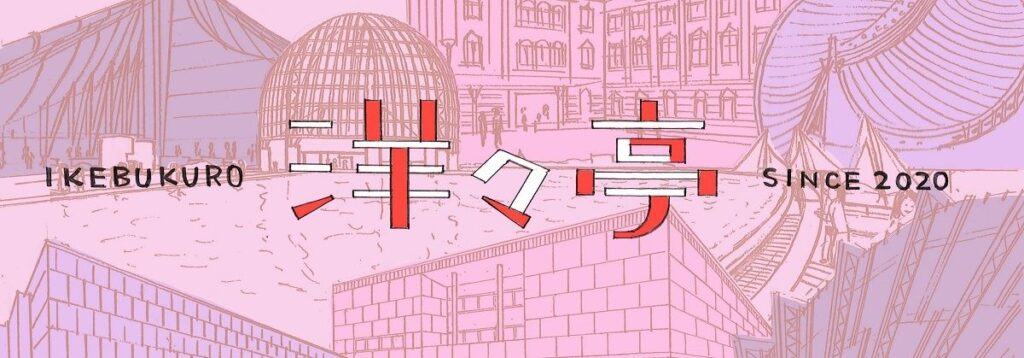坂倉準三の初期の代表作の1つ、羽島市旧庁舎(1959年竣工)の解体が決定したと前回書いた。2022年は中銀カプセルタワーが消え、東京海上ビルの解体が始まり…と、そんな悲報ばかり書いてきたが、唯一「良かった!」と言えるニュースが伊賀市旧庁舎(旧上野市庁舎、設計:坂倉準三、1964年竣工)の活用事業者が決定したことだ。

PFI事業の公募プロポーザルの結果は今年5月に記事にした。
【続報あり】坂倉準三・伊賀市旧庁舎再生事業の交渉権者決定、「MARU。architecture」の参画でさらに期待(2022年5月23日公開、9月30日に追記)
古巣の『日経アーキテクチュア』でも、がっつり12ページの記事を書いた。
日経アーキテクチュアの記事は7月28日号で、この段階では「優先交渉権者」が決まったというフェーズだった。議会で否決される可能性もあったが、幸いにも9月30日に行われた市議会で契約が正式に可決された。今後は「MARU。architecture」を含むSPC(株式会社伊賀市にぎわいパートナーズ)と伊賀市が設計、改修、活用を進めていく。
解体が決定した羽島市との差は何なのか。日経アーキテクチュアでもそういう視点では論じていないので、ポイントを挙げてみる。ちょっと固い話になるので、記事には使えなかったボツ写真を「目の保養」として眺めながら話を進めたい。

Point1:岡本栄市長の執念
元アナウンサーだった岡本市長。2012年、一部の解体が始まっていた市庁舎の保存を訴え、市長に初当選。3期10年にわたり、この問題に取り組んできた。岡本市長でなければ、おそらくこの建築は残っていなかっただろう。ただ、個人の熱意だけで建物が残るわけではない。

Point2:PFIで民活にしたこと
岡本市長はこの件で長く議会と対立していたが、市の直営事業ではなく、PFIにすることでようやく議会の理解が得られた。


Point3:新築と改修をセットに
PFIの公募では、新築事業と改修事業の2つをセットにした。新築は、上野市駅の南西側にある成瀬平馬屋敷跡に建てる「忍者体験施設」。改修は、「旧庁舎→図書館・観光まちづくり拠点等」へのコンバージョンだ。事業者から見ると、旧庁舎を単体で事業化するよりも、新築とセットで考えた方が選択肢が広がる。(一方で、事業者間でチームを組む手間やリスク管理のハードルは上がる)


Point4:市の費用負担がある
応募要項では改修について「予定対価25億3400万円」、それ以外について「予定対価38億8500万円」とした。事業期間はいずれも20年。

「耐震改修は自腹で」は民主的な発注条件か?
羽島市と決定的に違うのは、「Point4:市の費用負担がある」だろう。ここが、この記事で筆者が一番言いたい点だ。


羽島市の民活募集は、「耐震改修は自腹で」という条件だった。現状は耐震上危険なので、自費で改修して安全を確保してから使え、と。これは、既に解体された都城市民会館も同じだ。
筆者はこれが当たり前になることを危惧している。この流れが正当化されると、「民間から実現性のある提案がありませんでした」と市民に説明するための免罪符となる。
一見、民主的な流れに見えるが、このやり方は行政手続きとして奇異に感じる。建物の所有権が耐震改修後に民間に移るならば分かる。そうではなく、自治体の所有のままなのに、耐震改修を自腹でせよというのは、「耐震改修費を寄付しろ」と言っているのに等しい。



羽島市は民活募集に当たり、耐震改修費の目安を公表していた。「最も安価な『枠付鉄骨ブレース・RC壁増設』を採用した場合は5.7億円、最も高価な『免振レトロフィット工法』を採用した場合は20億円」とある。つまり、民間に「20億円寄付せよ」と言っているわけである。普通に民間1社がそんな金額を市に寄付したら、やましい関係だと議会で叩かれるだろう。(PFIでは民間が施設を建てた後に所有権を自治体に移すやり方があるが、その場合は建設の対価を民間に払うのが普通)
羽島市の募集では、改修後の賃料が明示されていなかった。自治体の持ち物なのだから、賃料は安くても支払うべきだろう。市民の安全を確保するための工事費は自治体が負担し、そのうえで事業者から何がしかの賃料を得る。それが行政手続きとして普通ではないか。
民間事業者に「耐震改修は自腹で」と言うのは、自治体が事業性の検討を完全放棄している証しだ。そんな「すべて丸投げ」の無責任な自治体に、資金力のある大企業が力を貸すはずがない。もし筆者が大企業の経営者だったらそう思う。


「耐震改修は自腹で」──。もし公共施設の活用に悩んでいる自治体の職員の方がこれを読んでくれたとしたら、その発想が民主的ルールとして正しいのかを自問してほしい。(宮沢洋)